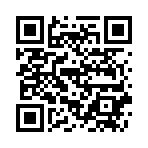テキサスビルのシユーテイングブログ
カウボーイとリボルバーとオートマとの葉巻のぶろぐです
2014年04月09日
ダッチオーブン
ダッチオーブン
移動: 案内、 検索
1890年代製のダッチオーブン。蓋まで灰に覆われている
ダッチオーブン (英語:dutch oven) は、分厚い金属製の蓋つき鍋のうち、蓋に炭火を載せられるようにしたものの名称である。アメリカ合衆国の西部開拓時代などで使用されていたものが有名であるが、近年ではキャンプなどレジャーでの用途に使われることが多い。
目次
[非表示] 1 概要 1.1 素材
1.2 使用法
1.3 種類
1.4 特徴
2 シーズニング
3 日常的な手入れ
4 長期の保管
5 語源
6 関連項目
7 脚注
概要[編集]
素材[編集]
鋳鉄製のものが一般的だが、アルミニウム合金や鋼板製・ステンレスのものもある。ロッジ社のものが特に有名であるが、それ以外にもヤマゼン、キャプテン・スタッグ、ユニフレーム、SOTO等様々なメーカーから多様な商品が販売されている。
使用法[編集]
ダッチオーブンでチリコンカーンを煮るカウボーイ(1930年代、テキサス州にて)
アメリカ合衆国で伝統的に用いられている蓋は全体的に平らなデザインで、周囲に縁取りがあり蓋の上にも炭などの熱源を置くことができ、オーブンと同じように上下から同時に加熱することができる。このようなデザインは、炭火を利用したローストチキンやピザ、パンなどの調理に適している[1]。また、蓋をフライパンのように用いることも不可能ではない。
オーストラリアではキャンプオーブン(camp oven)、フランスではココット(cocotte)と呼ばれている。南アフリカ共和国のポティー(potjie)やバルカン半島のサッチ(sač)もほぼ同じ構造である。これ以外にも日本の南部鉄器などダッチオーブンに似た鋳鉄製の深鍋は存在するが、殆どの場合これらの地域において、鋳鉄製の深鍋は煮込み料理にのみ用いられる。
ダッチオーブンと呼ばれるものは本来、蓋に置かれた炭火を利用したオーブンとしても使える点に特徴を持つ。この形状は北アメリカの、いわゆる「西部開拓」の時期には既に存在していたとされる[要出典]。この点について詳しく解説すると、ダッチオーブンとはその名称の通り、オーブンとしても使用されるものなのであり、その形状はそのような使用法の為に進化してきたものなのである。オーブンとして使用しない鋳鉄製の深鍋であれば、世界各地に存在している。
なお、近年、日本国においては後述のスキレットやコンボクッカーのような製品も「ダッチオーブン」と呼ばれることがある。
種類[編集]
キッチンオーブン2種。手前がフレンチ・オーブン
ダッチオーブンには用途に応じて以下のような種類がある。
キャンプオーブン - 野外活動での使用が前提で、焚き火にくべやすいよう三本の足を持っている。蓋の上にさらに何段かオーブンを積み重ねることもでき、蓋の上の炭を上下両方の鍋の加熱に使えて効率的である。
キッチンオーブン - 台所での使用が前提で、コンロにかけやすいよう底が平らになっている。このデザインをもとに、使いやすいよう改良されたものを「モダン・ダッチ・オーブン」と呼ぶこともある。フランスのル・クルーゼ社の製品が有名であるが、ル・クルーゼ社は自社の製品を「フレンチ・オーブン」と呼称している。
スキレット - いわゆるフライパンタイプの鍋だが、ダッチオーブンの特徴である厚みがあるため温度変化が少ない。
コンボクッカー - 深鍋とスキレットを組み合わせたもので、スキレットが蓋の替わりとなる。
特徴[編集]
鍋に厚みがあることで、温度変化が少なく鍋全体が均一の温度に保たれ、食材にじっくりと火が通る。 また、食材から出た水分による水蒸気が蓋と鍋の隙間を埋めて、蓋本来の重さも手伝って密閉状態になる。 この状態で暖め続けられると、内部の気圧が高くなり圧力鍋と同じ状態になる。さらに、水分が蒸気として逃げないため食材の水分を利用した無水調理がしやすい(ただしこれらはダッチオーブンにしか出来ない調理法というわけではない)。
シーズニング[編集]
「ダッチオーブン」として製造販売されている鋳鉄製の深鍋の愛好者は、多くの場合、「シーズニング」と呼ばれる独特の作業を行う(一般的なシーズニングの方法は後述)。これは意図的に鍋に黒錆(四酸化三鉄皮膜)を発生させることで、鍋の腐食を防止する技術である。他地域の鋳鉄製の深鍋の使用者はこうした作業を行わない(毎日のように使う鍋であれば、使用後に空焚きして乾かしているうちに放っておいても黒錆びがつく)。
シーズニングによって黒錆びが発生したダッチオーブンの中でも、長年の使用によって重厚な黒錆びが付着しているものは「ブラック・ポット」と呼ばれて美的鑑賞の対象になることがある。
シーズニングの一般的な手順を以下に示す。
1.錆止めオイルを、洗剤を使って丁寧に洗い落とししっかりと乾燥させる(新品時のみ)
2.鍋と蓋に食用の植物油(菜種油、大豆油、オリーブ油、グレープシード油など何でも良いが、ヒマシ油は不可)を薄く塗り、30分から60分ほど火にかけて熱し、自然冷却させる。 この作業を2~3回繰り返すこともある
3.鉄臭さをとるため、鍋にネギやショウガなどの香りの強い野菜クズを入れて炒める これを2~3回繰り返すこともある
4.洗剤や金属たわしは使用せずにスポンジや亀の子たわし等で洗い、火にかけて空焼きして乾燥させる。
日常的な手入れ[編集]
調理後は、基本的には洗剤や金属たわしを使わずに洗い、火にかけてよく乾燥させる(料理の種類によっては洗剤を使用するのも選択肢の一つである)。この状態からさらに植物油を薄く塗布する者もいるが、数日以内に再使用するような場合は不要である。
焦げつきがひどい場合には、そのまま火にかけ続けて完全に炭化させて、へらなどでこそげ落とす。毎日のように使う鍋であれば、金属たわしで掻き落としてからさっと空焼きして再び黒錆びをつけてやるだけでも良い。
よく誤解されるところであるが、きちんと黒錆びがついた鉄鍋は洗剤を付けた程度ではコンディションは変化しない。そもそも黒錆びとは強靱な酸化鉄の皮膜であり、洗剤とは界面活性剤である。界面活性剤は酸化鉄の皮膜のさらに表面に残った油脂を洗い流しはするが、四酸化三鉄皮膜を侵すものではない。鉄鍋は基本的に四酸化三鉄皮膜によって保護されているのであって、表面に残留した油脂分によってではない。もちろん年に数回しか使用しないような場合、油を引くに越したことはないが、頻繁に使用する場合は黒錆びの皮膜だけで充分である。
長期の保管[編集]
年に数回のキャンプにしか使わない場合には、前述の通り植物油を薄く塗布してから鍋の中に新聞紙などを入れて内部に湿気が籠もらない様にして、風通しの良い場所に保管する。再使用する際には洗剤とスポンジあるいは亀の子たわしを用いて表面の油脂分を洗い流す。長期間鍋の表面にあった油は酸化してしまっており、生体に害をなす。
語源[編集]
ダッチオーブン、「オランダ人のオーブン」という語源には諸説あるが定かではない。主なものには、オランダ系移民が売り歩いていた鍋であったとする説、ダッチと呼ばれた人物が発明したとする説、オランダの鋳造技術を利用したためとする説などがある。またイギリス人は「~もどき」の品物を「ダッチ~」と呼ぶ習慣があるため、本物のオーブンではないがオーブンとして使える鍋を「オーブンもどき」すなわちダッチオーブンと呼んだという説もある

移動: 案内、 検索
1890年代製のダッチオーブン。蓋まで灰に覆われている
ダッチオーブン (英語:dutch oven) は、分厚い金属製の蓋つき鍋のうち、蓋に炭火を載せられるようにしたものの名称である。アメリカ合衆国の西部開拓時代などで使用されていたものが有名であるが、近年ではキャンプなどレジャーでの用途に使われることが多い。
目次
[非表示] 1 概要 1.1 素材
1.2 使用法
1.3 種類
1.4 特徴
2 シーズニング
3 日常的な手入れ
4 長期の保管
5 語源
6 関連項目
7 脚注
概要[編集]
素材[編集]
鋳鉄製のものが一般的だが、アルミニウム合金や鋼板製・ステンレスのものもある。ロッジ社のものが特に有名であるが、それ以外にもヤマゼン、キャプテン・スタッグ、ユニフレーム、SOTO等様々なメーカーから多様な商品が販売されている。
使用法[編集]
ダッチオーブンでチリコンカーンを煮るカウボーイ(1930年代、テキサス州にて)
アメリカ合衆国で伝統的に用いられている蓋は全体的に平らなデザインで、周囲に縁取りがあり蓋の上にも炭などの熱源を置くことができ、オーブンと同じように上下から同時に加熱することができる。このようなデザインは、炭火を利用したローストチキンやピザ、パンなどの調理に適している[1]。また、蓋をフライパンのように用いることも不可能ではない。
オーストラリアではキャンプオーブン(camp oven)、フランスではココット(cocotte)と呼ばれている。南アフリカ共和国のポティー(potjie)やバルカン半島のサッチ(sač)もほぼ同じ構造である。これ以外にも日本の南部鉄器などダッチオーブンに似た鋳鉄製の深鍋は存在するが、殆どの場合これらの地域において、鋳鉄製の深鍋は煮込み料理にのみ用いられる。
ダッチオーブンと呼ばれるものは本来、蓋に置かれた炭火を利用したオーブンとしても使える点に特徴を持つ。この形状は北アメリカの、いわゆる「西部開拓」の時期には既に存在していたとされる[要出典]。この点について詳しく解説すると、ダッチオーブンとはその名称の通り、オーブンとしても使用されるものなのであり、その形状はそのような使用法の為に進化してきたものなのである。オーブンとして使用しない鋳鉄製の深鍋であれば、世界各地に存在している。
なお、近年、日本国においては後述のスキレットやコンボクッカーのような製品も「ダッチオーブン」と呼ばれることがある。
種類[編集]
キッチンオーブン2種。手前がフレンチ・オーブン
ダッチオーブンには用途に応じて以下のような種類がある。
キャンプオーブン - 野外活動での使用が前提で、焚き火にくべやすいよう三本の足を持っている。蓋の上にさらに何段かオーブンを積み重ねることもでき、蓋の上の炭を上下両方の鍋の加熱に使えて効率的である。
キッチンオーブン - 台所での使用が前提で、コンロにかけやすいよう底が平らになっている。このデザインをもとに、使いやすいよう改良されたものを「モダン・ダッチ・オーブン」と呼ぶこともある。フランスのル・クルーゼ社の製品が有名であるが、ル・クルーゼ社は自社の製品を「フレンチ・オーブン」と呼称している。
スキレット - いわゆるフライパンタイプの鍋だが、ダッチオーブンの特徴である厚みがあるため温度変化が少ない。
コンボクッカー - 深鍋とスキレットを組み合わせたもので、スキレットが蓋の替わりとなる。
特徴[編集]
鍋に厚みがあることで、温度変化が少なく鍋全体が均一の温度に保たれ、食材にじっくりと火が通る。 また、食材から出た水分による水蒸気が蓋と鍋の隙間を埋めて、蓋本来の重さも手伝って密閉状態になる。 この状態で暖め続けられると、内部の気圧が高くなり圧力鍋と同じ状態になる。さらに、水分が蒸気として逃げないため食材の水分を利用した無水調理がしやすい(ただしこれらはダッチオーブンにしか出来ない調理法というわけではない)。
シーズニング[編集]
「ダッチオーブン」として製造販売されている鋳鉄製の深鍋の愛好者は、多くの場合、「シーズニング」と呼ばれる独特の作業を行う(一般的なシーズニングの方法は後述)。これは意図的に鍋に黒錆(四酸化三鉄皮膜)を発生させることで、鍋の腐食を防止する技術である。他地域の鋳鉄製の深鍋の使用者はこうした作業を行わない(毎日のように使う鍋であれば、使用後に空焚きして乾かしているうちに放っておいても黒錆びがつく)。
シーズニングによって黒錆びが発生したダッチオーブンの中でも、長年の使用によって重厚な黒錆びが付着しているものは「ブラック・ポット」と呼ばれて美的鑑賞の対象になることがある。
シーズニングの一般的な手順を以下に示す。
1.錆止めオイルを、洗剤を使って丁寧に洗い落とししっかりと乾燥させる(新品時のみ)
2.鍋と蓋に食用の植物油(菜種油、大豆油、オリーブ油、グレープシード油など何でも良いが、ヒマシ油は不可)を薄く塗り、30分から60分ほど火にかけて熱し、自然冷却させる。 この作業を2~3回繰り返すこともある
3.鉄臭さをとるため、鍋にネギやショウガなどの香りの強い野菜クズを入れて炒める これを2~3回繰り返すこともある
4.洗剤や金属たわしは使用せずにスポンジや亀の子たわし等で洗い、火にかけて空焼きして乾燥させる。
日常的な手入れ[編集]
調理後は、基本的には洗剤や金属たわしを使わずに洗い、火にかけてよく乾燥させる(料理の種類によっては洗剤を使用するのも選択肢の一つである)。この状態からさらに植物油を薄く塗布する者もいるが、数日以内に再使用するような場合は不要である。
焦げつきがひどい場合には、そのまま火にかけ続けて完全に炭化させて、へらなどでこそげ落とす。毎日のように使う鍋であれば、金属たわしで掻き落としてからさっと空焼きして再び黒錆びをつけてやるだけでも良い。
よく誤解されるところであるが、きちんと黒錆びがついた鉄鍋は洗剤を付けた程度ではコンディションは変化しない。そもそも黒錆びとは強靱な酸化鉄の皮膜であり、洗剤とは界面活性剤である。界面活性剤は酸化鉄の皮膜のさらに表面に残った油脂を洗い流しはするが、四酸化三鉄皮膜を侵すものではない。鉄鍋は基本的に四酸化三鉄皮膜によって保護されているのであって、表面に残留した油脂分によってではない。もちろん年に数回しか使用しないような場合、油を引くに越したことはないが、頻繁に使用する場合は黒錆びの皮膜だけで充分である。
長期の保管[編集]
年に数回のキャンプにしか使わない場合には、前述の通り植物油を薄く塗布してから鍋の中に新聞紙などを入れて内部に湿気が籠もらない様にして、風通しの良い場所に保管する。再使用する際には洗剤とスポンジあるいは亀の子たわしを用いて表面の油脂分を洗い流す。長期間鍋の表面にあった油は酸化してしまっており、生体に害をなす。
語源[編集]
ダッチオーブン、「オランダ人のオーブン」という語源には諸説あるが定かではない。主なものには、オランダ系移民が売り歩いていた鍋であったとする説、ダッチと呼ばれた人物が発明したとする説、オランダの鋳造技術を利用したためとする説などがある。またイギリス人は「~もどき」の品物を「ダッチ~」と呼ぶ習慣があるため、本物のオーブンではないがオーブンとして使える鍋を「オーブンもどき」すなわちダッチオーブンと呼んだという説もある

Posted by テキサスビル
at 16:50
│Comments(0)