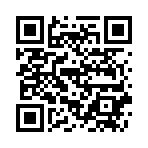テキサスビルのシユーテイングブログ
カウボーイとリボルバーとオートマとの葉巻のぶろぐです
2014年04月18日
続・夕陽のガンマン

続・夕陽のガンマン
移動: 案内、 検索
続・夕陽のガンマン
Il buono, il brutto, il cattivo
監督
セルジオ・レオーネ
脚本
フリオ・スカルペッリ
セルジオ・レオーネ
ルチアーノ・ヴィンチェンツォーニ
製作
アルベルト・グリマルディ
出演者
クリント・イーストウッド
リー・ヴァン・クリーフ
イーライ・ウォラック
音楽
エンニオ・モリコーネ
撮影
トニーノ・デリ・コリ
編集
エウジェニオ・アラビソ
ニノ・バラグリ
配給
ユナイテッド・アーティスツ
公開
1966年12月23日
1967年12月29日
1967年12月30日
上映時間
174分
製作国
イタリア
言語
イタリア語
製作費
$1,200,000
前作
夕陽のガンマン
テンプレートを表示
『続・夕陽のガンマン』(伊: Il buono, il brutto, il cattivo、英: The Good, the Bad and the Ugly、原題の意味は「善玉、悪玉、卑劣漢」)は1966年の叙事詩的マカロニ・ウェスタンである。監督はセルジオ・レオーネ、クリント・イーストウッド、リー・ヴァン・クリーフ、イーライ・ウォラックがそれぞれ原題の善玉、悪玉、卑劣漢を演じている。脚本はフリオ・スカルペッリとルチアーノ・ヴィンチェンツォーニ、レオーネによって書かれた。エンニオ・モリコーネが作ったこの映画の音楽は現在でも有名である。また、この映画は『荒野の用心棒』(1964年)と『夕陽のガンマン』(1965年)から続く「ドル箱三部作」の第3作目であるとされている。物語は、南軍の金貨を求めて南北戦争のアメリカを冒険する3人のガンマンを中心に展開する。この映画は西ドイツとイタリア、スペインに共同で制作された。
日本で初めて劇場公開されたときには『続・夕陽のガンマン/地獄の決斗』の題名だったがビデオが発売されたときに『続・夕陽のガンマン』に改められた。また、1967年公開のマカロニ・ウェスタンに『新・夕陽のガンマン/復讐の旅』(原題:Da uomo a uomo)という作品があるが本作及び『夕陽のガンマン』とは一切関係ない作品である。なお『続・夕陽のガンマン』という題名ではあるが作品の中に夕陽が出てくる場面は1度もない。
原題の Il buono, il brutto, il cattivo を直訳すると「善玉、卑劣漢、悪玉」であるが、英題(The Good, the Bad and the Ugly )では順番が変わって「善玉、悪玉、卑劣漢」となっている。
目次
[非表示] 1 ストーリー
2 キャスト 2.1 トリオ
2.2 その他のキャスト
2.3 日本語吹き替え
3 概要
4 音楽
5 DVD
6 外部リンク
ストーリー[編集]
舞台は南北戦争の時代の荒野。最初に卑劣漢、悪玉、善玉の順で三人のガンマンの紹介が行われる。お尋ね者のトゥーコは、賞金稼ぎの襲撃を逃れる。エンジェル・アイは、ある男の家を訪ね、隠された金貨の情報を聞き出そうとしたあとで、男とその息子を殺し、自分を雇った男も殺す。トゥーコが再び賞金稼ぎに襲われているときに、名無し(ブロンディ)が現れてトゥーコを奪い、保安官に突き出して賞金を受け取る。トゥーコが絞首刑にされる瞬間、ブロンディはロープを打ち抜いてトゥーコを救い出す。
ブロンディとトゥーコはコンビを組んで同じ賞金詐欺を繰り返し、せしめた賞金を“公平に”分け合う。トゥーコにうんざりしたブロンディは、トゥーコを砂漠に置き去りにして立ち去る。生き延びたトゥーコは盗んだ拳銃でブロンディを脅し、砂漠を歩かせて死なせようとする。そこに南軍の兵士の死体を乗せた馬車が通りかかる。馬車には金貨を隠した墓地を知っている眼帯の男(ビル・カーソン)が乗っており、トゥーコは瀕死のビルから墓地の場所、ブロンディは墓碑の名前を聞き出す。
墓地の場所を知っているトゥーコと墓碑の名前を知っているブロンディは、再びコンビを組む。トゥーコはビルの着ていた南軍の軍服と眼帯をまとい、死にそうなブロンディにも南軍の軍服を着せ、聖職者である兄の病院に担ぎ込む。回復したブロンディとトゥーコは南軍の馬車で出発するが、北軍に捕まり捕虜収容所に送られる。北軍の下士官となり収容所に潜り込んでいたエンジェル・アイはビルの軍服を着ていたトゥーコを拷問にかけるが、ブロンディが情報を持っていると知り、ブロンディと手下を連れて金貨探しに出発する。収容所から移送される列車から脱走したトゥーコはブロンディと合流し、二人はエンジェル・アイの手下を撃ち殺すが、エンジェル・アイは逃れる。
トゥーコとブロンディは南北両軍が橋を巡って争う戦場にたどり着き、捕まりそうになったトゥーコは咄嗟に北軍の志願兵を名乗る。延々と繰り返される殺戮に厭きた北軍大尉の願いもあり、二人は橋にダイナマイトを仕掛けて爆破する。その間際、お互いにトゥーコは墓地の場所(サッド・ヒルの墓地)、ブロンディは墓碑の名前(アーチ・スタントン)を告げる。両軍が去ったあとで二人は川を渡るが、南軍側の陣地は死屍累々たる有様だった。トゥーコは隙をついて先駆けしようとするが、それを見越したブロンディの砲撃を受けてほうほうの体で墓地にたどり着く。トゥーコは墓を見つけて素手で掘り返すが、ブロンディが銃口を向け、シャベルを投げる。そこにエンジェル・アイが現れ、ブロンディにも銃口を向け、再びシャベルを投げる。
あばかれたアーチ・スタントンの墓には金貨はなかった。本当の隠し場所を知っているブロンディは、三人による決闘を提案し、隠し場所の名前を書いた石を置く。かくして、金貨を巡る三人の男の決闘が始まった。
キャスト[編集]
トリオ[編集]
クリント・イーストウッド - “ブロンディ”:善玉、別名名無しの男
リー・ヴァン・クリーフ - エンジェル・アイ:悪玉、イタリア語版と脚本では「センテンサ」(字幕版では「エンジェル」、吹き替え版では「ハゲタカ」)
イーライ・ウォラック - トゥーコ:卑劣漢、トゥーコ・ベネディクト・パシフィコ・フアン・マリア・ラミレス(吹き替え版ではトーコ)
その他のキャスト[編集]
アルド・ジュフレ - 北軍の大尉、酔っぱらいの軍人
マリオ・ブレガ - ウォレス伍長、捕虜収容所の軍人
ルイジ・ピスティリ - パブロ・ラミレス神父、トゥーコの兄
アル・ミューロック - 隻腕の賞金稼ぎ
アントニオ・カサス - スティーヴンス
アントニオ・カサール - ビル・カーソン/ジャクソン
セルジオ・メンディザバル - ブロンディ登場シーンでの、金髪の賞金稼ぎ
ジョン・バーサ - 保安官、ブロンディに金を渡す
クラウディオ・スカラチリ - ‘ペドロ’、トゥーコの仲間
サンドロ・スカラチリ - ‘チコ’、トゥーコの仲間
アントニオ・モリノ・ロホ - ハーパー大尉、エンジェル・アイを軍法会議にかけようとする
ベニート・ステファネリ - エンジェル・アイの部下、トゥーコが殺害
アルド・サンブレル - エンジェル・アイの部下、ブロンディが殺害
ロレンツォ・ロブレド - クレム、ブロンディが殺害
エンゾ・ペティト - 銃砲店の店主
リヴィオ・ロレンゾン - ベイカー、エンジェル・アイを雇ってスティーヴンスを尋問
ラダ・ラシモフ - マリア、ビル・カーソンの恋人
チェロ・アロンソ - スティーヴンスの妻
日本語吹き替え[編集]
俳優
NETテレビ版・DVD
クリント・イーストウッド
山田康雄 (多田野曜平)
リー・ヴァン・クリーフ
納谷悟朗 (納谷悟朗)
イーライ・ウォラック
大塚周夫 (大塚周夫)
()内は「日本語吹替完声版」での追加収録部分の担当声優
初放送:1973年10月7日NETテレビ「日曜洋画劇場」(21:00-23:30の拡大放送)
上記のメインキャストの他に小林清志(「日本語吹替完声版」にも参加)、大宮悌二、蟹江栄司、北山年夫が吹き替えを担当している。
2009年12月11日、セルジオ・レオーネ監督の生誕80周年を記念して『夕陽のガンマン』『続・夕陽のガンマン』、『夕陽のギャングたち』を収録した6枚組のDVDセットが日本で発売された。「セルジオ・レオーネ 生誕80周年記念 夕陽コレクターズBOX -日本語吹替完声版- 」と題され、『夕陽のガンマン』、『続・夕陽のガンマン』はテレビ放送でカットされた部分の吹き替えが追加収録されている。イーストウッドの吹き替えは逝去した山田康雄の代わりに多田野曜平が担当し、それ以外の主要な役はテレビ版と同じ声優陣が再び声を当てている(「続・夕陽のガンマン アルティメットエディション」に収録されていた日本語吹き替えは再放送時の短尺版だが、「日本語吹替完声版」では初回放送の最長版がはじめてDVDに収録された)。
概要[編集]
『続・夕陽のガンマン』は1500人の地方兵をエキストラに使い、60トンの爆薬を使用し、160万ドルで製作された(ただし、当時のハリウッド映画としてはむしろ低予算である)。映画のロケーション撮影はスペインで行われた。本作品はセルジオ・レオーネの他の監督作品である『荒野の用心棒』、『夕陽のガンマン』と共にゆるやかな三部作を構成している。また、この映画の「ブロンディ」は、イーライ・ウォラック演じるトゥーコが付けた渾名である。
ファンの中には、本作品は前二作よりも過去の話だと解釈する者もいる。イーストウッド演じる「名無し」が映画の中盤になって前二作のトレードマークの青いシャツ・ベスト・テンガロンハットをエンジェル・アイから貰って着用し、終盤になって南軍の兵士が倒れている戦場からポンチョを手に入れ着るからである。しかし、三部作にはつながりや順番を示すようなものはない。マカロニ・ウェスタンの研究家クリストファー・フレイリングは、『セルジオ・レオーネ―西部劇神話を撃ったイタリアの悪童』の中で、これら三つの映画はレオーネも共同の脚本家も、同じ人物の物語とは意図していなかったと指摘している。もっとも、配給会社のユナイテッド・アーティスツは、イーストウッドの「名無し」役による三作はシリーズ物であると宣伝した。
また、本作は南北戦争時代を舞台としているので、前二作で主に使用された銃であるコルト・シングル・アクション・アーミーは1873年より製造され始めたため使われていない。ブロンディーはコルトM1851・ネイヴィーを使用(ただし、前二作と同様グリップには蛇の模様は描かれている)。トゥーコも蛇の模様は無いが同様のコルトM1851を使用し、エンジェル・アイはレミントンM1858・ニューアーミーを使用している。以上のように、疎かに描写されがちな銃器を精密に描いた、銃器時代考証も見どころと評される。
また、この映画はレオーネの特徴的な演出でも有名である。つまり、少ない会話、ゆっくりとクライマックスを築く長いシーン、遠景のショットと人物の目や手への極端なクローズアップの対比、といった特徴である。この映画の最初の10分には、何の会話もない。映画中のセリフのほとんどはトゥーコのものである。
音楽[編集]
『続・夕陽のガンマン』は、エンニオ・モリコーネによる音楽でよく知られている。一連のリフに砲声や口笛が混ぜられているテーマ曲は、もっとも西部劇的な音楽だと言われる。モリコーネはこのテーマ曲をコヨーテの遠吠えに似せたつもりだったと語っている。墓地におけるクライマックスの音楽も注目すべきもので、まず有名な「黄金のエクスタシー」(原題:L'Estasi Dell'Oro)が流れ、次の三人による対決には「トリオ」(原題:Il Triello)が流れる。モリコーネの楽曲は、映画史の中でもっとも衝撃的なクライマックスの一つとされるこの叙事詩的な三人の対決を大いに盛り上げている。
2014年04月18日
荒野の用心棒
荒野の用心棒
移動: 案内、 検索
この項目では、1964年のイタリアの映画について記述しています。
荒野の用心棒
Per un pugno di dollari
監督
セルジオ・レオーネ
脚本
ヴィクトル・アンドレス・カテナ
ハイメ・コマス・ギル
セルジオ・レオーネ
製作
アリゴ・コロンボ
ジョルジオ・パピ
出演者
クリント・イーストウッド
マリアンネ・コッホ
ジャン・マリア・ヴォロンテ
音楽
エンニオ・モリコーネ
配給
東和
公開
1964年9月16日
1965年12月25日
1967年1月18日
上映時間
96分
100分(完全版)
製作国
イタリア
スペイン
言語
イタリア語
製作費
$200,000
興行収入
$11,000,000
次作
夕陽のガンマン
テンプレートを表示
『荒野の用心棒』(伊: Per un pugno di dollari、英: A Fistful of Dollars、原題の意味は「一握りのドルのために」であり、よく知られる英題を訳した「一握りのドル」は誤りであると同時に次作『夕陽のガンマン』との題名上での繋がりもより鮮明になる)は、1964年にイタリアで制作されたマカロニ・ウェスタンである。監督はセルジオ・レオーネ、出演者はクリント・イーストウッド、ジャン・マリア・ヴォロンテ、マリアンネ・コッホなど。
1964年にイタリアで公開され、1965年に日本、1967年にアメリカで公開された。この映画によってマカロニ・ウェスタンというジャンルが確立される。この映画の後にイーストウッド主演による『夕陽のガンマン』、『続・夕陽のガンマン』の2作が制作され、『荒野の用心棒』と合わせて「ドル箱三部作」と呼ばれる。
この映画は黒澤明監督の『用心棒』(1961年)を非公式にリメイクした作品である。『用心棒』を制作した東宝は彼らを訴え、勝訴している。アメリカではユナイテッド・アーティスツがイーストウッドの演じたキャラクターを「名無しの男」として宣伝した。
初のマカロニ・ウェスタン作品であるため、アメリカでの公開時にはヨーロッパ系のキャスト・スタッフの多くがアメリカ風の偽名を使った。レオーネ監督("ボブ・ロバートソン"名義)やジャン・マリア・ヴォロンテ("ジョニー・ウェルズ"名義)、エンニオ・モリコーネ("ダン・サヴィオ"名義)たちも本名を使わなかった。
1966年公開のマカロニ・ウェスタンに『続・荒野の用心棒』(原題:Django)という作品があるが本作とは一切関係ない作品である。
目次
[非表示] 1 ストーリー
2 キャスト 2.1 日本語吹き替え
3 概要
4 音楽
5 関連作品 5.1 黒澤明の『用心棒』
5.2 影響
6 脚注
7 外部リンク
ストーリー[編集]
ある日、アメリカ=メキシコ国境にある小さな町サン・ミゲルに流れ者のガンマンが現れる。この街ではギャングの2大勢力が常に縄張り争いをしていた。ガンマンは酒場のおやじシルバニトからそれを聞かされる。ガンマンは早撃ちの腕前をギャングたちに売り込み、2大勢力を同士討ちさせようと試みる。
キャスト[編集]
クリント・イーストウッド - ジョー、よそ者(「名無しの男」)
ジャン・マリア・ヴォロンテ(ジョニー・ウェルズ名義) - ラモン・ロホ
マリアンネ・コッホ - マリソル
ホセ・カルヴォ(名前はJosé Calvo、 名義はJose Calvo) - シルバニト(日本語吹き替えではカルロス)
ヨゼフ・エッガー(ジョー・エッガー名義) - ピリペロ、棺桶屋
アントニオ・プリエート - ドン・ミゲル・ベニート・ロホ
ジークハルト・ルップ(S・ルップ名義) - エステバン・ロホ
ウォルフガング・ルスキー(W・ルスキー名義) - ジョン・バクスター保安官
マルガリータ・ロサノ(名前はMargarita Lozano、 名義はMargherita Lozano) - ドナ・コンスエラ・バクスター
ブルーノ・カロテヌート(キャロル・ブラウン名義) - アントニオ・バクスター
マリオ・ブレガ(リチャード・スティフェサント名義) - チコ、ロホの部下
ベニート・ステファネリ(ベニー・リーヴス名義) - ルビオ、ラモンのライフル持ち
ラフ・バルダッサーレ - フアン・テディオス、鐘つき
日本語吹き替え[編集]
俳優
日本語吹き替え
NETテレビ版1
TBS版1
TBS版2
テレビ朝日2・DVD
クリント・イーストウッド
納谷悟朗
夏八木勲
山田康雄
ジャン・マリア・ヴォロンテ
小林清志
内田良平
内海賢二
マリアンネ・コッホ
渡辺典子
弥永和子
ホセ・カルヴォ
富田耕生
根本嘉也
今西正男
富田耕生
ヨゼフ・エッガー
槐柳二
野本礼三
清川元夢
アントニオ・プリエト
加藤精三
加藤精三
ジークハルト・ルップ
羽佐間道夫
田中康郎
羽佐間道夫
ウォルフガング・ルスキー
島宇志夫
大久保正信
仁内建之
島宇志夫
マルガリータ・ロサノ
寺島信子
北村昌子
公卿敬子
ブルーノ・カロテヌート
石森達幸
マリオ・ブレガ
藤本譲
ラフ・バルダッサーレ
杉田俊也
NETテレビ 1 :初回放送1971年1月10日『日曜洋画劇場』 - 演出:春日正伸 翻訳:鈴木導
TBS版 1 :初回放送1974年7月1日『月曜ロードショー』
TBS版 2 :初回放送1976年6月28日『月曜ロードショー』 - 演出:長野武二郎 翻訳:大野隆一
テレビ朝日 2 :初回放送1979年6月24日『日曜洋画劇場』 - 演出:春日正伸 翻訳:鈴木導 効果:赤塚不二夫 P・A・G 調整:山田太平 担当:中島孝三
テレビ朝日 2 では上記のメインキャストの他に浅井淑子、緑川稔、仲木隆司、峰恵研、水鳥鉄夫、向殿あさみ、郷里大輔、笹岡繁蔵たちが吹き替えを担当している。また、このバージョンの日本語吹き替えは2006年12月22日発売のDVD『荒野の用心棒・完全版 スペシャル・エディション』に収録されている。
概要[編集]
イタリアで公開された黒澤明の『用心棒』を見て感銘を受けたセルジオ・レオーネが、日本の時代劇『用心棒』を西部劇に作り変えようとしたのが始まりである。レオーネは同僚の撮影監督や脚本家たちを誘って再度『用心棒』を鑑賞、脚本執筆の参考にするために映画の台詞をそのまま書き写したと言われている[1]。
主演のイーストウッドは当初、第一候補というわけではなかった。セルジオ・レオーネはヘンリー・フォンダの起用を望んでいた。だがフォンダはハリウッド・スターだったため獲得できなかった。その次にチャールズ・ブロンソンに出演依頼をするが彼は脚本が気に入らず、これも実現しなかった。しかし後にヘンリー・フォンダとチャールズ・ブロンソンはレオーネの『ウエスタン』(1968年)に出演することになる。さらにヘンリー・シルヴァ、ロリー・カルホーン、トニー・ラッセル、スティーヴ・リーヴス、タイ・ハーディン、ジェームズ・コバーンらに断られる。そこで代わりに白羽の矢を立てたのが当時テレビ西部劇『ローハイド』でブレイク中だったクリント・イーストウッドだった[1]。この時、イーストウッドが受け取った脚本の題名は「Magnificent Stranger」だったといい、また、その内容は『用心棒』の翻案であることもすぐに読み取った。無名のイタリア人監督がスペインで日本映画の西部劇風リメイクを制作するという如何にも胡散臭い企画ではあったが、『ローハイド』出演の際に他のハリウッド映画に出演できないという契約を結んでいたイーストウッドはヨーロッパへの物見遊山気分半ばでオファーを受諾、無事撮影が開始されることになった。
イーストウッドは名無しの男の役作りに励んだ。彼はブルーのジーンズをハリウッドで、帽子をサンタモニカで、葉巻をビバリーヒルズで買った。また彼は『ローハイド』で使っていた、蛇の飾りがついた銃のグリップも持ち込んだ。ポンチョはスペインで手に入れた。名無しの男の衣装はレオーネと、衣装監督のカルロ・シーミによって決められていった。
撮影はスペインのアルメリア地方で行われた。また、この作品にはアメリカ、ドイツ、イタリアなど様々な国の俳優が出演している。そのため撮影時にはそれぞれの母国語でしゃべり、イタリア公開時にはイタリア語、アメリカ公開時には英語に、セリフが吹き替えられた。
音楽[編集]
この映画の音楽はエンニオ・モリコーネ(ダン・サヴィオ)によって作られた。レオーネはモリコーネに「ディミトリ・ティオムキンの音楽」を作曲するように言った。この映画のトランペットのテーマは『リオ・ブラボー』(1959年)でティオムキンが作った「皆殺しの歌」に似ている。
関連作品[編集]
黒澤明の『用心棒』[編集]
本作品は映画の筋書きや登場人物、演出、台詞などからわかるとおり明らかに黒澤明の『用心棒』の翻案である。クリント・イーストウッドに出演依頼を行う際に「日本映画のリメイクを作る」と伝えている[2]。しかし、監督のセルジオ・レオーネと製作会社は公開にあたり黒澤明の許可を得ていなかった。そのため『用心棒』の製作会社がレオーネたちを著作権侵害だとして告訴、勝訴している。この裁判の結果を受けて『荒野の用心棒』の製作会社は黒澤たちに謝罪し、アジアにおける配給権と全世界における興行収入の15%を支払うことになった[3]。また、この裁判の過程で映画の著作者が受け取る世界の標準額を知った黒澤は東宝に不信感を抱き、契約解除、ハリウッド進出を決意させる要因にもなった。
影響[編集]
1960年代初期からイタリアでは西部劇が作られていたが、そのイタリア製の西部劇、いわゆるマカロニ・ウェスタンが世界的に知られるようになったのは『荒野の用心棒』のアメリカにおける大ヒットからである。その暴力的なシーンを多用した乾いた作風や激しいガン・ファイトが、当時の西部劇の価値観を大きく変えたと言われている[4]。1960年代中盤から1970年代にかけてイタリアでは大量のマカロニ・ウェスタンが量産されるようになったが、現在でもマカロニ・ウェスタンの代表作として本作品を挙げる人は多い。
アメリカに帰国後、再び『ローハイド』に出演していたイーストウッドはヨーロッパ全域で『A Fistful of Dollars』という映画が人気を博しているという噂を耳にしたが、それが自分が主演した「Magnificent Stranger」のことであるとはまったく知らなかった。この作品、及び一連の後続作品の影響で当時、ヨーロッパで最も有名なアメリカ人の一人となり、訪米した多くの著名なヨーロッパ人が彼との会見を希望したが、落ち目のテレビ俳優と認識していた周囲の人たちはその光景が不思議ものに見えていたという。因みに本作が全米で公開されたのは本国公開から3年後の1967年である。
その知名度の高さゆえか本作品は他の映画やアニメ、テレビゲームなどでパロディにされることも多い
移動: 案内、 検索
この項目では、1964年のイタリアの映画について記述しています。

荒野の用心棒
Per un pugno di dollari
監督
セルジオ・レオーネ
脚本
ヴィクトル・アンドレス・カテナ
ハイメ・コマス・ギル
セルジオ・レオーネ
製作
アリゴ・コロンボ
ジョルジオ・パピ
出演者
クリント・イーストウッド
マリアンネ・コッホ
ジャン・マリア・ヴォロンテ
音楽
エンニオ・モリコーネ
配給
東和
公開
1964年9月16日
1965年12月25日
1967年1月18日
上映時間
96分
100分(完全版)
製作国
イタリア
スペイン
言語
イタリア語
製作費
$200,000
興行収入
$11,000,000
次作
夕陽のガンマン
テンプレートを表示
『荒野の用心棒』(伊: Per un pugno di dollari、英: A Fistful of Dollars、原題の意味は「一握りのドルのために」であり、よく知られる英題を訳した「一握りのドル」は誤りであると同時に次作『夕陽のガンマン』との題名上での繋がりもより鮮明になる)は、1964年にイタリアで制作されたマカロニ・ウェスタンである。監督はセルジオ・レオーネ、出演者はクリント・イーストウッド、ジャン・マリア・ヴォロンテ、マリアンネ・コッホなど。
1964年にイタリアで公開され、1965年に日本、1967年にアメリカで公開された。この映画によってマカロニ・ウェスタンというジャンルが確立される。この映画の後にイーストウッド主演による『夕陽のガンマン』、『続・夕陽のガンマン』の2作が制作され、『荒野の用心棒』と合わせて「ドル箱三部作」と呼ばれる。
この映画は黒澤明監督の『用心棒』(1961年)を非公式にリメイクした作品である。『用心棒』を制作した東宝は彼らを訴え、勝訴している。アメリカではユナイテッド・アーティスツがイーストウッドの演じたキャラクターを「名無しの男」として宣伝した。
初のマカロニ・ウェスタン作品であるため、アメリカでの公開時にはヨーロッパ系のキャスト・スタッフの多くがアメリカ風の偽名を使った。レオーネ監督("ボブ・ロバートソン"名義)やジャン・マリア・ヴォロンテ("ジョニー・ウェルズ"名義)、エンニオ・モリコーネ("ダン・サヴィオ"名義)たちも本名を使わなかった。
1966年公開のマカロニ・ウェスタンに『続・荒野の用心棒』(原題:Django)という作品があるが本作とは一切関係ない作品である。
目次
[非表示] 1 ストーリー
2 キャスト 2.1 日本語吹き替え
3 概要
4 音楽
5 関連作品 5.1 黒澤明の『用心棒』
5.2 影響
6 脚注
7 外部リンク
ストーリー[編集]
ある日、アメリカ=メキシコ国境にある小さな町サン・ミゲルに流れ者のガンマンが現れる。この街ではギャングの2大勢力が常に縄張り争いをしていた。ガンマンは酒場のおやじシルバニトからそれを聞かされる。ガンマンは早撃ちの腕前をギャングたちに売り込み、2大勢力を同士討ちさせようと試みる。
キャスト[編集]
クリント・イーストウッド - ジョー、よそ者(「名無しの男」)
ジャン・マリア・ヴォロンテ(ジョニー・ウェルズ名義) - ラモン・ロホ
マリアンネ・コッホ - マリソル
ホセ・カルヴォ(名前はJosé Calvo、 名義はJose Calvo) - シルバニト(日本語吹き替えではカルロス)
ヨゼフ・エッガー(ジョー・エッガー名義) - ピリペロ、棺桶屋
アントニオ・プリエート - ドン・ミゲル・ベニート・ロホ
ジークハルト・ルップ(S・ルップ名義) - エステバン・ロホ
ウォルフガング・ルスキー(W・ルスキー名義) - ジョン・バクスター保安官
マルガリータ・ロサノ(名前はMargarita Lozano、 名義はMargherita Lozano) - ドナ・コンスエラ・バクスター
ブルーノ・カロテヌート(キャロル・ブラウン名義) - アントニオ・バクスター
マリオ・ブレガ(リチャード・スティフェサント名義) - チコ、ロホの部下
ベニート・ステファネリ(ベニー・リーヴス名義) - ルビオ、ラモンのライフル持ち
ラフ・バルダッサーレ - フアン・テディオス、鐘つき
日本語吹き替え[編集]
俳優
日本語吹き替え
NETテレビ版1
TBS版1
TBS版2
テレビ朝日2・DVD
クリント・イーストウッド
納谷悟朗
夏八木勲
山田康雄
ジャン・マリア・ヴォロンテ
小林清志
内田良平
内海賢二
マリアンネ・コッホ
渡辺典子
弥永和子
ホセ・カルヴォ
富田耕生
根本嘉也
今西正男
富田耕生
ヨゼフ・エッガー
槐柳二
野本礼三
清川元夢
アントニオ・プリエト
加藤精三
加藤精三
ジークハルト・ルップ
羽佐間道夫
田中康郎
羽佐間道夫
ウォルフガング・ルスキー
島宇志夫
大久保正信
仁内建之
島宇志夫
マルガリータ・ロサノ
寺島信子
北村昌子
公卿敬子
ブルーノ・カロテヌート
石森達幸
マリオ・ブレガ
藤本譲
ラフ・バルダッサーレ
杉田俊也
NETテレビ 1 :初回放送1971年1月10日『日曜洋画劇場』 - 演出:春日正伸 翻訳:鈴木導
TBS版 1 :初回放送1974年7月1日『月曜ロードショー』
TBS版 2 :初回放送1976年6月28日『月曜ロードショー』 - 演出:長野武二郎 翻訳:大野隆一
テレビ朝日 2 :初回放送1979年6月24日『日曜洋画劇場』 - 演出:春日正伸 翻訳:鈴木導 効果:赤塚不二夫 P・A・G 調整:山田太平 担当:中島孝三
テレビ朝日 2 では上記のメインキャストの他に浅井淑子、緑川稔、仲木隆司、峰恵研、水鳥鉄夫、向殿あさみ、郷里大輔、笹岡繁蔵たちが吹き替えを担当している。また、このバージョンの日本語吹き替えは2006年12月22日発売のDVD『荒野の用心棒・完全版 スペシャル・エディション』に収録されている。
概要[編集]
イタリアで公開された黒澤明の『用心棒』を見て感銘を受けたセルジオ・レオーネが、日本の時代劇『用心棒』を西部劇に作り変えようとしたのが始まりである。レオーネは同僚の撮影監督や脚本家たちを誘って再度『用心棒』を鑑賞、脚本執筆の参考にするために映画の台詞をそのまま書き写したと言われている[1]。
主演のイーストウッドは当初、第一候補というわけではなかった。セルジオ・レオーネはヘンリー・フォンダの起用を望んでいた。だがフォンダはハリウッド・スターだったため獲得できなかった。その次にチャールズ・ブロンソンに出演依頼をするが彼は脚本が気に入らず、これも実現しなかった。しかし後にヘンリー・フォンダとチャールズ・ブロンソンはレオーネの『ウエスタン』(1968年)に出演することになる。さらにヘンリー・シルヴァ、ロリー・カルホーン、トニー・ラッセル、スティーヴ・リーヴス、タイ・ハーディン、ジェームズ・コバーンらに断られる。そこで代わりに白羽の矢を立てたのが当時テレビ西部劇『ローハイド』でブレイク中だったクリント・イーストウッドだった[1]。この時、イーストウッドが受け取った脚本の題名は「Magnificent Stranger」だったといい、また、その内容は『用心棒』の翻案であることもすぐに読み取った。無名のイタリア人監督がスペインで日本映画の西部劇風リメイクを制作するという如何にも胡散臭い企画ではあったが、『ローハイド』出演の際に他のハリウッド映画に出演できないという契約を結んでいたイーストウッドはヨーロッパへの物見遊山気分半ばでオファーを受諾、無事撮影が開始されることになった。
イーストウッドは名無しの男の役作りに励んだ。彼はブルーのジーンズをハリウッドで、帽子をサンタモニカで、葉巻をビバリーヒルズで買った。また彼は『ローハイド』で使っていた、蛇の飾りがついた銃のグリップも持ち込んだ。ポンチョはスペインで手に入れた。名無しの男の衣装はレオーネと、衣装監督のカルロ・シーミによって決められていった。
撮影はスペインのアルメリア地方で行われた。また、この作品にはアメリカ、ドイツ、イタリアなど様々な国の俳優が出演している。そのため撮影時にはそれぞれの母国語でしゃべり、イタリア公開時にはイタリア語、アメリカ公開時には英語に、セリフが吹き替えられた。
音楽[編集]
この映画の音楽はエンニオ・モリコーネ(ダン・サヴィオ)によって作られた。レオーネはモリコーネに「ディミトリ・ティオムキンの音楽」を作曲するように言った。この映画のトランペットのテーマは『リオ・ブラボー』(1959年)でティオムキンが作った「皆殺しの歌」に似ている。
関連作品[編集]
黒澤明の『用心棒』[編集]
本作品は映画の筋書きや登場人物、演出、台詞などからわかるとおり明らかに黒澤明の『用心棒』の翻案である。クリント・イーストウッドに出演依頼を行う際に「日本映画のリメイクを作る」と伝えている[2]。しかし、監督のセルジオ・レオーネと製作会社は公開にあたり黒澤明の許可を得ていなかった。そのため『用心棒』の製作会社がレオーネたちを著作権侵害だとして告訴、勝訴している。この裁判の結果を受けて『荒野の用心棒』の製作会社は黒澤たちに謝罪し、アジアにおける配給権と全世界における興行収入の15%を支払うことになった[3]。また、この裁判の過程で映画の著作者が受け取る世界の標準額を知った黒澤は東宝に不信感を抱き、契約解除、ハリウッド進出を決意させる要因にもなった。
影響[編集]
1960年代初期からイタリアでは西部劇が作られていたが、そのイタリア製の西部劇、いわゆるマカロニ・ウェスタンが世界的に知られるようになったのは『荒野の用心棒』のアメリカにおける大ヒットからである。その暴力的なシーンを多用した乾いた作風や激しいガン・ファイトが、当時の西部劇の価値観を大きく変えたと言われている[4]。1960年代中盤から1970年代にかけてイタリアでは大量のマカロニ・ウェスタンが量産されるようになったが、現在でもマカロニ・ウェスタンの代表作として本作品を挙げる人は多い。
アメリカに帰国後、再び『ローハイド』に出演していたイーストウッドはヨーロッパ全域で『A Fistful of Dollars』という映画が人気を博しているという噂を耳にしたが、それが自分が主演した「Magnificent Stranger」のことであるとはまったく知らなかった。この作品、及び一連の後続作品の影響で当時、ヨーロッパで最も有名なアメリカ人の一人となり、訪米した多くの著名なヨーロッパ人が彼との会見を希望したが、落ち目のテレビ俳優と認識していた周囲の人たちはその光景が不思議ものに見えていたという。因みに本作が全米で公開されたのは本国公開から3年後の1967年である。
その知名度の高さゆえか本作品は他の映画やアニメ、テレビゲームなどでパロディにされることも多い
2014年04月17日
エスグリマ・クリオーラ


エスグリマ・クリオーラ
移動: 案内、 検索
エスグリマ・クリオーラを使ったガウチョの決闘
エスグリマ・クリオーラ(スペイン語 Esgrima criolla)とは、アルゼンチンやウルグアイ、ブラジルにいたガウチョに伝わったナイフ格闘術。
目次
[非表示] 1 概要
2 歴史
3 関連項目
概要[編集]
ファコンというナイフを遣い、ポンチョを盾代わりに遣う。この技法は「カパ・イ・エスパダ」(外套と短剣)と呼ばれる技法で、ヨーロッパの剣術でも見られる技法である。これはスペインのフェンシングの技術が取り入れられたものであるが、現在では独自の発達を遂げた部分もあるという。
ガウチョはがほぼいなくなった現在では護身術として稽古されている。
歴史[編集]
パンパで牧畜を行っていたガウチョにとって、牛から肉や皮を取るためにナイフは元々生活に不可欠な物であり、常に持ち歩いていた。その為ナイフは護身用具としても発達し、独自に進化を遂げてファソンが生まれた。またガウチョは決闘を好み、口論から決闘になる事が日常茶飯事であった。決闘は凄まじいもので、死人が出る事もあったという。
19世紀に入るとその腕前を見込まれてガウチョは各地でカウディーリョ(提督)に率いられてアルゼンチン、ウルグアイ、ブラジルの独立戦争で戦い、アルゼンチンに攻めてきたイギリス軍やインディオも破った。ガウチョはとても勇敢に戦い、人々の尊敬を集めたという。
関連項目[編集]
ガウチョ
2014年04月17日
ガウチョ
ガウチョ
移動: 案内、 検索
この項目では、南米の民族について記述しています。
ガウチョ
ガウチョ
ガウチョ(Gaucho)は、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル南部のパンパ(草原地帯)やアンデス山脈東部に17世紀から19世紀にかけて居住し、主として牧畜に従事していたスペイン人と先住民その他との混血住民である。ウルグアイではガウーチョ、ブラジルではガウーショという発音がより近くなる。
目次
[非表示] 1 語源と成り立ち
2 歴史
3 ガウチョ文学
4 現在
5 関連項目
6 脚注
語源と成り立ち[編集]
ガウチョはグアラニー語の「孤児」や「放浪者」を指した言葉が語源とされるが、マプーチェ族の言葉で「友達」(ガチュ)を表していたという説や、南ブラジルの方言で「牛殺し」(ガウデリオ)を表していたとも言われている。
ガウチョも元々はペルー方面からラ・プラタ地方の開拓にやってきたスペイン人の農業移民だったようだが、インディオとの抗争の中で次第に農業を忘れ、19世紀の後半にラ・プラタ地域全体で1,500万頭~2,000万頭いたとされる程大繁殖した野生の牛や馬を追って生計を立てるようになっていた。このようにしてラ・プラタで生まれたガウチョは1680年のコロニア・デル・サクラメント建設から始まったバンダ・オリエンタルを巡るスペイン、ポルトガルとの抗争の中で次第に南ブラジルにも伝播し、現在のリオ・グランデ・ド・スル州を中心とする範囲ではポルトガル語でガウーショと呼ばれるようになった。
さながらアメリカ合衆国のカウボーイと似ているともいえる。スペイン人と先住民、その他との混血が多くなっていった。ブエノスアイレスやモンテビデオの商人に輸出用の牛や馬の皮革や肉を卸していた。都市の知識人の印象は悪く、今ではアルゼンチン人・ウルグアイ人のアイデンティティとなっている言葉も、17世紀から18世紀にかけてはむしろ下層階級の浮浪者などの人間をネガティブに指したものだった。こうした存在には黒人(アフリカ系アルゼンチン人、アフリカ系ウルグアイ人)なども含まれていたという。
歴史[編集]
19世紀に入るとガウチョは各地のカウディージョに率いられて1806年、1807年にブエノスアイレスに攻めてきたイギリス軍を破り(イギリスのラプラタ侵略(英語版))、武芸の達人としての能力を買われてアルゼンチン、ウルグアイ、ブラジルの独立戦争と内戦に従軍した。
アルゼンチンの歴史家マルチニアモ・レギサモンは「自らの住むランチョにその妻子を残し、給料も衣服も貰うでもなく、時にはわずかに許された悪習とでもいうべき地酒、煙草、マテ茶にも見切りをつけ、進軍ラッパと共に死線を越え、固い誇りを持って旗の下に死ぬ覚悟を持ち、自らを主と頼むものにはいっさい掛値なしに信頼し、白兵戦ともなれば第一番に敵陣に乗り込む──これがガウチョである」と記している。
アルゼンチンでは自らも牧場主であり、若い頃からガウチョに囲まれてガウチョ同然の生活をしていたブエノスアイレス州知事フアン・マヌエル・デ・ロサスの時代(1829年~1852年)に最も優遇され、国内の中央集権派やイギリス、フランスとの戦いで活躍した。チャールズ・ダーウィンが1833年に、荒野の討伐作戦(英語版)でパンパのインディオを討伐するロサスの軍隊を見た時はインディオと戦う英雄としてロサス将軍を賛美しながらも、「混血者や黒人ばかりであり、こんな悪漢然として盗賊風の軍隊は前代未聞である」「ガウチョと農民たちは都会に住む人間たちよりもずっと人間が上だ。ガウチョはいつも気前が良く、親切で、客を持てなす精神を持っている。無礼な者や、不親切な者は見たことがない。自分と自分の国について話すときには非常に謙虚だが、同時に無鉄砲で勇敢でもある」と記している。
1852年のカセーロスの戦い(英語版)によりアルゼンチンでロサスの時代が終わって、1862年に自由主義者バルトロメ・ミトレ(英語版)主導で全アルゼンチンが統一され、アルゼンチン共和国が成立すると、それまでのカウディージョ政治への反動と、西欧への盲目的な信奉により1868年にアルゼンチン大統領に就任したドミンゴ・ファウスティーノ・サルミエント(英語版)に代表される自由主義知識人はガウチョを「根性曲がりの二本足の動物」と呼び、スペイン的な遅れたもの、野蛮なものの見本のように扱い毛嫌いした。1878年から開始されたフリオ・アルヘンティーノ・ロカ(英語版)の砂漠の開拓作戦(英語版)に代表される、パンパ南部、パタゴニアでの主にマプーチェ族をはじめとする一連の狩猟インディオとの戦いでは、ガウチョは先住民の駆逐・殺戮のために徴兵され、ニコラス・アベジャネーダ(英語版)大統領に代表されるアルゼンチンの自由主義者は共に近代化の障壁とみなしたガウチョとインディオを同士討ちさせた。その後のヨーロッパ移民のアルゼンチンへの大規模な入植による牧畜業の発展、所有地の確定と有刺鉄線の導入などにより、パンパが細分され、自由に行き来出来なくなる空間になるとほぼ消滅した。
ガウチョ文学[編集]
1819年に連邦同盟のホセ・アルティーガス(英語版)と共に戦った軍人だった現ウルグアイ出身のバルトロメ・イダルゴ(スペイン語版)が、アルティーガスらの独立運動の失敗が、新しい国家を国民の求めるものにできなかったブエノスアイレスの寡頭支配層の考え方にあると考え、ガウチョをそれまで見られていたような浮浪者ではなく古いヨーロッパに抵抗して新しいアイデンティティを求める、新しい国家の精神を反映する存在として描く、斬新なガウチョ文学(英語版)を開始した。
サルミエントに代表される自由主義知識人はガウチョをスペイン的な遅れたもの、野蛮なものの見本のように扱い毛嫌いしたが、大衆の心性に訴えたガウチョ文学はその後アルゼンチンの作家ホセ・エルナンデスの叙事詩『マルティン・フィエロ(英語版) 』(1872) などによって完成され、その独特な文化や精神性を歌い、アルゼンチンの国民文学となった。
20世紀に入ると、東欧系のユダヤ移民がアルゼンチンに同化する様子を描いた『ユダヤ人のガウチョ』などの作品も生まれた。この作品は発表された当時は前向きに受け止められたが、20世紀後半に映画化されるとなった時にアルゼンチン人の反ユダヤ主義の猛攻撃を受けることになった。ユダヤ人がアルゼンチンの誇るガウチョであってはならないというのがその理由だった。
現在[編集]
19世紀後半以降、職業、社会階層としてのガウチョは消滅したが、それでも現在のアルゼンチン人、ウルグアイ人とブラジル南部のリオグランデ・ド・スル州の住民が誇りをこめてガウチョ(ポルトガル語ではガウーショ)を自称する。アルゼンチンで「とてもガウチョだ」と言えば、寛大で、他人のために自己犠牲を惜しまない人のことになるし、「ガウチョらしく振舞う」といえば自己を犠牲にしても他人のために尽くす人という意味になり、「ガウチョの言葉」といえば、それは「武士の一言」を意味する。旅行者や在住者がしばしば口にする、アルゼンチンとウルグアイにおける強烈な個人主義はガウチョから来ているとも言われる。タンゴの楽曲に「ガウチョの嘆き」があり、強い嫉妬をいだくガウチョが登場する歌詞がついてある。
非常によく間違われているが、職業としての牧人はペオン(アルゼンチン)やヴァケイロ(ブラジル)とよばれる。
関連項目[編集]
ウアッソ
リャネーロ
カウボーイ
グアラニー族
ガウチョの嘆き
パジャドール
パニオロ
草原の追跡(Way of a Gaucho) エスグリマ・クリオーラ

移動: 案内、 検索
この項目では、南米の民族について記述しています。
ガウチョ
ガウチョ
ガウチョ(Gaucho)は、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル南部のパンパ(草原地帯)やアンデス山脈東部に17世紀から19世紀にかけて居住し、主として牧畜に従事していたスペイン人と先住民その他との混血住民である。ウルグアイではガウーチョ、ブラジルではガウーショという発音がより近くなる。
目次
[非表示] 1 語源と成り立ち
2 歴史
3 ガウチョ文学
4 現在
5 関連項目
6 脚注
語源と成り立ち[編集]
ガウチョはグアラニー語の「孤児」や「放浪者」を指した言葉が語源とされるが、マプーチェ族の言葉で「友達」(ガチュ)を表していたという説や、南ブラジルの方言で「牛殺し」(ガウデリオ)を表していたとも言われている。
ガウチョも元々はペルー方面からラ・プラタ地方の開拓にやってきたスペイン人の農業移民だったようだが、インディオとの抗争の中で次第に農業を忘れ、19世紀の後半にラ・プラタ地域全体で1,500万頭~2,000万頭いたとされる程大繁殖した野生の牛や馬を追って生計を立てるようになっていた。このようにしてラ・プラタで生まれたガウチョは1680年のコロニア・デル・サクラメント建設から始まったバンダ・オリエンタルを巡るスペイン、ポルトガルとの抗争の中で次第に南ブラジルにも伝播し、現在のリオ・グランデ・ド・スル州を中心とする範囲ではポルトガル語でガウーショと呼ばれるようになった。
さながらアメリカ合衆国のカウボーイと似ているともいえる。スペイン人と先住民、その他との混血が多くなっていった。ブエノスアイレスやモンテビデオの商人に輸出用の牛や馬の皮革や肉を卸していた。都市の知識人の印象は悪く、今ではアルゼンチン人・ウルグアイ人のアイデンティティとなっている言葉も、17世紀から18世紀にかけてはむしろ下層階級の浮浪者などの人間をネガティブに指したものだった。こうした存在には黒人(アフリカ系アルゼンチン人、アフリカ系ウルグアイ人)なども含まれていたという。
歴史[編集]
19世紀に入るとガウチョは各地のカウディージョに率いられて1806年、1807年にブエノスアイレスに攻めてきたイギリス軍を破り(イギリスのラプラタ侵略(英語版))、武芸の達人としての能力を買われてアルゼンチン、ウルグアイ、ブラジルの独立戦争と内戦に従軍した。
アルゼンチンの歴史家マルチニアモ・レギサモンは「自らの住むランチョにその妻子を残し、給料も衣服も貰うでもなく、時にはわずかに許された悪習とでもいうべき地酒、煙草、マテ茶にも見切りをつけ、進軍ラッパと共に死線を越え、固い誇りを持って旗の下に死ぬ覚悟を持ち、自らを主と頼むものにはいっさい掛値なしに信頼し、白兵戦ともなれば第一番に敵陣に乗り込む──これがガウチョである」と記している。
アルゼンチンでは自らも牧場主であり、若い頃からガウチョに囲まれてガウチョ同然の生活をしていたブエノスアイレス州知事フアン・マヌエル・デ・ロサスの時代(1829年~1852年)に最も優遇され、国内の中央集権派やイギリス、フランスとの戦いで活躍した。チャールズ・ダーウィンが1833年に、荒野の討伐作戦(英語版)でパンパのインディオを討伐するロサスの軍隊を見た時はインディオと戦う英雄としてロサス将軍を賛美しながらも、「混血者や黒人ばかりであり、こんな悪漢然として盗賊風の軍隊は前代未聞である」「ガウチョと農民たちは都会に住む人間たちよりもずっと人間が上だ。ガウチョはいつも気前が良く、親切で、客を持てなす精神を持っている。無礼な者や、不親切な者は見たことがない。自分と自分の国について話すときには非常に謙虚だが、同時に無鉄砲で勇敢でもある」と記している。
1852年のカセーロスの戦い(英語版)によりアルゼンチンでロサスの時代が終わって、1862年に自由主義者バルトロメ・ミトレ(英語版)主導で全アルゼンチンが統一され、アルゼンチン共和国が成立すると、それまでのカウディージョ政治への反動と、西欧への盲目的な信奉により1868年にアルゼンチン大統領に就任したドミンゴ・ファウスティーノ・サルミエント(英語版)に代表される自由主義知識人はガウチョを「根性曲がりの二本足の動物」と呼び、スペイン的な遅れたもの、野蛮なものの見本のように扱い毛嫌いした。1878年から開始されたフリオ・アルヘンティーノ・ロカ(英語版)の砂漠の開拓作戦(英語版)に代表される、パンパ南部、パタゴニアでの主にマプーチェ族をはじめとする一連の狩猟インディオとの戦いでは、ガウチョは先住民の駆逐・殺戮のために徴兵され、ニコラス・アベジャネーダ(英語版)大統領に代表されるアルゼンチンの自由主義者は共に近代化の障壁とみなしたガウチョとインディオを同士討ちさせた。その後のヨーロッパ移民のアルゼンチンへの大規模な入植による牧畜業の発展、所有地の確定と有刺鉄線の導入などにより、パンパが細分され、自由に行き来出来なくなる空間になるとほぼ消滅した。
ガウチョ文学[編集]
1819年に連邦同盟のホセ・アルティーガス(英語版)と共に戦った軍人だった現ウルグアイ出身のバルトロメ・イダルゴ(スペイン語版)が、アルティーガスらの独立運動の失敗が、新しい国家を国民の求めるものにできなかったブエノスアイレスの寡頭支配層の考え方にあると考え、ガウチョをそれまで見られていたような浮浪者ではなく古いヨーロッパに抵抗して新しいアイデンティティを求める、新しい国家の精神を反映する存在として描く、斬新なガウチョ文学(英語版)を開始した。
サルミエントに代表される自由主義知識人はガウチョをスペイン的な遅れたもの、野蛮なものの見本のように扱い毛嫌いしたが、大衆の心性に訴えたガウチョ文学はその後アルゼンチンの作家ホセ・エルナンデスの叙事詩『マルティン・フィエロ(英語版) 』(1872) などによって完成され、その独特な文化や精神性を歌い、アルゼンチンの国民文学となった。
20世紀に入ると、東欧系のユダヤ移民がアルゼンチンに同化する様子を描いた『ユダヤ人のガウチョ』などの作品も生まれた。この作品は発表された当時は前向きに受け止められたが、20世紀後半に映画化されるとなった時にアルゼンチン人の反ユダヤ主義の猛攻撃を受けることになった。ユダヤ人がアルゼンチンの誇るガウチョであってはならないというのがその理由だった。
現在[編集]
19世紀後半以降、職業、社会階層としてのガウチョは消滅したが、それでも現在のアルゼンチン人、ウルグアイ人とブラジル南部のリオグランデ・ド・スル州の住民が誇りをこめてガウチョ(ポルトガル語ではガウーショ)を自称する。アルゼンチンで「とてもガウチョだ」と言えば、寛大で、他人のために自己犠牲を惜しまない人のことになるし、「ガウチョらしく振舞う」といえば自己を犠牲にしても他人のために尽くす人という意味になり、「ガウチョの言葉」といえば、それは「武士の一言」を意味する。旅行者や在住者がしばしば口にする、アルゼンチンとウルグアイにおける強烈な個人主義はガウチョから来ているとも言われる。タンゴの楽曲に「ガウチョの嘆き」があり、強い嫉妬をいだくガウチョが登場する歌詞がついてある。
非常によく間違われているが、職業としての牧人はペオン(アルゼンチン)やヴァケイロ(ブラジル)とよばれる。
関連項目[編集]
ウアッソ
リャネーロ
カウボーイ
グアラニー族
ガウチョの嘆き
パジャドール
パニオロ
草原の追跡(Way of a Gaucho) エスグリマ・クリオーラ

2014年04月15日
カシャッサ
カシャッサ
移動: 案内、
カシャッサ酒
カシャッサ(ポルトガル語:Cachaça、カシャーサとも)は、サトウキビを原料として作られる、ブラジル原産の蒸留酒。またPinga(ピンガ)などとも呼ばれる。
現在、世界で第2番目に多く消費される蒸留酒。ブラジル全土で生産されているが、特にミナス・ジェライス州が多いとされる。なお、同じくサトウキビを原料とする西インド諸島原産のラム酒とは同類系統の蒸留酒であり、広義ではラム酒の仲間と解釈される(ただしブラジルではこれを敬遠し否定する。詳細は後述)。
目次
[非表示] 1 歴史
2 名称
3 分類 3.1 主な大衆的ブランド
4 製法と定義
5 ラム酒との違い
6 バチーダ
7 関連項目
歴史[編集]
1532年にポルトガル探検隊の隊長Martim Affonso de Souza(マルチン・アフォンゾ・デ・ソウザ)により大規模な入植地が形成された。この時にポルトガル領であった北大西洋のマデイラ諸島からサトウキビの苗がブラジルに持ち込まれ、サンパウロ州サントス港近辺のサンヴィセンチで最初のサトウキビ畑をプランテーション化して砂糖を精製するようになった。
1536年、ポルトガル移植者がブラジルに蒸留機を輸入し、プランテーション化していたサトウキビを原料に蒸留酒を造るようになった。
なお、これとは別に偶然による産物でカシャッサが生まれたとする説もある。砂糖はサトウキビの絞り汁を煮立たせて醗酵するが、当初、その際に上ってくる泡をすくい上げて捨てていた。しかし泡は一晩経つと翌日には液状化する。働かされていた黒人奴隷たちは、偶然それを飲んでみると気分が良くなった。つまり酔うようになった、というものである。
いずれの説にしても、黒人が飲むようになったことで、奴隷たちに与える食事が少なく済むようになったため、ポルトガル人たちも黒人奴隷が飲むことをある程度容認し、また自分達も飲むようになった。
1622年、ノルデスチ(ブラジル北東部)にオランダが入植を図ったが、この際にオランダ製の蒸留酒製造機が持ち込まれ、カシャッサの質・量が共に飛躍的に向上した。
1789年、歯科医のJoaquim José da Silva Xavier(ジョアキン・ジョゼ・ダ・シルヴァ・シャビエ、別名:Tiradentes - チラデンチス)という若い騎兵隊の将校をリーダーに、ポルトガルに対して独立運動が起こった。この時、彼らは「独立の乾杯はポルトガルワインでなく我々のカシャッサだ」というスローガンを打ち出した。独立運動は失敗に終わりチラデンチスは処刑されたものの、このスローガンが民衆の心を掴み、カシャッサは独立のシンボルとして、また一般大衆に浸透されて愛飲されるようになっていった。
近代になると、有名なメーカーによる大衆的なブランドが大量生産され販売されるようになった。しかし近年では、こうした量産品ではなく職人が造る芸術的な域にまで達したカシャッサが注目され好んで飲む人が増えている。きっかけはミナス州サリナスで故アニジオ・サンチアゴとその一家が製造した、Havana(ハヴァナ)というブランドである。ハヴァナとは彼らのファゼンダ(農場)の名前で、1943年に蒸留酒所を創業した。ブラジル政府は海外からの来賓にこのHavanaを起用したことで有名になった。
しかし、キューバ・ロンのハバナ・クラブがブラジルに入ってきた際に、登録商標問題が起こり、その結果Havanaを自身の名であるANÍSIO SANTIAGO -アニジオ・サンチアゴに変えざるを得なくなった。これにより市場からHavanaブランドが稀少化しプレミアムな価格がつくようになった。これによりHavanaの名称は一気に知られることになり、こうした職人の作る希少価値のあるカシャッサが注目されることになった。またこれにより、カシャッサの高級化が図られ、欧州などへの輸出も拡大されている。
名称[編集]
上記の通り、カシャッサにはいくつかの名称があるが、これは地域での呼称によるものである。カシャッサは主にリオを中心としたブラジル全土での共通語とされる。サンパウロではピンガ、そしてリオ・グランデ・ド・スルなどブラジル南部ではアグアルディエンテ・デ・カニャなどと呼ばれる。この他にもカニーニャ、シュガー・ケーン・ブランデーなどともいわれる。なおブラジルではカシャッサのブランド力を高めるために州の機関によって認められたものだけをカシャッサと呼んで、あえてピンガとは呼ばない地域もある。
Cachaça(カシャッサ)の語源は、Cachos - カッショス(複数の房)に、aca(大きい・成長した)という接尾語がついたものである。つまり本来は藤の花房やバナナ、ブドウの房のような状態のことである。ポルトガル国内でワインなどの醸造酒を製造する際、発酵工程で泡が出る。この泡は不純物が含まれており容器の底に、澱みや滓(おり・かす)が沈殿する。また当時のワイン製法は雑だったため、醜くて悪臭があり、醗酵過程で泡粒が生じる。この泡粒は原料のブドウと似ていた。ポルトガルはアペリード(ニックネーム、あだ名)がつけるのが通例で、これをブドウの花房になぞらえてカシャッサと名づけたといわれる。
これに対し、Pinga(ピンガ)は、本来は滴(しずく)や点滴のことであるが、大衆的なブランドで世界最多の生産量で知られるブランドの「51 - シンクエンタ・イ・ウン」を製造する会社名である。30年ほど前からこの51がブラジル全土で販売展開されるようになり、また日本をはじめ海外へ輸出されたことで、ピンガの名称も広く知られることになった。
またカシャッサには多くの別名がある。Água Branca(アグア・ブランカ、白い水)、Água Maluca(アグア・マルーカ、狂った水)、Brasileirinha(ブラジレイリーニャ、ブラジル娘)、Café Branco(カフェ・ブランコ、白いコーヒー)、Dona Branca(ドナ・ブランカ、白い女主人)、Veneno(ヴェネーノ、毒)など、100を越える俗名で呼ばれることもある。
分類[編集]
カシャーサには、有名メーカーが工場で量産する大衆的ブランドと、職人が手間ひまをかけて作るため量産できない地酒ならぬ地カシャーサの2つに大きく分けられる。
主な大衆的ブランド[編集]
イピオカ(Ypióca)
ヴェーリョ・バヘイロ(Velho Barreiro)
タトゥジーニョ(Tatuzinho)
51(シンクエンタ・イ・ウン、Cinquenta e um) - 現在、サントリーが輸入代理している。
上記の大衆的なブランドのいくつかは日本の大きなデパートや専門店、またブラジル食材店でも入手できる。これに対して職人が作る非量産のカシャッサは、ブラジルではCachaça Artesanal - カシャッサ・アルチサナゥといい、一般的なルートでの入手は容易ではない。
しかし日本においてもこれらのカシャッサを愛好する人々も存在し、これらの人々の間ではアーティザン・カシャーサなどと呼ばれる。なお、Artesanal - アルチサナゥ、Artesão - アーティザン(正確な発音はアルチザゥン)は、ともに“芸術的な職人”を意味する言葉であるが、一般的にブラジルでは、Cachaça Artesanal - カシャッサ・アルチサナゥというのが正式な呼称である。
製法と定義[編集]
サトウキビの搾り汁を加水せず直接発酵、蒸留を行って作り、48%のアルコール分になるまで発酵させ、その後アルコール分が39%辺りになるまで、芳香成分と香りを残しながら調整する。ブラジルが定めるカシャーサの定義は、ブラジルで産出されたサトウキビを原料とし、その絞り汁を醗酵させたアルコール度数が38~54度の蒸留酒とする。また製品1リットルに対し6グラムまで加糖したものも含める。ただし、カシャッサ・アルチサナゥの主産地であるミナス・ジェライス州の法律では、独自のカシャッサ・アルチサナゥ製造工程法が取り決められており、原料として砂糖や副原料などの添加物を一切使用してはならない、と厳格に定めている。
特に北ミナス地方では、土地や気候に加え、製造技術の3つの条件を満たす、最も品質に優れたカシャッサができるという。気候は特に重要とされる。サトウキビの生産サイクルにおいては雨が大事で、前半は多くの雨を必要とし、後半は雨が少ない方がいいとされる。またさらに収穫の1ヶ月ほど前には雨がまったく降らないことが望まれる。もしこの時期に大雨が降ると、糖度が低下し苦味ができるためである。
ラム酒との違い[編集]
冒頭文の説明の通り、カシャッサとラム酒は共にサトウキビを原料とする蒸留酒である。
ブラジルでラムの名が知られるようになったのは1660年代半ば頃で、これに対しカシャッサの名が定着したのは1750年代半ばといわれる。ブラジルでラム酒の名が定着しなかったのは一説に西インド諸島を領土化したスペインとの交易対立であるともいわれる。
したがって、ブラジルでは「カシャッサはラム酒ではない」と明確に区別している。
ラム酒との違いを具体的に挙げると、
1.ブラジルと西インド諸島の気候や気温などにより、本来持っている酵素や細菌が異なる。
2.異なった文化圏(ポルトガル語対スペイン語という言葉や生活習慣など)での製造の手順や手法が異なる。
3.ブラジル以外で製造されるスピリッツの多くは、200リットルのアメリカやヨーロッパの広葉樹(オーク)の樽に長く置かれるが、ブラジル原産のカシャッサは、それらよりも大きい1万リットル程度の樽を使う。また樽はアマゾンの森林樹や大西洋沿岸の森林樹を使う。
これらの違いにより、ブラジル原産のカシャッサは、ラム酒とは異なる、独特な味わいと香りのあるスピリッツとなっている。
バチーダ[編集]
バチーダとは、ブラジルでいうカシャーサをベースで作るカクテルのこと。果物を使うことが多い。
カイピリーニャ - ライムを乱切りにしてコップに加えて棒でつぶし、砂糖をやや多めに入れてクラッシュアイスで飲む。
バチーダ・ジ・ココ - ココナッツフレーバーとココナッツミルクを加えて作るカクテル。
バチーダ・ジ・ラランジャ - ラランジャ(オレンジ)で作るカクテル。
バチーダ・ジ・モランゴ - モランゴ(イチゴ)で作るカクテル。
バチーダ・ジ・アバカシ - アバカシ(パイナップル)で作るカクテル。
バチーダ・ジ・ウヴァ - ウヴァ(ブドウ)で作るカクテル。
バチーダ・ジ・マラクジャ - マラクジャ(パッション・フルーツ)で作るカクテル。
バチーダ・ジ・アメンドイン - アメンドイン(無塩のピーナッツクリーム)で作る。比較的、男性に好まれるカクテル。


移動: 案内、
カシャッサ酒
カシャッサ(ポルトガル語:Cachaça、カシャーサとも)は、サトウキビを原料として作られる、ブラジル原産の蒸留酒。またPinga(ピンガ)などとも呼ばれる。
現在、世界で第2番目に多く消費される蒸留酒。ブラジル全土で生産されているが、特にミナス・ジェライス州が多いとされる。なお、同じくサトウキビを原料とする西インド諸島原産のラム酒とは同類系統の蒸留酒であり、広義ではラム酒の仲間と解釈される(ただしブラジルではこれを敬遠し否定する。詳細は後述)。
目次
[非表示] 1 歴史
2 名称
3 分類 3.1 主な大衆的ブランド
4 製法と定義
5 ラム酒との違い
6 バチーダ
7 関連項目
歴史[編集]
1532年にポルトガル探検隊の隊長Martim Affonso de Souza(マルチン・アフォンゾ・デ・ソウザ)により大規模な入植地が形成された。この時にポルトガル領であった北大西洋のマデイラ諸島からサトウキビの苗がブラジルに持ち込まれ、サンパウロ州サントス港近辺のサンヴィセンチで最初のサトウキビ畑をプランテーション化して砂糖を精製するようになった。
1536年、ポルトガル移植者がブラジルに蒸留機を輸入し、プランテーション化していたサトウキビを原料に蒸留酒を造るようになった。
なお、これとは別に偶然による産物でカシャッサが生まれたとする説もある。砂糖はサトウキビの絞り汁を煮立たせて醗酵するが、当初、その際に上ってくる泡をすくい上げて捨てていた。しかし泡は一晩経つと翌日には液状化する。働かされていた黒人奴隷たちは、偶然それを飲んでみると気分が良くなった。つまり酔うようになった、というものである。
いずれの説にしても、黒人が飲むようになったことで、奴隷たちに与える食事が少なく済むようになったため、ポルトガル人たちも黒人奴隷が飲むことをある程度容認し、また自分達も飲むようになった。
1622年、ノルデスチ(ブラジル北東部)にオランダが入植を図ったが、この際にオランダ製の蒸留酒製造機が持ち込まれ、カシャッサの質・量が共に飛躍的に向上した。
1789年、歯科医のJoaquim José da Silva Xavier(ジョアキン・ジョゼ・ダ・シルヴァ・シャビエ、別名:Tiradentes - チラデンチス)という若い騎兵隊の将校をリーダーに、ポルトガルに対して独立運動が起こった。この時、彼らは「独立の乾杯はポルトガルワインでなく我々のカシャッサだ」というスローガンを打ち出した。独立運動は失敗に終わりチラデンチスは処刑されたものの、このスローガンが民衆の心を掴み、カシャッサは独立のシンボルとして、また一般大衆に浸透されて愛飲されるようになっていった。
近代になると、有名なメーカーによる大衆的なブランドが大量生産され販売されるようになった。しかし近年では、こうした量産品ではなく職人が造る芸術的な域にまで達したカシャッサが注目され好んで飲む人が増えている。きっかけはミナス州サリナスで故アニジオ・サンチアゴとその一家が製造した、Havana(ハヴァナ)というブランドである。ハヴァナとは彼らのファゼンダ(農場)の名前で、1943年に蒸留酒所を創業した。ブラジル政府は海外からの来賓にこのHavanaを起用したことで有名になった。
しかし、キューバ・ロンのハバナ・クラブがブラジルに入ってきた際に、登録商標問題が起こり、その結果Havanaを自身の名であるANÍSIO SANTIAGO -アニジオ・サンチアゴに変えざるを得なくなった。これにより市場からHavanaブランドが稀少化しプレミアムな価格がつくようになった。これによりHavanaの名称は一気に知られることになり、こうした職人の作る希少価値のあるカシャッサが注目されることになった。またこれにより、カシャッサの高級化が図られ、欧州などへの輸出も拡大されている。
名称[編集]
上記の通り、カシャッサにはいくつかの名称があるが、これは地域での呼称によるものである。カシャッサは主にリオを中心としたブラジル全土での共通語とされる。サンパウロではピンガ、そしてリオ・グランデ・ド・スルなどブラジル南部ではアグアルディエンテ・デ・カニャなどと呼ばれる。この他にもカニーニャ、シュガー・ケーン・ブランデーなどともいわれる。なおブラジルではカシャッサのブランド力を高めるために州の機関によって認められたものだけをカシャッサと呼んで、あえてピンガとは呼ばない地域もある。
Cachaça(カシャッサ)の語源は、Cachos - カッショス(複数の房)に、aca(大きい・成長した)という接尾語がついたものである。つまり本来は藤の花房やバナナ、ブドウの房のような状態のことである。ポルトガル国内でワインなどの醸造酒を製造する際、発酵工程で泡が出る。この泡は不純物が含まれており容器の底に、澱みや滓(おり・かす)が沈殿する。また当時のワイン製法は雑だったため、醜くて悪臭があり、醗酵過程で泡粒が生じる。この泡粒は原料のブドウと似ていた。ポルトガルはアペリード(ニックネーム、あだ名)がつけるのが通例で、これをブドウの花房になぞらえてカシャッサと名づけたといわれる。
これに対し、Pinga(ピンガ)は、本来は滴(しずく)や点滴のことであるが、大衆的なブランドで世界最多の生産量で知られるブランドの「51 - シンクエンタ・イ・ウン」を製造する会社名である。30年ほど前からこの51がブラジル全土で販売展開されるようになり、また日本をはじめ海外へ輸出されたことで、ピンガの名称も広く知られることになった。
またカシャッサには多くの別名がある。Água Branca(アグア・ブランカ、白い水)、Água Maluca(アグア・マルーカ、狂った水)、Brasileirinha(ブラジレイリーニャ、ブラジル娘)、Café Branco(カフェ・ブランコ、白いコーヒー)、Dona Branca(ドナ・ブランカ、白い女主人)、Veneno(ヴェネーノ、毒)など、100を越える俗名で呼ばれることもある。
分類[編集]
カシャーサには、有名メーカーが工場で量産する大衆的ブランドと、職人が手間ひまをかけて作るため量産できない地酒ならぬ地カシャーサの2つに大きく分けられる。
主な大衆的ブランド[編集]
イピオカ(Ypióca)
ヴェーリョ・バヘイロ(Velho Barreiro)
タトゥジーニョ(Tatuzinho)
51(シンクエンタ・イ・ウン、Cinquenta e um) - 現在、サントリーが輸入代理している。
上記の大衆的なブランドのいくつかは日本の大きなデパートや専門店、またブラジル食材店でも入手できる。これに対して職人が作る非量産のカシャッサは、ブラジルではCachaça Artesanal - カシャッサ・アルチサナゥといい、一般的なルートでの入手は容易ではない。
しかし日本においてもこれらのカシャッサを愛好する人々も存在し、これらの人々の間ではアーティザン・カシャーサなどと呼ばれる。なお、Artesanal - アルチサナゥ、Artesão - アーティザン(正確な発音はアルチザゥン)は、ともに“芸術的な職人”を意味する言葉であるが、一般的にブラジルでは、Cachaça Artesanal - カシャッサ・アルチサナゥというのが正式な呼称である。
製法と定義[編集]
サトウキビの搾り汁を加水せず直接発酵、蒸留を行って作り、48%のアルコール分になるまで発酵させ、その後アルコール分が39%辺りになるまで、芳香成分と香りを残しながら調整する。ブラジルが定めるカシャーサの定義は、ブラジルで産出されたサトウキビを原料とし、その絞り汁を醗酵させたアルコール度数が38~54度の蒸留酒とする。また製品1リットルに対し6グラムまで加糖したものも含める。ただし、カシャッサ・アルチサナゥの主産地であるミナス・ジェライス州の法律では、独自のカシャッサ・アルチサナゥ製造工程法が取り決められており、原料として砂糖や副原料などの添加物を一切使用してはならない、と厳格に定めている。
特に北ミナス地方では、土地や気候に加え、製造技術の3つの条件を満たす、最も品質に優れたカシャッサができるという。気候は特に重要とされる。サトウキビの生産サイクルにおいては雨が大事で、前半は多くの雨を必要とし、後半は雨が少ない方がいいとされる。またさらに収穫の1ヶ月ほど前には雨がまったく降らないことが望まれる。もしこの時期に大雨が降ると、糖度が低下し苦味ができるためである。
ラム酒との違い[編集]
冒頭文の説明の通り、カシャッサとラム酒は共にサトウキビを原料とする蒸留酒である。
ブラジルでラムの名が知られるようになったのは1660年代半ば頃で、これに対しカシャッサの名が定着したのは1750年代半ばといわれる。ブラジルでラム酒の名が定着しなかったのは一説に西インド諸島を領土化したスペインとの交易対立であるともいわれる。
したがって、ブラジルでは「カシャッサはラム酒ではない」と明確に区別している。
ラム酒との違いを具体的に挙げると、
1.ブラジルと西インド諸島の気候や気温などにより、本来持っている酵素や細菌が異なる。
2.異なった文化圏(ポルトガル語対スペイン語という言葉や生活習慣など)での製造の手順や手法が異なる。
3.ブラジル以外で製造されるスピリッツの多くは、200リットルのアメリカやヨーロッパの広葉樹(オーク)の樽に長く置かれるが、ブラジル原産のカシャッサは、それらよりも大きい1万リットル程度の樽を使う。また樽はアマゾンの森林樹や大西洋沿岸の森林樹を使う。
これらの違いにより、ブラジル原産のカシャッサは、ラム酒とは異なる、独特な味わいと香りのあるスピリッツとなっている。
バチーダ[編集]
バチーダとは、ブラジルでいうカシャーサをベースで作るカクテルのこと。果物を使うことが多い。
カイピリーニャ - ライムを乱切りにしてコップに加えて棒でつぶし、砂糖をやや多めに入れてクラッシュアイスで飲む。
バチーダ・ジ・ココ - ココナッツフレーバーとココナッツミルクを加えて作るカクテル。
バチーダ・ジ・ラランジャ - ラランジャ(オレンジ)で作るカクテル。
バチーダ・ジ・モランゴ - モランゴ(イチゴ)で作るカクテル。
バチーダ・ジ・アバカシ - アバカシ(パイナップル)で作るカクテル。
バチーダ・ジ・ウヴァ - ウヴァ(ブドウ)で作るカクテル。
バチーダ・ジ・マラクジャ - マラクジャ(パッション・フルーツ)で作るカクテル。
バチーダ・ジ・アメンドイン - アメンドイン(無塩のピーナッツクリーム)で作る。比較的、男性に好まれるカクテル。


2014年04月14日
テンガロンハット
テンガロンハット
移動: 案内、 検索
本来のテンガロンハット
テンガロンハット(ten-gallon hat)は、カウボーイなどがかぶる帽子、カウボーイハットの一種。 高いクラウン(crown、山部)、幅広いブリム(brim、つば)、飾りひもを持つ。
目次
[非表示] 1 由来
2 特徴
3 一覧
由来[編集]
10ガロン (ten gallon) の水が入ると言われ、西部劇ではテンガロンハットで水を汲むシーンも登場しているが、帽子の中に10ガロン(=38リットル)の水が収まる容積はない。
実際にはメキシコからのスペイン語が変化したものとされるのが一般的だが、名前の由来には諸説がある。
飾りひもが付いてブレーディングしていることから、「ひもを編む(ブレード、braid)」という意味で、メキシコ人カウボーイ(vaqueros)が使うスペイン語の「ガロン(galón)」を、「テキサス州の物は何でも大きい」というテキサス人の見栄と絡めて、わざと誤訳的に命名されたと考えられる[要出典]。
西部劇の衣装として作られたとも言われる。
特徴[編集]
素材は冬はウールや夏は麦わらが使用されている。色は白や灰色、茶色、黒が多いが赤や青も存在する。カウボーイハットの中では珍しい種類であり、実際のカウボーイがこのスタイルの帽子をかぶることはほとんどない。現在の一般的なカウボーイや、カントリー・ミュージック歌手が被るハットのスタイルは、カトルマン(Cattleman)と呼ばれる種類である。

移動: 案内、 検索
本来のテンガロンハット
テンガロンハット(ten-gallon hat)は、カウボーイなどがかぶる帽子、カウボーイハットの一種。 高いクラウン(crown、山部)、幅広いブリム(brim、つば)、飾りひもを持つ。
目次
[非表示] 1 由来
2 特徴
3 一覧
由来[編集]
10ガロン (ten gallon) の水が入ると言われ、西部劇ではテンガロンハットで水を汲むシーンも登場しているが、帽子の中に10ガロン(=38リットル)の水が収まる容積はない。
実際にはメキシコからのスペイン語が変化したものとされるのが一般的だが、名前の由来には諸説がある。
飾りひもが付いてブレーディングしていることから、「ひもを編む(ブレード、braid)」という意味で、メキシコ人カウボーイ(vaqueros)が使うスペイン語の「ガロン(galón)」を、「テキサス州の物は何でも大きい」というテキサス人の見栄と絡めて、わざと誤訳的に命名されたと考えられる[要出典]。
西部劇の衣装として作られたとも言われる。
特徴[編集]
素材は冬はウールや夏は麦わらが使用されている。色は白や灰色、茶色、黒が多いが赤や青も存在する。カウボーイハットの中では珍しい種類であり、実際のカウボーイがこのスタイルの帽子をかぶることはほとんどない。現在の一般的なカウボーイや、カントリー・ミュージック歌手が被るハットのスタイルは、カトルマン(Cattleman)と呼ばれる種類である。

2014年04月10日
ペミカン
ペミカン
移動: 案内、 検索
アウトドア・ショーであるカルガリー・スタンピード(英語版)で作られているペミカン
ペミカン(英語:pemmican)は、カナダ及びアメリカに先住するインディアンたちの伝統的な保存食。 携帯保存食の一種である。
目次
[非表示] 1 概要
2 犬用のペミカン
3 その他のペミカン
4 脚注
5 関連項目
概要[編集]
ペミカンは、加熱溶解した動物性脂肪に、粉砕した干し肉とドライフルーツなどを混ぜ、密封して固めることで保存性を高めた食品である。毛皮交易の際に携帯保存食として広く利用され、後にロバート・スコットやロアール・アムンセンのような極地探検家の間で高カロリー食品として利用された。適切に包装されたペミカンは、長期間保存することができた。日本においても、大学山岳部などによる長期に及ぶ冬季登山などにおいてよく利用されている。
ペミカンの材料は、使用可能なものなら何でも用いられた。例えば、ペミカン用の肉としてしばしばアメリカバイソン、ヘラジカ、シカ(アメリカアカシカやオジロジカなど)の肉が使われた。果物はクランベリー、サスカトゥーンベリー(saskatoon berry、ザイフリボク属)がよく使われた。チェリー、スグリ 、セイヨウカマツカの実、ブルーベリーが使われたペミカンは、インディアンたちの間でもっぱら冠婚葬祭などの特別な場合に、現在でも食べられている。パウワウにも供されることが多い。
脂肪分の少ない肉と骨髄の脂肪で作られたペミカンが最上級とされるなど、毛皮交易時代のペミカン購入者の間では厳格な仕様が存在していた。
語源はクリー語の「ピミーカーン」(pimîhkân)で、「pimî」は「脂肪」を意味する。
犬用のペミカン[編集]
イギリスの北極探検隊は、犬ぞりを引く犬に牛肉で作られたペミカンを与えた。このペミカンは「ボブリル・ペミカン (Bovril pemmican)」、または単純に「犬用のペミカン」と呼ばれた。成分は2/3が蛋白質、1/3が脂肪であり、炭水化物は含まなかった。このペミカンは蛋白質の割合が高すぎて犬の健康に良くないことが後に確かめられた。[1]
アーネスト・シャクルトンの帝国南極横断探検隊(1914年-1916年)の隊員たちは、船が氷塊に阻まれ身動きが取れなくなった時に犬用のペミカンを食べて生き延びた。[2]
その他のペミカン[編集]
コンアグラ・フーズがネブラスカ州オマハで製造販売しているビーフジャーキーと、カリフォルニア州オールバニのインターマウンテン・トレーディング社(Intermountain Trading Co. Ltd.)が製造販売しているスナックバー型の携帯食に「ペミカン」というブランド名が使用されているが、どちらも上記の伝統的なペミカンとは異なる食品である。
カカオ豆の脂肪分であるカカオバターから作られたホワイトチョコレートを溶かし、ナッツ類とドライフルーツを混ぜ、冷やし固めた物を、ペミカンの代用品とすることができる。家庭で手軽に作ることができ、純植物性なのでベジタリアンにも適している

移動: 案内、 検索
アウトドア・ショーであるカルガリー・スタンピード(英語版)で作られているペミカン
ペミカン(英語:pemmican)は、カナダ及びアメリカに先住するインディアンたちの伝統的な保存食。 携帯保存食の一種である。
目次
[非表示] 1 概要
2 犬用のペミカン
3 その他のペミカン
4 脚注
5 関連項目
概要[編集]
ペミカンは、加熱溶解した動物性脂肪に、粉砕した干し肉とドライフルーツなどを混ぜ、密封して固めることで保存性を高めた食品である。毛皮交易の際に携帯保存食として広く利用され、後にロバート・スコットやロアール・アムンセンのような極地探検家の間で高カロリー食品として利用された。適切に包装されたペミカンは、長期間保存することができた。日本においても、大学山岳部などによる長期に及ぶ冬季登山などにおいてよく利用されている。
ペミカンの材料は、使用可能なものなら何でも用いられた。例えば、ペミカン用の肉としてしばしばアメリカバイソン、ヘラジカ、シカ(アメリカアカシカやオジロジカなど)の肉が使われた。果物はクランベリー、サスカトゥーンベリー(saskatoon berry、ザイフリボク属)がよく使われた。チェリー、スグリ 、セイヨウカマツカの実、ブルーベリーが使われたペミカンは、インディアンたちの間でもっぱら冠婚葬祭などの特別な場合に、現在でも食べられている。パウワウにも供されることが多い。
脂肪分の少ない肉と骨髄の脂肪で作られたペミカンが最上級とされるなど、毛皮交易時代のペミカン購入者の間では厳格な仕様が存在していた。
語源はクリー語の「ピミーカーン」(pimîhkân)で、「pimî」は「脂肪」を意味する。
犬用のペミカン[編集]
イギリスの北極探検隊は、犬ぞりを引く犬に牛肉で作られたペミカンを与えた。このペミカンは「ボブリル・ペミカン (Bovril pemmican)」、または単純に「犬用のペミカン」と呼ばれた。成分は2/3が蛋白質、1/3が脂肪であり、炭水化物は含まなかった。このペミカンは蛋白質の割合が高すぎて犬の健康に良くないことが後に確かめられた。[1]
アーネスト・シャクルトンの帝国南極横断探検隊(1914年-1916年)の隊員たちは、船が氷塊に阻まれ身動きが取れなくなった時に犬用のペミカンを食べて生き延びた。[2]
その他のペミカン[編集]
コンアグラ・フーズがネブラスカ州オマハで製造販売しているビーフジャーキーと、カリフォルニア州オールバニのインターマウンテン・トレーディング社(Intermountain Trading Co. Ltd.)が製造販売しているスナックバー型の携帯食に「ペミカン」というブランド名が使用されているが、どちらも上記の伝統的なペミカンとは異なる食品である。
カカオ豆の脂肪分であるカカオバターから作られたホワイトチョコレートを溶かし、ナッツ類とドライフルーツを混ぜ、冷やし固めた物を、ペミカンの代用品とすることができる。家庭で手軽に作ることができ、純植物性なのでベジタリアンにも適している

2014年04月10日
4月10日の記事
HWS / ハートフォード
SAA.45 ファストドロウカスタム
・バレル、シリンダーがシルバーでフレームがブラックというコンビネーションは日本ではあまり馴染みないと思います。が、本場米国のファストドロウ カスタムガンでは非常にポピュラーです。
本場米国でスタンダードなファストドロウカスタムをリサーチしモデルアップ。
仕様】バレル、シリンダー、ハンマーはニッケルシルバー。ワイドトリガー装備。ダミーエジェクターロッド標準装備(標準マガジンも付属)。エジェクターチューブ先端と、ハンマートップはラウンド加工。ファストドロウ対応ホップレスインナーバレル。生ガス放出軽減アイテムビルトイン。木製グリップ、ロングベースピン(チャージアダプター収納可能)装備
今度はこの銃をサポート用として、ビズリーとペアを組ませてツインシュートをしてみたいと思う、右にビズリー、左にSAA.45 ファストドロウカスタムもありかと思う。右利きの私には、左の使方が難かもしれないが。
SAA.45 ファストドロウカスタム
・バレル、シリンダーがシルバーでフレームがブラックというコンビネーションは日本ではあまり馴染みないと思います。が、本場米国のファストドロウ カスタムガンでは非常にポピュラーです。
本場米国でスタンダードなファストドロウカスタムをリサーチしモデルアップ。
仕様】バレル、シリンダー、ハンマーはニッケルシルバー。ワイドトリガー装備。ダミーエジェクターロッド標準装備(標準マガジンも付属)。エジェクターチューブ先端と、ハンマートップはラウンド加工。ファストドロウ対応ホップレスインナーバレル。生ガス放出軽減アイテムビルトイン。木製グリップ、ロングベースピン(チャージアダプター収納可能)装備
今度はこの銃をサポート用として、ビズリーとペアを組ませてツインシュートをしてみたいと思う、右にビズリー、左にSAA.45 ファストドロウカスタムもありかと思う。右利きの私には、左の使方が難かもしれないが。

2014年04月09日
ラスト・シューティスト
ラスト・シューティスト
移動: 案内、 検索
ラスト・シューティスト
The Shootist
監督
ドン・シーゲル
脚本
マイルズ・フッド・スワザウト
スコット・D・ヘイル
原作
グレンドン・スワザウト
製作
M・J・フランコヴィッチ
ウィリアム・セルフ
音楽
エルマー・バーンスタイン
撮影
ブルース・サーティース
編集
ダグラス・スチュワート
配給
パラマウント映画
東宝東和
公開
1976年8月11日
1979年7月7日
上映時間
99分
製作国
アメリカ合衆国
言語
英語
テンプレートを表示
『ラスト・シューティスト』(原題: The Shootist)は、1976年製作の、ジョン・ウェイン主演の西部劇映画である。1975年に発表された同名の小説の映画化で、ローレン・バコール、ロン・ハワードそしてジェームズ・ステュアートが共演している。師であるジョン・フォード亡き後も、一人で奮闘したジョン・ウェインの遺作となった作品である。
目次
[非表示] 1 あらすじ
2 キャスト
3 スタッフ
4 エピソード
5 脚注
6 外部リンク
あらすじ[編集]
1901年1月22日、かつての射撃の名手、ブックスがネバダ州のカーソンシティに戻ってきた。信頼のおける医者のホステトラーから、自分の病気について聞いたところ、ガンで病状が悪化していることを知らされる。未亡人のロジャース夫人が経営する、下宿屋の部屋を借りたブックスを、保安官のティビドーが訪れ、町を立ち退くよう命じるが、ブックスが余命いくばくもないことを知る。
ブックスがカーソンシティに滞在していることが知れ渡り、かつての仇敵たち、あるいは、これでひと儲けを目論む者たちが集まって来る。新聞記者がやって来て、彼のガンマン人生を美化した記事を書こうとしたり、この大物を倒して名を挙げようとする者もおり、2人の男が寝込みを襲おうとしたため、ブックスはやむを得ず2人を撃つ。ロジャース夫人の息子、ギロムはブックスに感銘をうけるものの、この件で、泊まり客に出て行かれた夫人は激しく怒る。ブックスの昔の女、セレプタも部屋を訪れて、結婚を申し込むが、結局は知名度利用であることに気づく。
ブックスは、葬儀屋のベッカムらと話をつけたあと、ロジャース夫人に、自分に残された時間がわずかであることを告げ、ギロムに頼んで3人の男、自分を弟の敵と狙うスイーニー、賭博を生業とするプルフォード、そして町のならず者コッブに挑戦状を突きつけて、自分の58歳の誕生日の午前中に、メトロポールの酒場での果たし合いを告げる。朝早い時間、4人と、バーテンダーしかいない酒場で始まった撃ち合いがやんだ時、入ってきたギロムは、あちこちに傷を負いながらも、立っているのはブックス唯一人であるのを発見した。その時バーテンダーが、背後からブックスを撃った。ギロムはブックスの銃を取り、バーテンダーを殺した。そしてすぐ銃を放り投げた。ブックスの顔に満足げな表情が見て取れた。
キャスト[編集]
役名
俳優
日本語吹き替え
フジテレビ版
テレビ朝日版
J・B・ブックス
ジョン・ウェイン
小林昭二
納谷悟朗
ロジャース夫人
ローレン・バコール
馬渕晴子
小沢寿美恵
ギロム
ロン・ハワード
水島裕
村山明
ホステトラー医師
ジェームズ・ステュアート
浦野光
浦野光
スイーニー
リチャード・ブーン
郷里大輔
田中康郎
プルフォード
ヒュー・オブライエン
池田勝
小林清志
ティビドー保安官
ハリー・モーガン
永井一郎
大木民夫
ベッカム
ジョン・キャラダイン
北村弘一
村越伊知郎
セレプタ
シェリー・ノース
榊原良子
モーゼス
スキャットマン・クローザース
龍田直樹
藤本譲
コッブ
ビル・マッキーニー
玄田哲章
仲木隆司
新聞記者ドブキンス
リック・レンズ
千田光男
石丸博也
フジテレビ版 - 初放送1982年6月12日 『ゴールデン洋画劇場』
テレビ朝日版 - 初放送1987年6月14日 『日曜洋画劇場』
スタッフ[編集]
監督:ドン・シーゲル
製作:M・J・フランコヴィッチ、ウィリアム・セルフ
脚本:マイルズ・フッド・スワザウト、スコット・D・ヘイル
原作:グレンドン・スウォースアウト
撮影:ブルース・サーティース
美術:ロバート・F・ボイル
音楽:エルマー・バーンスタイン
衣装(デザイン):モス・メーブリー
字幕:清水俊二
[1]
エピソード[編集]
冒頭で、『赤い河』、『ホンドー』、『リオ・ブラボー』、『エル・ドラド』というウェイン主演の映画のシーンが挿入されている。
意外な話だが、この映画の製作時点では、ウェインのガンは完治していた。ガンが再発したのは、この映画が製作されて3年たった1979年の1月12日のことである。
ネバダ州のカーソンシティでロケが行われた時、ロジャース夫人の宿となった建物は、ネバダ州知事の邸宅から3件しか離れていなかった。
ロケ地がエルパソからカーソンシティに変更になった時、ウェインは愛馬ドラーをキャストに加えて、脚本を書き直させた。また、演技も手直しをさせた。ブックスが背後からプルフォードを撃ち、しかる後に、ギロムがブックスを撃つという設定であったのだが、ウェインは「自分の映画人生の中で、ひとを背後から撃ったことは一度もない。変えてほしい。」と言い、また、若いギロムに人殺しをさせるのは忍びないとして、最後にギロムが銃を捨てて、ガンマンの道を諦めるという設定にした。
ウェインは配役にも責任を持った。ローレン・バコール、ジェームズ・ステュアート、リチャード・ブーン、そしてジョン・キャラダインの出演は、彼の意向によるものである。特にバコールは、20年ほど前に夫であるハンフリー・ボガートを癌で亡くしている。
映画に登場するドラーは、1969年、2歳の時に『勇気ある追跡』に出演し、以来10年間、ウェインの愛馬だった。この栗毛のアメリカン・クォーターホース(短距離用の競走馬)には、自分以外の人間が乗ることを禁じていたが、ウェインの死後、『探偵ハート&ハート』の中で、ロバート・ワグナーが乗ったことがある[2]。

移動: 案内、 検索
ラスト・シューティスト
The Shootist
監督
ドン・シーゲル
脚本
マイルズ・フッド・スワザウト
スコット・D・ヘイル
原作
グレンドン・スワザウト
製作
M・J・フランコヴィッチ
ウィリアム・セルフ
音楽
エルマー・バーンスタイン
撮影
ブルース・サーティース
編集
ダグラス・スチュワート
配給
パラマウント映画
東宝東和
公開
1976年8月11日
1979年7月7日
上映時間
99分
製作国
アメリカ合衆国
言語
英語
テンプレートを表示
『ラスト・シューティスト』(原題: The Shootist)は、1976年製作の、ジョン・ウェイン主演の西部劇映画である。1975年に発表された同名の小説の映画化で、ローレン・バコール、ロン・ハワードそしてジェームズ・ステュアートが共演している。師であるジョン・フォード亡き後も、一人で奮闘したジョン・ウェインの遺作となった作品である。
目次
[非表示] 1 あらすじ
2 キャスト
3 スタッフ
4 エピソード
5 脚注
6 外部リンク
あらすじ[編集]
1901年1月22日、かつての射撃の名手、ブックスがネバダ州のカーソンシティに戻ってきた。信頼のおける医者のホステトラーから、自分の病気について聞いたところ、ガンで病状が悪化していることを知らされる。未亡人のロジャース夫人が経営する、下宿屋の部屋を借りたブックスを、保安官のティビドーが訪れ、町を立ち退くよう命じるが、ブックスが余命いくばくもないことを知る。
ブックスがカーソンシティに滞在していることが知れ渡り、かつての仇敵たち、あるいは、これでひと儲けを目論む者たちが集まって来る。新聞記者がやって来て、彼のガンマン人生を美化した記事を書こうとしたり、この大物を倒して名を挙げようとする者もおり、2人の男が寝込みを襲おうとしたため、ブックスはやむを得ず2人を撃つ。ロジャース夫人の息子、ギロムはブックスに感銘をうけるものの、この件で、泊まり客に出て行かれた夫人は激しく怒る。ブックスの昔の女、セレプタも部屋を訪れて、結婚を申し込むが、結局は知名度利用であることに気づく。
ブックスは、葬儀屋のベッカムらと話をつけたあと、ロジャース夫人に、自分に残された時間がわずかであることを告げ、ギロムに頼んで3人の男、自分を弟の敵と狙うスイーニー、賭博を生業とするプルフォード、そして町のならず者コッブに挑戦状を突きつけて、自分の58歳の誕生日の午前中に、メトロポールの酒場での果たし合いを告げる。朝早い時間、4人と、バーテンダーしかいない酒場で始まった撃ち合いがやんだ時、入ってきたギロムは、あちこちに傷を負いながらも、立っているのはブックス唯一人であるのを発見した。その時バーテンダーが、背後からブックスを撃った。ギロムはブックスの銃を取り、バーテンダーを殺した。そしてすぐ銃を放り投げた。ブックスの顔に満足げな表情が見て取れた。
キャスト[編集]
役名
俳優
日本語吹き替え
フジテレビ版
テレビ朝日版
J・B・ブックス
ジョン・ウェイン
小林昭二
納谷悟朗
ロジャース夫人
ローレン・バコール
馬渕晴子
小沢寿美恵
ギロム
ロン・ハワード
水島裕
村山明
ホステトラー医師
ジェームズ・ステュアート
浦野光
浦野光
スイーニー
リチャード・ブーン
郷里大輔
田中康郎
プルフォード
ヒュー・オブライエン
池田勝
小林清志
ティビドー保安官
ハリー・モーガン
永井一郎
大木民夫
ベッカム
ジョン・キャラダイン
北村弘一
村越伊知郎
セレプタ
シェリー・ノース
榊原良子
モーゼス
スキャットマン・クローザース
龍田直樹
藤本譲
コッブ
ビル・マッキーニー
玄田哲章
仲木隆司
新聞記者ドブキンス
リック・レンズ
千田光男
石丸博也
フジテレビ版 - 初放送1982年6月12日 『ゴールデン洋画劇場』
テレビ朝日版 - 初放送1987年6月14日 『日曜洋画劇場』
スタッフ[編集]
監督:ドン・シーゲル
製作:M・J・フランコヴィッチ、ウィリアム・セルフ
脚本:マイルズ・フッド・スワザウト、スコット・D・ヘイル
原作:グレンドン・スウォースアウト
撮影:ブルース・サーティース
美術:ロバート・F・ボイル
音楽:エルマー・バーンスタイン
衣装(デザイン):モス・メーブリー
字幕:清水俊二
[1]
エピソード[編集]
冒頭で、『赤い河』、『ホンドー』、『リオ・ブラボー』、『エル・ドラド』というウェイン主演の映画のシーンが挿入されている。
意外な話だが、この映画の製作時点では、ウェインのガンは完治していた。ガンが再発したのは、この映画が製作されて3年たった1979年の1月12日のことである。
ネバダ州のカーソンシティでロケが行われた時、ロジャース夫人の宿となった建物は、ネバダ州知事の邸宅から3件しか離れていなかった。
ロケ地がエルパソからカーソンシティに変更になった時、ウェインは愛馬ドラーをキャストに加えて、脚本を書き直させた。また、演技も手直しをさせた。ブックスが背後からプルフォードを撃ち、しかる後に、ギロムがブックスを撃つという設定であったのだが、ウェインは「自分の映画人生の中で、ひとを背後から撃ったことは一度もない。変えてほしい。」と言い、また、若いギロムに人殺しをさせるのは忍びないとして、最後にギロムが銃を捨てて、ガンマンの道を諦めるという設定にした。
ウェインは配役にも責任を持った。ローレン・バコール、ジェームズ・ステュアート、リチャード・ブーン、そしてジョン・キャラダインの出演は、彼の意向によるものである。特にバコールは、20年ほど前に夫であるハンフリー・ボガートを癌で亡くしている。
映画に登場するドラーは、1969年、2歳の時に『勇気ある追跡』に出演し、以来10年間、ウェインの愛馬だった。この栗毛のアメリカン・クォーターホース(短距離用の競走馬)には、自分以外の人間が乗ることを禁じていたが、ウェインの死後、『探偵ハート&ハート』の中で、ロバート・ワグナーが乗ったことがある[2]。

2014年04月09日
トゥームストーン
トゥームストーン
移動: 案内、 検索
この項目では、アメリカ合衆国の都市について記述しています。
全盛期のトゥームストーン。1881年
トゥームストーン(英: Tombstone)は、アメリカ合衆国アリゾナ州南東部に位置する都市。かつては銀の鉱山町として栄え、その人口はサンフランシスコをしのいだ。しかし銀鉱が掘り尽くされると町は急速に衰え、2006年の推計では人口1,569人にまで減少した。現在では町全体が国の史跡に指定され、西部開拓時代の辺境の町の町並みを残す「生きた博物館」として観光客を集めている。日本では、ツームストーンとも表記される。
目次
[非表示] 1 歴史 1.1 繁栄
1.2 凋落と観光化
2 地理
3 人口動勢
4 外部リンク
歴史[編集]
繁栄[編集]
エド・シーフェリン。1880年、トゥームストーンにて
1877年夏、エド・シーフェリンはアリゾナ準州南東部、サンペドロ川(San Pedro River)東岸の丘陵地帯を探索していた時、グース台地(Goose Flats)と呼ばれる高台に豊富な銀の鉱脈を見つけた。トゥームストーンという名はシーフェリンがこの地の銀鉱の採掘権を得たとき、この地の過酷な環境を揶揄してつけられたものであった。シーフェリンは石を集めていたとき、部下の兵士に、水のない丘陵地帯で、しかもアパッチ族による攻撃まで受けるこの地で見つける石は彼の墓石(トゥームストーン)になるであろうと言ったのである。
1879年にトゥームストーンは正式な町になった。この町は銀の鉱山町として急速に発展を遂げ、翌々年の1881年には人口1,000人に達し、市に昇格した。市に昇格すると、今度は1年経たないうちに人口5,000-15,000人にまで増え、新しく成立したコチセ郡(Cochise County)の郡庁所在地になった。市には冷蔵施設ができ、アイスクリーム店やアイススケートリンクまでもができた。水道施設が整えられ、電報や電話も開通した。コーンウォールやヨーロッパ出身の資産家・実業家たちはこの地に移民として流入してきた。中国系移民によってサービス業も発達した。
しかし、荒野の中に突如として形成されたトゥームストーンの町は良いことずくめではなかった。鉄道がなかったため、発展した町の中心部とは対照的に、周囲には荒涼とした、人気のない砂漠が広がっていた。そうした砂漠を活動範囲とするギャングもいて、治安はあまり良いとは言えなかった。ギャングたちはトゥームストーンにやってきては町を荒らし、北部の実業家や移民の鉱夫たちを殺したりもした。
凋落と観光化[編集]
旧コカイズ郡裁判所の処刑場の絞首台
繁栄は長くは続かなかった。もともと砂漠地帯で水が不足していた上、爆発的な人口増加によって突貫工事で建てられた木造の建物が多かったトゥームストーンは、1881年と1882年5月の2度にわたって大火に見まわれた。特に2度目の大火は、トゥームストーンの繁栄の歴史に終止符を打ったと言っても過言ではないものであった。1880年代中盤に入ると、銀鉱は掘り尽くされ、坑内は地下水であふれるようになった。
以後、トゥームストーンは凋落への道をたどり、ゴーストタウンと化した。1929年には南東約45kmに位置し、銅の露天掘りで人口が増えたビズビーに郡庁が移った。しかし、旧コカイズ郡裁判所と隣接する処刑場は博物館として残っている。
ブート・ヒル墓地(Boot Hill Graveyard)は、トゥームストーンが繁栄していた時期に暴力、または病気で亡くなった人たちが眠る墓地である。この墓地はトゥームストーンでリンチにあった、もしくは死刑を受けた者(人違いで死刑になった者もいるとの解説が墓地内にある)の行き先でもあり、死者が履いていたブーツが墓碑(簡素な木製のもの)に掛けられたことから、この名が付いた。現在、墓碑は木を模した金属製に置き換えられているが、当時の雰囲気を充分に味わうことができる。この歴史的な墓場の入り口には土産物屋があり、その店内から入場料を払い入ることになる。
1881年にトゥームストーンで起きた暴力事件の代表とも言えるOK牧場の決闘が起きた場所も史跡として残っている。同史跡は見学料を課しているが、市のメインストリートであるフレモント通り(州道80号線)からその大部分を見ることができる。
トゥームストーンはまた、世界最大のバラの茂みが植えられている地でもある。このバラの茂みはギネスブックにも登録されている。1885年に植えられたこのレディー・バンクシア種(Lady Banksia)のバラは、1年を通じて晴天に恵まれたこの地の気候の影響もあって成長状態が良く、宿屋の屋根上約743m²をカバーし、12本の幹を有している。[1]
現在のダウンタウン・トゥームストーン
こういった歴史的なものが数多く存在するトゥームストーンは、1961年に「1870年代から1880年代にかけての辺境の町の町並みが最もよく保存された例」として国の歴史地区に指定された。現在のトゥームストーンの主産業はこの歴史地区を生かした観光である。2005年7月に発表されたCNNの記事によると、トゥームストーンを訪れる観光客の数は年間450,000人に上る。現在の常住人口が約1,500人であるので、人口1人あたり300人の観光客が訪れている計算になる。しかし市内の酒場が24時間営業し、売春宿が立ち並んだ全盛期とは異なり、現在のトゥームストーンは落ち着いたコミュニティで、夜遅くまで開いている店はほとんどない。
しかし過度な観光化は、トゥームストーンの歴史的価値が危機にさらすことでもあった。2004年、アメリカ国立公園局(NPS)はトゥームストーンの歴史地区が「危機状態」にあると宣言し、地元コミュニティに対し、適切なスチュワードシップ制による保全を求めた。国立公園局が不適切と指摘した点には次のようなものがある。
新しく建てられた建物に対し「歴史的」な日付の記載がなされている。
新しく建てられた建物と歴史的建造物との区別が困難である。
歴史的建造物に対し、不適切な建材を用いている。
歴史的建造物を修復するのではなく、新たに建て替えている。
憶測による、十分な根拠のない建材で建て替えられ、建物の歴史的側面が失われている。
既存の歴史的建造物を大幅に増築したり、敷地内に新しい建物を建てたりしている。
歴史的な看板を囲む点滅灯の使用など、看板にイルミネーションを用いている。
トゥームストーンに存在しなかったはずの建築様式で建物が建てられている。
また、市内の道が舗装されたことも、歴史的な町並みの保存に反するものであるとされた。
これらの問題点の対策として、2006年1月現在、トゥームストーン修復委員会(Tombstone Restoration Committee)は市内の歴史的建造物の修復に尽力している。市内の通りに施された舗装は剥がされ、再び「歴史的」な埃道に戻った。
地理[編集]
トゥームストーンの位置
トゥームストーンは北緯31度42分57秒西経110度3分53秒(31.715940, -110.064827)に位置している。ツーソンの東南東約110km、フェニックスの南東約300kmに位置している。
アメリカ合衆国統計局によると、トゥームストーン市は総面積11.1km²(4.3mi²)である。市の全域が陸地であり、水域はない。
ダウンタウンは西北西-東南東方向に約2km、北北東-南南西方向に約800mの範囲内に収まっている。ダウンタウンの道路は整然と区画されている。アリゾナ州道80号線がダウンタウンを通っており、フレモント通り(Fremont Street)として市のメインストリートになっている。西部開拓時代の町並み保存の一環として、アレン通り(Allen Street)など一部のダウンタウンの通りは舗装が剥がされている。
トゥームストーンの気候は温暖な冬と暑い夏、そして1年を通じて乾燥した気候に特徴付けられる。夏の平均気温は摂氏27度ほどだが、日中は摂氏35度に達する。ただし湿度が低いため、夜になると摂氏20度程度まで下がって涼しくなり、日本のような熱帯夜にはならない。冬でも平均気温は摂氏10度程度、夜でも氷点下に下がることは滅多にない。降水量は1年を通じて月間0-25mmほどであるが、7月・8月は短い雨季で、月間75mm程度の降水がある。年間降水量は200-250mm程度である。ケッペンの気候区分では砂漠気候(BW)に属する。
人口動勢[編集]
以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。
基礎データ 人口: 1,504人
世帯数: 694世帯
家族数: 419家族
人口密度: 135.0人/km²(349.8人/mi²)
住居数: 839軒
住居密度: 75.3軒/km²(195.1軒/mi²)
人種別人口構成 白人: 87.37 %
黒人: 0.60 %
インディアン: 1.00 %
アジア人: 0.33 %
その他の人種: 8.18 %
混血: 2.53 %
ヒスパニック・ラテン系: 24.14 %
年齢別人口構成 18歳未満: 19.3 %
18-24歳: 4.9 %
25-44歳: 19.9 %
45-64歳: 32.5 %
65歳以上: 23.3 %
年齢の中央値: 49歳
性比(女性100人あたり男性の人口) 総人口: 94.3
18歳以上: 91.0
世帯と家族(対世帯数) 18歳未満の子供がいる: 20.2 %
結婚・同居している夫婦: 47.6 %
未婚・離婚・死別女性が世帯主: 7.9 %
非家族世帯: 39.5 %
単身世帯: 32.9 %
65歳以上の老人1人暮らし: 15.3 %
平均構成人数 世帯: 2.17人
家族: 2.73人
収入と家計 収入の中央値 世帯: 26,571米ドル
家族: 33,750米ドル
性別 男性: 26,923米ドル
女性: 18,846米ドル
人口1人あたり収入: 15,447米ドル
貧困線以下 対人口: 17.4 %
対家族数: 13.0 %
18歳未満: 22.6 %
65歳以上: 13.1 %

移動: 案内、 検索
この項目では、アメリカ合衆国の都市について記述しています。
全盛期のトゥームストーン。1881年
トゥームストーン(英: Tombstone)は、アメリカ合衆国アリゾナ州南東部に位置する都市。かつては銀の鉱山町として栄え、その人口はサンフランシスコをしのいだ。しかし銀鉱が掘り尽くされると町は急速に衰え、2006年の推計では人口1,569人にまで減少した。現在では町全体が国の史跡に指定され、西部開拓時代の辺境の町の町並みを残す「生きた博物館」として観光客を集めている。日本では、ツームストーンとも表記される。
目次
[非表示] 1 歴史 1.1 繁栄
1.2 凋落と観光化
2 地理
3 人口動勢
4 外部リンク
歴史[編集]
繁栄[編集]
エド・シーフェリン。1880年、トゥームストーンにて
1877年夏、エド・シーフェリンはアリゾナ準州南東部、サンペドロ川(San Pedro River)東岸の丘陵地帯を探索していた時、グース台地(Goose Flats)と呼ばれる高台に豊富な銀の鉱脈を見つけた。トゥームストーンという名はシーフェリンがこの地の銀鉱の採掘権を得たとき、この地の過酷な環境を揶揄してつけられたものであった。シーフェリンは石を集めていたとき、部下の兵士に、水のない丘陵地帯で、しかもアパッチ族による攻撃まで受けるこの地で見つける石は彼の墓石(トゥームストーン)になるであろうと言ったのである。
1879年にトゥームストーンは正式な町になった。この町は銀の鉱山町として急速に発展を遂げ、翌々年の1881年には人口1,000人に達し、市に昇格した。市に昇格すると、今度は1年経たないうちに人口5,000-15,000人にまで増え、新しく成立したコチセ郡(Cochise County)の郡庁所在地になった。市には冷蔵施設ができ、アイスクリーム店やアイススケートリンクまでもができた。水道施設が整えられ、電報や電話も開通した。コーンウォールやヨーロッパ出身の資産家・実業家たちはこの地に移民として流入してきた。中国系移民によってサービス業も発達した。
しかし、荒野の中に突如として形成されたトゥームストーンの町は良いことずくめではなかった。鉄道がなかったため、発展した町の中心部とは対照的に、周囲には荒涼とした、人気のない砂漠が広がっていた。そうした砂漠を活動範囲とするギャングもいて、治安はあまり良いとは言えなかった。ギャングたちはトゥームストーンにやってきては町を荒らし、北部の実業家や移民の鉱夫たちを殺したりもした。
凋落と観光化[編集]
旧コカイズ郡裁判所の処刑場の絞首台
繁栄は長くは続かなかった。もともと砂漠地帯で水が不足していた上、爆発的な人口増加によって突貫工事で建てられた木造の建物が多かったトゥームストーンは、1881年と1882年5月の2度にわたって大火に見まわれた。特に2度目の大火は、トゥームストーンの繁栄の歴史に終止符を打ったと言っても過言ではないものであった。1880年代中盤に入ると、銀鉱は掘り尽くされ、坑内は地下水であふれるようになった。
以後、トゥームストーンは凋落への道をたどり、ゴーストタウンと化した。1929年には南東約45kmに位置し、銅の露天掘りで人口が増えたビズビーに郡庁が移った。しかし、旧コカイズ郡裁判所と隣接する処刑場は博物館として残っている。
ブート・ヒル墓地(Boot Hill Graveyard)は、トゥームストーンが繁栄していた時期に暴力、または病気で亡くなった人たちが眠る墓地である。この墓地はトゥームストーンでリンチにあった、もしくは死刑を受けた者(人違いで死刑になった者もいるとの解説が墓地内にある)の行き先でもあり、死者が履いていたブーツが墓碑(簡素な木製のもの)に掛けられたことから、この名が付いた。現在、墓碑は木を模した金属製に置き換えられているが、当時の雰囲気を充分に味わうことができる。この歴史的な墓場の入り口には土産物屋があり、その店内から入場料を払い入ることになる。
1881年にトゥームストーンで起きた暴力事件の代表とも言えるOK牧場の決闘が起きた場所も史跡として残っている。同史跡は見学料を課しているが、市のメインストリートであるフレモント通り(州道80号線)からその大部分を見ることができる。
トゥームストーンはまた、世界最大のバラの茂みが植えられている地でもある。このバラの茂みはギネスブックにも登録されている。1885年に植えられたこのレディー・バンクシア種(Lady Banksia)のバラは、1年を通じて晴天に恵まれたこの地の気候の影響もあって成長状態が良く、宿屋の屋根上約743m²をカバーし、12本の幹を有している。[1]
現在のダウンタウン・トゥームストーン
こういった歴史的なものが数多く存在するトゥームストーンは、1961年に「1870年代から1880年代にかけての辺境の町の町並みが最もよく保存された例」として国の歴史地区に指定された。現在のトゥームストーンの主産業はこの歴史地区を生かした観光である。2005年7月に発表されたCNNの記事によると、トゥームストーンを訪れる観光客の数は年間450,000人に上る。現在の常住人口が約1,500人であるので、人口1人あたり300人の観光客が訪れている計算になる。しかし市内の酒場が24時間営業し、売春宿が立ち並んだ全盛期とは異なり、現在のトゥームストーンは落ち着いたコミュニティで、夜遅くまで開いている店はほとんどない。
しかし過度な観光化は、トゥームストーンの歴史的価値が危機にさらすことでもあった。2004年、アメリカ国立公園局(NPS)はトゥームストーンの歴史地区が「危機状態」にあると宣言し、地元コミュニティに対し、適切なスチュワードシップ制による保全を求めた。国立公園局が不適切と指摘した点には次のようなものがある。
新しく建てられた建物に対し「歴史的」な日付の記載がなされている。
新しく建てられた建物と歴史的建造物との区別が困難である。
歴史的建造物に対し、不適切な建材を用いている。
歴史的建造物を修復するのではなく、新たに建て替えている。
憶測による、十分な根拠のない建材で建て替えられ、建物の歴史的側面が失われている。
既存の歴史的建造物を大幅に増築したり、敷地内に新しい建物を建てたりしている。
歴史的な看板を囲む点滅灯の使用など、看板にイルミネーションを用いている。
トゥームストーンに存在しなかったはずの建築様式で建物が建てられている。
また、市内の道が舗装されたことも、歴史的な町並みの保存に反するものであるとされた。
これらの問題点の対策として、2006年1月現在、トゥームストーン修復委員会(Tombstone Restoration Committee)は市内の歴史的建造物の修復に尽力している。市内の通りに施された舗装は剥がされ、再び「歴史的」な埃道に戻った。
地理[編集]
トゥームストーンの位置
トゥームストーンは北緯31度42分57秒西経110度3分53秒(31.715940, -110.064827)に位置している。ツーソンの東南東約110km、フェニックスの南東約300kmに位置している。
アメリカ合衆国統計局によると、トゥームストーン市は総面積11.1km²(4.3mi²)である。市の全域が陸地であり、水域はない。
ダウンタウンは西北西-東南東方向に約2km、北北東-南南西方向に約800mの範囲内に収まっている。ダウンタウンの道路は整然と区画されている。アリゾナ州道80号線がダウンタウンを通っており、フレモント通り(Fremont Street)として市のメインストリートになっている。西部開拓時代の町並み保存の一環として、アレン通り(Allen Street)など一部のダウンタウンの通りは舗装が剥がされている。
トゥームストーンの気候は温暖な冬と暑い夏、そして1年を通じて乾燥した気候に特徴付けられる。夏の平均気温は摂氏27度ほどだが、日中は摂氏35度に達する。ただし湿度が低いため、夜になると摂氏20度程度まで下がって涼しくなり、日本のような熱帯夜にはならない。冬でも平均気温は摂氏10度程度、夜でも氷点下に下がることは滅多にない。降水量は1年を通じて月間0-25mmほどであるが、7月・8月は短い雨季で、月間75mm程度の降水がある。年間降水量は200-250mm程度である。ケッペンの気候区分では砂漠気候(BW)に属する。
人口動勢[編集]
以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。
基礎データ 人口: 1,504人
世帯数: 694世帯
家族数: 419家族
人口密度: 135.0人/km²(349.8人/mi²)
住居数: 839軒
住居密度: 75.3軒/km²(195.1軒/mi²)
人種別人口構成 白人: 87.37 %
黒人: 0.60 %
インディアン: 1.00 %
アジア人: 0.33 %
その他の人種: 8.18 %
混血: 2.53 %
ヒスパニック・ラテン系: 24.14 %
年齢別人口構成 18歳未満: 19.3 %
18-24歳: 4.9 %
25-44歳: 19.9 %
45-64歳: 32.5 %
65歳以上: 23.3 %
年齢の中央値: 49歳
性比(女性100人あたり男性の人口) 総人口: 94.3
18歳以上: 91.0
世帯と家族(対世帯数) 18歳未満の子供がいる: 20.2 %
結婚・同居している夫婦: 47.6 %
未婚・離婚・死別女性が世帯主: 7.9 %
非家族世帯: 39.5 %
単身世帯: 32.9 %
65歳以上の老人1人暮らし: 15.3 %
平均構成人数 世帯: 2.17人
家族: 2.73人
収入と家計 収入の中央値 世帯: 26,571米ドル
家族: 33,750米ドル
性別 男性: 26,923米ドル
女性: 18,846米ドル
人口1人あたり収入: 15,447米ドル
貧困線以下 対人口: 17.4 %
対家族数: 13.0 %
18歳未満: 22.6 %
65歳以上: 13.1 %