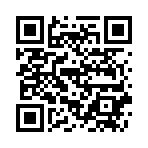テキサスビルのシユーテイングブログ
カウボーイとリボルバーとオートマとの葉巻のぶろぐです
2014年04月06日
ウィンチェスターライフル
ウィンチェスターライフル
移動: 案内、 検索
ウィンチェスターライフル
ウィンチェスターM1873
ウィンチェスターライフル
種類
レバーアクションライフル
製造国
アメリカ合衆国
設計・製造
ウィンチェスター社
年代
西部開拓時代
仕様
口径
.44口径、.38口径、.32口径
.22口径など
銃身長
76.2cm
使用弾薬
.44-40弾、.38-40弾、.32-20弾
.22LR弾など
装弾数
14発
作動方式
レバーアクション
全長
125.2cm
重量
4.3kg
歴史
設計年
1873年
製造期間
1873年-1919年
配備先
ガンマンやカウボーイ、アウトローなど
テンプレートを表示
ウィンチェスターライフル(英: Winchester rifle)は、西部開拓時代のアメリカにおいてウィンチェスター社が開発したレバーアクションライフルである。
目次
[非表示] 1 開発経緯
2 改良
3 その後
4 登場作品
5 関連項目
6 外部リンク
開発経緯[編集]
西部開拓時代のアメリカにおける銃器開発で有名になった企業としてコルト社が挙げられる。SAAをはじめとしたコルト社製リボルバーは開拓時代において保安官から巷のならず者に至るまで護身用として所有していた拳銃であるが、それに平行してライフル銃を製造していた企業がウィンチェスター社である。
ウィンチェスター社はオリバー・ウィンチェスターにより創業され、もともとは開拓民の洋服などを販売していた企業であるが、1857年に武器製造工場を買収しライフル銃などの武器製造を始め、後にジョン・ブローニングが開発したレバーアクション機能を有するライフル銃「レバーアクションライフル」の製造権を買い取り、アメリカ全土に販売した。 レバーアクションとは銃の機関部下側に突き出したレバーを下に引き、それをまた戻すことで薬室から空薬莢を排除すると同時に次弾を装填するという仕組みである。この機構はもともと南北戦争で使用されていた単発式ライフル銃をジョン・ブローニングが改良したものであり、それまで1発発射するたびに弾込めが必要であったライフル銃を10発以上連射できるようにした。ウィンチェスター社はこの画期的なライフルの製造権を取得すると、オリバーの息子であるウィリアムにより全米で販売されるようになった。
改良[編集]
ウィンチェスターライフル。左からM73、M73、M94、M92、M92Trapper
工場の買収後、ライフル銃の生産を盛んに行ってきたウィンチェスター社はその後もレバーアクションライフルの生産を続け、西部を代表するライフルメーカーとなった。このウィンチェスターライフルの中でも有名な機種としては西部劇に多く登場する「M1866(イエローボーイ)」、「M1873」、「M1892」が挙げられるが、これらはいずれも強力なライフルカートリッジの連射に充分に耐えられるほどの耐久力を持っておらず、ライフルでありながら実際は拳銃弾しか使用できないというものであった。
この問題点を改善するため、有名な銃技師ジョン・ブローニングによって、それまでのウィンチェスターライフルの中で最も完成度が高いといわれるM1892を基に、レバーアクション方式を継承しながら新機構の採用や機関部の強度向上を施した「M1894」が開発された。このM1894はいくつかの軍隊に対して売り込みが行われたが、レバーアクション方式のライフルであるがゆえに機構が複雑で機関部が露出する部分も多かったため、泥やホコリまみれの野戦には不向きであると判断され軍では不評であった。ブローニングが設計に関わったものとして ショットガン用の弾薬を使用する「M1887」というモデルも存在するが、大柄なショットシェルとは相性が悪かったらしく、作動不良を起こすなど評価は芳しくない。
アメリカ陸軍では評判の悪かったウィンチェスターライフルであるが、その後ロシア帝国から発注を受けることになる。当時のロシア帝国における標準的なライフル弾は7.62mm×54R弾(ラシアン)であったため、ウィンチェスター社はこのラシアン弾を使用できるように改良し垂直式の弾倉を装備した「M1895」をロシアに輸出した。M1895は予定通りロシア軍に採用され、最後の軍用レバーアクションライフルとなった。
その後[編集]
連射がそれなりに早く行えるライフルとして登場したウィンチェスターライフルであるが19世紀の終わりごろに登場したボルトアクションライフルが手動式ライフルの主流になると、ボルトアクションライフルよりも高価で機構が複雑なレバーアクションライフルは実戦の場から消えていった。2006年1月、ウィンチェスター社に代わってレバーアクションライフルを製造していたUSリピーティングアームズ社は全モデルの生産終了・工場閉鎖を表明。これによって純正モデルの生産は終わり、ブランドを引き継ぐ外国メーカーのライセンス生産品のみとなる。(ブラジルのトーラス社など)
登場作品[編集]
映画 『ウィンチェスター銃'73』
1950年のアメリカ映画。 『風来坊探偵 赤い谷の惨劇』
1961年の日本映画で、千葉真一演ずる主人公が使用。 『荒野の用心棒』
1964年のイタリア映画。 『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3』
1980年のアメリカ映画で、クリストファー・ロイド演ずるエメット・ブラウン博士(ドク)が改造したものを使用。 『ショーン・オブ・ザ・デッド』
2004年のイギリス映画。パブの名前にもなっている。 『バイオハザードIII』
2007年のアメリカ映画。 『噂のモーガン夫妻』
2009年のアメリカ映画。 『スティーヴ・オースティン S.W.A.T.』
年代物のBBガン。 ドラマ 『マードック・ミステリー 〜刑事マードックの捜査ファイル〜』
『ライフルマン』
楽曲 『ウィンチェスター73(小林旭)』
小林旭の楽曲。 ゲーム 『Fall out NEW VEGAS -フォールアウトニューベガス-』
カウボーイ・リピーターという名称の武器として登場。ニューカルフォルニア共和国のレンジャー達が主に使用する。使用弾薬は.357マグナム弾。 『KILLING FLOOR -キリング フロア-』
『グランド・セフト・オート・バイスシティ・ストーリーズ』
「ショットガン」という名称で登場。 『うみねこのなく頃に』
『Red Dead Redemption -レッド・デッド・リデンプション』
『レッド・デッド・リボルバー』
漫画 『荒野の少年イサム』
『魔法とパンツとオレ』

移動: 案内、 検索
ウィンチェスターライフル
ウィンチェスターM1873
ウィンチェスターライフル
種類
レバーアクションライフル
製造国
アメリカ合衆国
設計・製造
ウィンチェスター社
年代
西部開拓時代
仕様
口径
.44口径、.38口径、.32口径
.22口径など
銃身長
76.2cm
使用弾薬
.44-40弾、.38-40弾、.32-20弾
.22LR弾など
装弾数
14発
作動方式
レバーアクション
全長
125.2cm
重量
4.3kg
歴史
設計年
1873年
製造期間
1873年-1919年
配備先
ガンマンやカウボーイ、アウトローなど
テンプレートを表示
ウィンチェスターライフル(英: Winchester rifle)は、西部開拓時代のアメリカにおいてウィンチェスター社が開発したレバーアクションライフルである。
目次
[非表示] 1 開発経緯
2 改良
3 その後
4 登場作品
5 関連項目
6 外部リンク
開発経緯[編集]
西部開拓時代のアメリカにおける銃器開発で有名になった企業としてコルト社が挙げられる。SAAをはじめとしたコルト社製リボルバーは開拓時代において保安官から巷のならず者に至るまで護身用として所有していた拳銃であるが、それに平行してライフル銃を製造していた企業がウィンチェスター社である。
ウィンチェスター社はオリバー・ウィンチェスターにより創業され、もともとは開拓民の洋服などを販売していた企業であるが、1857年に武器製造工場を買収しライフル銃などの武器製造を始め、後にジョン・ブローニングが開発したレバーアクション機能を有するライフル銃「レバーアクションライフル」の製造権を買い取り、アメリカ全土に販売した。 レバーアクションとは銃の機関部下側に突き出したレバーを下に引き、それをまた戻すことで薬室から空薬莢を排除すると同時に次弾を装填するという仕組みである。この機構はもともと南北戦争で使用されていた単発式ライフル銃をジョン・ブローニングが改良したものであり、それまで1発発射するたびに弾込めが必要であったライフル銃を10発以上連射できるようにした。ウィンチェスター社はこの画期的なライフルの製造権を取得すると、オリバーの息子であるウィリアムにより全米で販売されるようになった。
改良[編集]
ウィンチェスターライフル。左からM73、M73、M94、M92、M92Trapper
工場の買収後、ライフル銃の生産を盛んに行ってきたウィンチェスター社はその後もレバーアクションライフルの生産を続け、西部を代表するライフルメーカーとなった。このウィンチェスターライフルの中でも有名な機種としては西部劇に多く登場する「M1866(イエローボーイ)」、「M1873」、「M1892」が挙げられるが、これらはいずれも強力なライフルカートリッジの連射に充分に耐えられるほどの耐久力を持っておらず、ライフルでありながら実際は拳銃弾しか使用できないというものであった。
この問題点を改善するため、有名な銃技師ジョン・ブローニングによって、それまでのウィンチェスターライフルの中で最も完成度が高いといわれるM1892を基に、レバーアクション方式を継承しながら新機構の採用や機関部の強度向上を施した「M1894」が開発された。このM1894はいくつかの軍隊に対して売り込みが行われたが、レバーアクション方式のライフルであるがゆえに機構が複雑で機関部が露出する部分も多かったため、泥やホコリまみれの野戦には不向きであると判断され軍では不評であった。ブローニングが設計に関わったものとして ショットガン用の弾薬を使用する「M1887」というモデルも存在するが、大柄なショットシェルとは相性が悪かったらしく、作動不良を起こすなど評価は芳しくない。
アメリカ陸軍では評判の悪かったウィンチェスターライフルであるが、その後ロシア帝国から発注を受けることになる。当時のロシア帝国における標準的なライフル弾は7.62mm×54R弾(ラシアン)であったため、ウィンチェスター社はこのラシアン弾を使用できるように改良し垂直式の弾倉を装備した「M1895」をロシアに輸出した。M1895は予定通りロシア軍に採用され、最後の軍用レバーアクションライフルとなった。
その後[編集]
連射がそれなりに早く行えるライフルとして登場したウィンチェスターライフルであるが19世紀の終わりごろに登場したボルトアクションライフルが手動式ライフルの主流になると、ボルトアクションライフルよりも高価で機構が複雑なレバーアクションライフルは実戦の場から消えていった。2006年1月、ウィンチェスター社に代わってレバーアクションライフルを製造していたUSリピーティングアームズ社は全モデルの生産終了・工場閉鎖を表明。これによって純正モデルの生産は終わり、ブランドを引き継ぐ外国メーカーのライセンス生産品のみとなる。(ブラジルのトーラス社など)
登場作品[編集]
映画 『ウィンチェスター銃'73』
1950年のアメリカ映画。 『風来坊探偵 赤い谷の惨劇』
1961年の日本映画で、千葉真一演ずる主人公が使用。 『荒野の用心棒』
1964年のイタリア映画。 『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3』
1980年のアメリカ映画で、クリストファー・ロイド演ずるエメット・ブラウン博士(ドク)が改造したものを使用。 『ショーン・オブ・ザ・デッド』
2004年のイギリス映画。パブの名前にもなっている。 『バイオハザードIII』
2007年のアメリカ映画。 『噂のモーガン夫妻』
2009年のアメリカ映画。 『スティーヴ・オースティン S.W.A.T.』
年代物のBBガン。 ドラマ 『マードック・ミステリー 〜刑事マードックの捜査ファイル〜』
『ライフルマン』
楽曲 『ウィンチェスター73(小林旭)』
小林旭の楽曲。 ゲーム 『Fall out NEW VEGAS -フォールアウトニューベガス-』
カウボーイ・リピーターという名称の武器として登場。ニューカルフォルニア共和国のレンジャー達が主に使用する。使用弾薬は.357マグナム弾。 『KILLING FLOOR -キリング フロア-』
『グランド・セフト・オート・バイスシティ・ストーリーズ』
「ショットガン」という名称で登場。 『うみねこのなく頃に』
『Red Dead Redemption -レッド・デッド・リデンプション』
『レッド・デッド・リボルバー』
漫画 『荒野の少年イサム』
『魔法とパンツとオレ』

2014年04月06日
スペンサー銃
スペンサー銃
移動: 案内、 検索
スペンサー連発銃
1865 スペンサーライフル
スペンサー連発銃
種類
レバーアクションライフル
製造国
アメリカ合衆国
設計・製造
クリストファー・スペンサー・スペンサー社
バンサードライフル
ウィンチェスター社
年代
19世紀中ごろ
仕様
口径
14mm
銃身長
30インチ(1200mmモデル)
22インチ(997mmカービンモデル)
使用弾薬
.56-56 スペンサー
装弾数
7発
作動方式
手動コック式ハンマー、レバーアクション
全長
1200mm(47インチ)
997mm(39.25インチ)
発射速度
14~20発/分
銃口初速
284~315m/秒
有効射程
200ヤード
歴史
設計年
1860年
製造期間
1860年~1869年
配備先
アメリカ陸軍、アメリカ海軍
南部連邦
幕府歩兵隊
関連戦争・紛争
南北戦争
インディアン戦争
戊辰戦争
製造数
約20万挺
テンプレートを表示
スペンサー銃、スペンサー連発銃(英:Spencer repeating rifle)は、管状弾倉装填式・手動操作式のレバーアクションライフルである。
南北戦争中の北軍、特に騎兵隊に採用された。しかし当時の標準装備である前装式ライフルマスケットを置き換えることはなかった。
スペンサー騎兵銃(Spencer carbine)は騎兵向けに短銃身化されたカービン。
目次
[非表示] 1 概要
2 歴史
3 日本のスペンサー銃
4 関連項目
概要[編集]
設計は、1860年にクリストファー・スペンサーによって完成した。それは.56-56スペンサーリムファイアカートリッジを使用する、弾倉装填式、手動操作式ライフルのための設計だった。後のカートリッジ表示と異なって、最初の数は薬莢後部(リムの直前部分)の直径について、2番目の数が薬莢前部の直径について言及していた。実際の弾丸直径は0.52インチだった。カートリッジには45グレイン(2.9g)の黒色火薬を充填していた。
スペンサー銃を使用するにあたっては、使用済みの薬莢を排出して、管状弾倉から新しいカートリッジを装填するためにレバーを動かさなければならなかった。また、スプリングフィールドM1873トラップドアのように、撃鉄を別動作で手動で起こさなければならなかった。
スペンサー銃は弾を次々と発射できるように、7発入り管状弾倉に収納されたリムファイアカートリッジを使用した。空になったときには、管状弾倉に新しいカートリッジを落とすことによってか、または、ブレイクスリーカートリッジボックス(blakeslee cartridge box)と呼ばれる弾薬盒から素早く装填することができた。ブレイクスリーカートリッジボックスには各7発入りのチューブが入っていた。6本入りと10本入りと13本入りがあった。ブレイクスリーカートリッジボックスは銃床内の管状弾倉を空状態にすることを可能にした。
カートリッジには.56-52、.56-50もあり、.56-46のバージョンさえ少数が作られた。それらはオリジナルの56-56のネックダウンバージョンであった。カートリッジの長さは作動機構によって約1.75インチに制限された。
そして後期の口径は、オリジナルの.56-56以上に威力と射程を増すために、より小さい直径、より軽い弾丸、より多い装薬量を用いた。それらは当時の口径0.58インチのライフルマスケットとおおよそ同じくらい強力であったが、.45-70と.50-70ガバメント弾のような他の初期の実包の規格によっては威力不足だった。
歴史[編集]
当初、陸軍省の保守主義は、スペンサー連発銃の軍への導入を遅らせた。しかしクリストファー・スペンサーは、結局、エイブラハム・リンカーン大統領に謁見できた。次に、彼は射撃競技会と兵器の展示会に大統領を招待した。リンカーンはスペンサー銃に感銘を受け、それを採用し製造するよう命じた。
スペンサー連発銃は、最初にアメリカ海軍、次にアメリカ陸軍によって採用され、南北戦争の間、使用された。アメリカ連合国は時折これらの兵器と弾薬の一部を鹵獲したが、銅の不足のためにカートリッジを製造できなかったので、兵器を活用する彼らの能力は制限されていた。
注目に値する早期の使用例はフーヴァーズギャップの戦闘(ジョン・T・ワイルダー大佐の「稲妻旅団」が連発銃の火力を効果的に示した場所)と、ゲティスバーグの戦い(ジョージ・アームストロング・カスター准将麾下のミシガン旅団の2個連隊が、ハノーヴァーの戦闘と、東の騎兵の戦場において、スペンサー銃を運用した場所)を含んでいた。
戦争が進むにつれて、スペンサー銃は、多くの北軍騎兵と騎乗歩兵連隊によって運用され、追加火力と共に、南軍に対抗する北軍に供給された。
スペンサー騎兵銃 M1865 .50口径
スペンサー銃は、持続可能な毎分20発以上の発射速度とともに、戦闘という状況下で非常に信頼できることを示した。毎分2-3発の発射速度の標準的な前装銃と比べて、これは重要な戦術的な利点だった。しかし高い発射速度の利点を活かす効果的な戦術がまだ開発されていなかった。同様に、予備弾薬を運ぶための補給及び輜重(サプライチェーン)を備えていなかった。また中傷者は、発生した煙で敵が発見しにくいと不平を言うだろう。
1860年代後期に、スペンサー社はフォーガティライフル社に、そして最終的にウィンチェスター社に売却された。およそ20万挺のライフルとカービンが製造された。いくつかの国では、初めて採用された弾倉装填式歩兵銃であった。後に多くのスペンサー騎兵銃が余剰品としてフランスに販売され、1870年の普仏戦争で使用された。
スペンサー社が1869年に倒産したという事実にもかかわらず、弾薬が1920年代頃まで合衆国で販売されていた。後に多くのライフルとカービンがセンターファイア方式に改造されて、真鍮製.50-70センターファイアカートリッジを撃てるようになった。製造弾薬が未だに専門市場で入手できる。
日本のスペンサー銃[編集]
南北戦争後、アメリカで余剰となったスペンサー銃、スペンサー騎兵銃が、幕末の日本に輸入された。幕府歩兵隊(後の大鳥圭介配下含む)と主に佐賀藩・黒羽藩が購入して装備し、戊辰戦争で使用したが、高価なこともあって、他の輸入銃に比べて、その数は多くはない。この他に、郡上藩の凌霜隊(同藩の佐幕派から成る諸隊の一つ)も装備していたとみられ、少数とはいえ討幕・佐幕双方で使用していたといわれる。
会津藩士の山本覚馬は長崎でスペンサー騎兵銃を購入し、会津に居た妹の八重に送った。彼女が戊辰戦争の会津若松城籠城戦で城に入り、この銃で奮戦したエピソードが知られている。『八重の桜』で八重を演じた綾瀬はるかは、戦闘のシーンで、実物と同じおよそ5キログラムあるこの銃のステージガンを抱えて走り回る必要上、腕立て伏せをして腕力を鍛え撮影に臨んだという。
関連項目[編集]
ゲベール銃
スナイドル銃
エンフィールド銃
マルティニ・ヘンリー銃
ミニエー銃
シャスポー銃
グラース銃
ヘンリー銃

移動: 案内、 検索
スペンサー連発銃
1865 スペンサーライフル
スペンサー連発銃
種類
レバーアクションライフル
製造国
アメリカ合衆国
設計・製造
クリストファー・スペンサー・スペンサー社
バンサードライフル
ウィンチェスター社
年代
19世紀中ごろ
仕様
口径
14mm
銃身長
30インチ(1200mmモデル)
22インチ(997mmカービンモデル)
使用弾薬
.56-56 スペンサー
装弾数
7発
作動方式
手動コック式ハンマー、レバーアクション
全長
1200mm(47インチ)
997mm(39.25インチ)
発射速度
14~20発/分
銃口初速
284~315m/秒
有効射程
200ヤード
歴史
設計年
1860年
製造期間
1860年~1869年
配備先
アメリカ陸軍、アメリカ海軍
南部連邦
幕府歩兵隊
関連戦争・紛争
南北戦争
インディアン戦争
戊辰戦争
製造数
約20万挺
テンプレートを表示
スペンサー銃、スペンサー連発銃(英:Spencer repeating rifle)は、管状弾倉装填式・手動操作式のレバーアクションライフルである。
南北戦争中の北軍、特に騎兵隊に採用された。しかし当時の標準装備である前装式ライフルマスケットを置き換えることはなかった。
スペンサー騎兵銃(Spencer carbine)は騎兵向けに短銃身化されたカービン。
目次
[非表示] 1 概要
2 歴史
3 日本のスペンサー銃
4 関連項目
概要[編集]
設計は、1860年にクリストファー・スペンサーによって完成した。それは.56-56スペンサーリムファイアカートリッジを使用する、弾倉装填式、手動操作式ライフルのための設計だった。後のカートリッジ表示と異なって、最初の数は薬莢後部(リムの直前部分)の直径について、2番目の数が薬莢前部の直径について言及していた。実際の弾丸直径は0.52インチだった。カートリッジには45グレイン(2.9g)の黒色火薬を充填していた。
スペンサー銃を使用するにあたっては、使用済みの薬莢を排出して、管状弾倉から新しいカートリッジを装填するためにレバーを動かさなければならなかった。また、スプリングフィールドM1873トラップドアのように、撃鉄を別動作で手動で起こさなければならなかった。
スペンサー銃は弾を次々と発射できるように、7発入り管状弾倉に収納されたリムファイアカートリッジを使用した。空になったときには、管状弾倉に新しいカートリッジを落とすことによってか、または、ブレイクスリーカートリッジボックス(blakeslee cartridge box)と呼ばれる弾薬盒から素早く装填することができた。ブレイクスリーカートリッジボックスには各7発入りのチューブが入っていた。6本入りと10本入りと13本入りがあった。ブレイクスリーカートリッジボックスは銃床内の管状弾倉を空状態にすることを可能にした。
カートリッジには.56-52、.56-50もあり、.56-46のバージョンさえ少数が作られた。それらはオリジナルの56-56のネックダウンバージョンであった。カートリッジの長さは作動機構によって約1.75インチに制限された。
そして後期の口径は、オリジナルの.56-56以上に威力と射程を増すために、より小さい直径、より軽い弾丸、より多い装薬量を用いた。それらは当時の口径0.58インチのライフルマスケットとおおよそ同じくらい強力であったが、.45-70と.50-70ガバメント弾のような他の初期の実包の規格によっては威力不足だった。
歴史[編集]
当初、陸軍省の保守主義は、スペンサー連発銃の軍への導入を遅らせた。しかしクリストファー・スペンサーは、結局、エイブラハム・リンカーン大統領に謁見できた。次に、彼は射撃競技会と兵器の展示会に大統領を招待した。リンカーンはスペンサー銃に感銘を受け、それを採用し製造するよう命じた。
スペンサー連発銃は、最初にアメリカ海軍、次にアメリカ陸軍によって採用され、南北戦争の間、使用された。アメリカ連合国は時折これらの兵器と弾薬の一部を鹵獲したが、銅の不足のためにカートリッジを製造できなかったので、兵器を活用する彼らの能力は制限されていた。
注目に値する早期の使用例はフーヴァーズギャップの戦闘(ジョン・T・ワイルダー大佐の「稲妻旅団」が連発銃の火力を効果的に示した場所)と、ゲティスバーグの戦い(ジョージ・アームストロング・カスター准将麾下のミシガン旅団の2個連隊が、ハノーヴァーの戦闘と、東の騎兵の戦場において、スペンサー銃を運用した場所)を含んでいた。
戦争が進むにつれて、スペンサー銃は、多くの北軍騎兵と騎乗歩兵連隊によって運用され、追加火力と共に、南軍に対抗する北軍に供給された。
スペンサー騎兵銃 M1865 .50口径
スペンサー銃は、持続可能な毎分20発以上の発射速度とともに、戦闘という状況下で非常に信頼できることを示した。毎分2-3発の発射速度の標準的な前装銃と比べて、これは重要な戦術的な利点だった。しかし高い発射速度の利点を活かす効果的な戦術がまだ開発されていなかった。同様に、予備弾薬を運ぶための補給及び輜重(サプライチェーン)を備えていなかった。また中傷者は、発生した煙で敵が発見しにくいと不平を言うだろう。
1860年代後期に、スペンサー社はフォーガティライフル社に、そして最終的にウィンチェスター社に売却された。およそ20万挺のライフルとカービンが製造された。いくつかの国では、初めて採用された弾倉装填式歩兵銃であった。後に多くのスペンサー騎兵銃が余剰品としてフランスに販売され、1870年の普仏戦争で使用された。
スペンサー社が1869年に倒産したという事実にもかかわらず、弾薬が1920年代頃まで合衆国で販売されていた。後に多くのライフルとカービンがセンターファイア方式に改造されて、真鍮製.50-70センターファイアカートリッジを撃てるようになった。製造弾薬が未だに専門市場で入手できる。
日本のスペンサー銃[編集]
南北戦争後、アメリカで余剰となったスペンサー銃、スペンサー騎兵銃が、幕末の日本に輸入された。幕府歩兵隊(後の大鳥圭介配下含む)と主に佐賀藩・黒羽藩が購入して装備し、戊辰戦争で使用したが、高価なこともあって、他の輸入銃に比べて、その数は多くはない。この他に、郡上藩の凌霜隊(同藩の佐幕派から成る諸隊の一つ)も装備していたとみられ、少数とはいえ討幕・佐幕双方で使用していたといわれる。
会津藩士の山本覚馬は長崎でスペンサー騎兵銃を購入し、会津に居た妹の八重に送った。彼女が戊辰戦争の会津若松城籠城戦で城に入り、この銃で奮戦したエピソードが知られている。『八重の桜』で八重を演じた綾瀬はるかは、戦闘のシーンで、実物と同じおよそ5キログラムあるこの銃のステージガンを抱えて走り回る必要上、腕立て伏せをして腕力を鍛え撮影に臨んだという。
関連項目[編集]
ゲベール銃
スナイドル銃
エンフィールド銃
マルティニ・ヘンリー銃
ミニエー銃
シャスポー銃
グラース銃
ヘンリー銃

2014年04月06日
マルティニ・ヘンリー銃
マルティニ・ヘンリー銃
移動: 案内、 検索
マルティニ・ヘンリー Mk.1~4
マルティニ・ヘンリー Mk.4 小銃
マルティニ・ヘンリー Mk.1~4
種類
軍用小銃
製造国
イギリス
設計・製造
王立小火器工廠
年代
19世紀
仕様
種別
後装式小銃
口径
11.6mm(0.455インチ)
使用弾薬
.577/450マルティニ・ヘンリー弾
装弾数
1発
作動方式
フォーリングブロックアクション方式
全長
1245mm(49インチ)
重量
3.827kg
発射速度
12発/分
銃口初速
380m/秒
最大射程
1900ヤード (約1700m)
有効射程
400ヤード (約370m)
歴史
設計年
1870年
製造期間
1871年 - 1891年
配備期間
1871年 - 1888年
配備先
大英帝国とその植民地、大日本帝國海軍陸戦隊
関連戦争・紛争
イギリス植民地戦争、第二次アングロ-アフガン戦争、ズールー戦争、ボーア戦争、マフディー戦争、第一次世界大戦
バリエーション
マルティニ・ヘンリー カービン
グリーナー警察用散弾銃
製造数
約50万~100万挺
テンプレートを表示
マルティニ・ヘンリー銃(マルティニ・ヘンリーじゅう、英:Martini-Henry)は、イギリスで採用された、後装式・レバー作動方式の小銃である。作動にはフリードリッヒ・フォン・マルティニの設計(特定箇所や、基本形状がヘンリー・ピーボディの開発したピーボディ・ライフルと類似しているとして、しばしば指摘されている)が加えられ、旋条の入った銃身の設計は、銃匠であるスコッツマン・アレクサンダー・ヘンリーが行った。この銃が軍務に就いたのは1871年のことで、スナイダー・エンフィールド銃と代替された。また派生型は30年間を通じて大英帝国に用いられた。本銃は、金属製薬莢を採用した真の後装式としては、最初のイギリス軍制式小銃であった。
マルティニ・ヘンリー銃には4つの形式が存在する。マークI(1871年6月開発)、マークII、マークIII、マークIVである。また、1877年には派生型の一つにカービン銃が存在し、これはガリソン砲兵用カービン銃として分類される砲兵用カービン(マークI、マークII、マークIII)であり、またより小型の派生型が陸軍士官学校の訓練用小銃として設計された。マルティニ・ヘンリー小銃のマークIVは1889年に生産終了した。しかし、大英帝国における軍務での使用は第一次世界大戦の終結まで続き、アフガニスタンでは、少数が部族民の手によりソ連のアフガン侵攻に対して使用された。
マルティニ・ヘンリー銃は、北西辺境州の銃器製作者たちによって大規模に複製された。彼らの製作した兵器は、王立小火器工廠やエンフィールドと比較して貧しい品質であったが、これは性能試験の正確さが低下していたことによる。主な製作者たちはアダム・ケール市のアフリディ族である。彼らはカイバル峠の周辺に居住していた。このため、イギリスの言葉でこのような兵器はPass made rifles(峠製の銃)と呼ばれた。こうした兵器の生き残りの多くは、アフガニスタンの国際治安支援部隊に参加している部族の戦士に売却された。[要出典]
目次
[非表示] 1 概観 1.1 トルコ軍のピーボディ・マルティニ銃
1.2 日本におけるマルティニ・ヘンリー銃
2 マルティニ・アクションの作動について
3 関連項目
4 脚注
5 外部リンク
概観[編集]
(左から右の順に).577 スナイダー実包、ズールー戦争時代の真鍮板を巻いて成形した.577/450 マルティニ・ヘンリー実包、引き抜き成形された後期型真鍮製.577/450 マルティニ・ヘンリー実包、.303ブリティッシュ Mk.7 SAA 通常弾実包
オリジナルの装填方式を持つこの銃は、直径.451インチ(11.455mm)、重量480グレイン(31.104g)の弾丸を射出する。弾丸は起縁式薬莢にはめられており、今日この薬莢は.577/450実包として知られている。この実包は薬莢がボトルネック型に設計されており、基本はスナイダー・エンフィールド銃の.577実包と同じである。また、85グレイン(5.51g)の発射薬を用い、強力な反動が特徴である。空薬莢はレバー操作により後方から排出される。
小銃の全長は49インチ(124.5cm)であり、鋼鉄製の銃身は33.22インチ(84cm)である。ヘンリーの旋条の特許はヘプタゴナル(七角形)銃身の設計であり、七つの腔綫が22インチ(55.88cm)で一回転した。この兵器の全重は8ポンド7オンス(3.83kg)である。伍長から曹長までの陸軍下士官には銃剣が標準的に支給されており、着剣時には長さが延長されて68インチ(172.7cm)、重量は10ポンド4オンス(4.65kg)に増大した。
標準的な銃剣はソケットタイプの刺突剣であり、1853年型の旧式の銃剣(全長20.4インチ)や、1876年型の新式の銃剣(全長25インチ)と互換性があった。また、エルコー卿の開発した銃剣は叩き斬ることを目的にしており、他に非戦闘のいろいろな用途に使えた。これには二列の歯が追加されており、鋸としても使えた。しかし大量生産はされず、標準的な支給品にはならなかった。
本銃は1,400ヤード(1,300m)を照準できた。射程1,200ヤード(1,100m)では、射出された20発が標的の中央から27インチ(69.5cm)の散布界に入るという平均的な偏りを示しており、弾道の最高点は、500ヤード(450m)における高さ8フィート(2.44m)である。
エンフィールド・マルティニ銃は0.402口径のモデルで、安全装置のようないくつかのマイナーな改善を取り入れており、マルティニ・ヘンリー銃を代替するために1884年以前から段階的に導入された。代替が段階的なのは既存の古い弾薬のストックを使い果たすためである。
しかしながらこれが完了する前に、マルティニ銃をリー・メトフォード銃で刷新する決断がなされた。.303口径のこの銃はボルトアクション作動で弾倉が装備されており、かなり高い発射速度を与えた。従って軍務に3種の異なるライフル口径を採用するのを避けるために、エンフィールド・マルティニ銃は退役させられ、マルティニ・ヘンリー銃は0.45口径に換装された上で、「A」および「B」型小銃に改名した。また、黒色火薬を用いる0.303口径でカービン形式の派生型が少数生産され、これはマルティニ・メトフォード銃と呼ばれたほか、0.303口径でコルダイト火薬仕様のカービン銃もあり、マルティニ・エンフィールド銃と呼ばれた(エンフィールド・マルティニ銃と対照である)。
マルティニ・ヘンリー銃が軍務での運用を終えるまでの間に、英国陸軍は数多くの植民地戦争に巻き込まれたが、最も注目すべきものは1879年に起きたズールー戦争である。本銃は、ロークス・ドリフトに進出していた第24歩兵連隊、第2大隊所属の中隊によって使われた。この戦闘中、139名の英軍兵士が約1,000名のズールー戦士による攻撃に対抗し、防衛に成功した。マルティニ・ヘンリー銃の段階的な代替は1904年まで完了しなかった。
本銃は、ロークス・ドリフトの戦いに先立つイサンドルワナの戦いなどで起こった、英軍部隊の敗北に関して(拙劣な戦術と数的不利に加え)部分的に責を負うものとされる。マルティニ・ヘンリー銃は最高水準の技術にあったが、アフリカの気候の中において、酷使された後の本銃の作動には、過熱や詰まりを起こす傾向があった。これらから結果的にブリーチブロックを動かして小銃に再装填することが難しいものになった。問題の調査後、英軍兵器部は、原因が巻いて成形される真鍮製薬莢の脆弱な構造にあること、詰まりや汚染を起こすのは黒色火薬を用いた発射薬が主因であると決定した。これを修正するため、薬莢が脆弱な巻いて作る真鍮製のものから、強靭な引き抜き成形の真鍮製のものに換えられ、機関部が不具合を起こしたときにはより強いトルクで作動させられるよう、延長された装填レバーが取り付けられた。これらの後期派生型は戦闘において高い信頼性を持っていた。
稀少な散弾銃仕様の派生型がグリーナー警察用散弾銃として知られており、特別な実包を装填する。薬室形状と実包の特殊な形状から、この兵器は盗まれても弾薬の共用性がなく、利用できなかった[1]。この銃はリーズにある王立兵器博物館で見ることができる[2]。
もう一種の派生型はガヘンドラ小銃で、ネパールの地域で生産された。設計は基となったマルティニ・ヘンリー銃からやや進んでいるが、しかしこの銃は手製であることからその性能には様々な差がある。
マルティニ・ヘンリー銃は、第一次世界大戦の様々な任務にも主に補助兵器として投入された。また航空機の搭乗員に支給され(戦争の初期段階で)、観測気球や敵航空機の撃墜に用いられた。マルティニ・ヘンリー銃はまた、第一次世界大戦中、アフリカや中東の戦場で現地住民の補助部隊により用いられた。
トルコ軍のピーボディ・マルティニ銃[編集]
トルコはマルティニ・ヘンリー銃をイギリスから購入することができず、プロヴィデンスのロード・アイランドに所在したプロヴィデンス器具会社から同一の兵器を購入した。これらは露土戦争 (1877年)に投入された[3][4]。
日本におけるマルティニ・ヘンリー銃[編集]
日本におけるマルティニ・ヘンリー銃の配備は、慶応4年(明治元年、1868-1869年)の庄内藩での制式採用が最初の事例[5]で、後の明治4年(1871-1872年)には大日本帝國海軍の移乗攻撃部隊である海兵隊にて本銃が採用された。当時陸軍ではブリーチ式後装銃のスナイドル銃が採用されていたが、移乗攻撃という戦法の性質上速射性能を重視した為に海兵隊では本銃が採用されたという[6]。移乗攻撃が時代遅れとされた為、海兵隊は1876年に一度解体されるが、後に海兵隊の任務を内包する形で臨時編成部隊として発足した海軍陸戦隊でも村田銃の登場までスナイドル銃や本銃が併用されたという。
日本では前述のピーボディ・マルティニ銃と共にマルチニーヘンリー銃またはヘンリーマルチニー銃等と呼ばれていた。
先代:
日本海軍の建軍
日本軍制式小銃
1871-1880
次代:
村田銃
マルティニ・アクションの作動について[編集]
マルティニ・ヘンリー銃の閉鎖部
マルティニ・ヘンリー銃。
A:装填準備。
B:装填完了、および射撃位置
ロックとブリーチはストックからのメタルボルト(A)によって保持されている。ブリーチはブロック(B)により閉鎖されており、ピン(C)が回転するとブロック後方が開放されて通過可能になる。ブロックの終端はケース(D)と共にナックルジョイントを構成するために丸められており、反動をピン(C)よりもある程度多く吸収する。
トリガーガードの下部のレバー(E)は、ケース内部のタンブラー(G)を突きだすとき、ピン(F)を働かせる。このタンブラーはノッチ(H)の中へ移動し、ブロックを押し上げるよう働くもので、レバーの位置に応じて、射撃位置にこれを引き上げるか、これを落下位置に引く。
ブロック(B)は、実包を薬室(J)に装填するのを補助する上面(I)に沿ってへこんでいる。実包を発射するために、ブロックは実包に対して発射機構(K)をセットするよう位置を引き上げる。発射機構は、とがった金属製の撃針と、その周囲をとりまく螺旋形のバネから構成される。その先端は薬室に挿入された実包の電管へ打撃を与えるため、ブロック前面のホールを通過する。レバー(E)が前方へ動かされたとき、タンブラー(G)が回転し、アームの1本が連動する。そしてタンブラーをノッチ(H)が確実にロックするまで、スプリングが後退する。さらにバネは、タンブラーの下部の角に押し込まれるレストピース(L)によって保持される。
発射後、空薬莢はロックによって部分的に引き出される。エキストラクターはピン(M)を中心に回転する。これは2本の垂直の腕(N)を持っており、それらは空薬莢の後端の溝部に押され、元の位置である銃身脇に彫られた2条の筋へと押し戻される。レバーが前に押されるとき、エキストラクターのアームとベントアーム(O)は80°の角度を構成し、下がるブロックによって押しやられる。これにより直立するアームが少し空薬莢を引き抜き、より簡単に、完全な手動排莢が可能となる。
英国の軍用小銃と同様に、マルティニ・ブリーチ・アクションは英国のグリーナー社によって散弾銃に採用された。この単発の「EP」暴動鎮圧用銃は、旧英領の植民地では1970年代まで運用された。 グリーナー「GP」散弾銃もまたマルティニ・アクションを採用し、手軽に使える銃として20世紀中頃まで愛用された。マルティニ・アクションはBSA社も採用した。最近年の銃としては、BSA社のパーカー・ヘイルは彼らの手になる小口径射撃用ライフル「スモール・アクション・マルティニ」を1955年まで生産した。
関連項目[編集]
ビラ銃: 人力作動の機関銃。マルティニ・ヘンリー銃と同じく.577/450実包を装填する。
マルティニ・エンフィールド銃: マルティニ・ヘンリー銃の.303口径の派生型。
マルティニ・カデット銃: カデットライフル射撃用銃。
小銃・自動小銃等一覧
脚注[編集]
1.^ http://www.dave-cushman.net/shot/greenerpolice.html
2.^ http://www.cybershooters.org/Royal%20Armoury/Greener.JPG
3.^ M1874 Turkish Peabody-Martini: (types "A" and "B")
4.^ "The Turkish Connection: The Saga of the Peabody-Martini Rifle" by William O. Achtermeier. originally published in Man At Arms Magazine, Volume 1, Number 2, pp. 12-21, 55-57, March/April 1979
5.^ [www.water.sannet.ne.jp/kazuya-ai/27/rifle-gun.html 幕末の銃器]
6.^ 第玖章 設定資料集 9-3-2 兵士 - TRPG『維新の嵐』
Military Heritage did a feature on the Martini-Henry breach-loading rifle (Peter Suciu, Military Heritage, August 2005, Volume 7, No. 1, pp. 24 to 27), ISSN 1524-8666.
Small Arms Identification Series No 15: .450 & .303 Martini Rifles And Carbines (Ian Skennerton, Arms & Militaria Press) ISBN 0949749443.
Encyclopedia Britannica, "Gunmaking", 1905 edition
Official Report of the Calcutta International Exhibition, 1883-84, Military Exhibits

移動: 案内、 検索
マルティニ・ヘンリー Mk.1~4
マルティニ・ヘンリー Mk.4 小銃
マルティニ・ヘンリー Mk.1~4
種類
軍用小銃
製造国
イギリス
設計・製造
王立小火器工廠
年代
19世紀
仕様
種別
後装式小銃
口径
11.6mm(0.455インチ)
使用弾薬
.577/450マルティニ・ヘンリー弾
装弾数
1発
作動方式
フォーリングブロックアクション方式
全長
1245mm(49インチ)
重量
3.827kg
発射速度
12発/分
銃口初速
380m/秒
最大射程
1900ヤード (約1700m)
有効射程
400ヤード (約370m)
歴史
設計年
1870年
製造期間
1871年 - 1891年
配備期間
1871年 - 1888年
配備先
大英帝国とその植民地、大日本帝國海軍陸戦隊
関連戦争・紛争
イギリス植民地戦争、第二次アングロ-アフガン戦争、ズールー戦争、ボーア戦争、マフディー戦争、第一次世界大戦
バリエーション
マルティニ・ヘンリー カービン
グリーナー警察用散弾銃
製造数
約50万~100万挺
テンプレートを表示
マルティニ・ヘンリー銃(マルティニ・ヘンリーじゅう、英:Martini-Henry)は、イギリスで採用された、後装式・レバー作動方式の小銃である。作動にはフリードリッヒ・フォン・マルティニの設計(特定箇所や、基本形状がヘンリー・ピーボディの開発したピーボディ・ライフルと類似しているとして、しばしば指摘されている)が加えられ、旋条の入った銃身の設計は、銃匠であるスコッツマン・アレクサンダー・ヘンリーが行った。この銃が軍務に就いたのは1871年のことで、スナイダー・エンフィールド銃と代替された。また派生型は30年間を通じて大英帝国に用いられた。本銃は、金属製薬莢を採用した真の後装式としては、最初のイギリス軍制式小銃であった。
マルティニ・ヘンリー銃には4つの形式が存在する。マークI(1871年6月開発)、マークII、マークIII、マークIVである。また、1877年には派生型の一つにカービン銃が存在し、これはガリソン砲兵用カービン銃として分類される砲兵用カービン(マークI、マークII、マークIII)であり、またより小型の派生型が陸軍士官学校の訓練用小銃として設計された。マルティニ・ヘンリー小銃のマークIVは1889年に生産終了した。しかし、大英帝国における軍務での使用は第一次世界大戦の終結まで続き、アフガニスタンでは、少数が部族民の手によりソ連のアフガン侵攻に対して使用された。
マルティニ・ヘンリー銃は、北西辺境州の銃器製作者たちによって大規模に複製された。彼らの製作した兵器は、王立小火器工廠やエンフィールドと比較して貧しい品質であったが、これは性能試験の正確さが低下していたことによる。主な製作者たちはアダム・ケール市のアフリディ族である。彼らはカイバル峠の周辺に居住していた。このため、イギリスの言葉でこのような兵器はPass made rifles(峠製の銃)と呼ばれた。こうした兵器の生き残りの多くは、アフガニスタンの国際治安支援部隊に参加している部族の戦士に売却された。[要出典]
目次
[非表示] 1 概観 1.1 トルコ軍のピーボディ・マルティニ銃
1.2 日本におけるマルティニ・ヘンリー銃
2 マルティニ・アクションの作動について
3 関連項目
4 脚注
5 外部リンク
概観[編集]
(左から右の順に).577 スナイダー実包、ズールー戦争時代の真鍮板を巻いて成形した.577/450 マルティニ・ヘンリー実包、引き抜き成形された後期型真鍮製.577/450 マルティニ・ヘンリー実包、.303ブリティッシュ Mk.7 SAA 通常弾実包
オリジナルの装填方式を持つこの銃は、直径.451インチ(11.455mm)、重量480グレイン(31.104g)の弾丸を射出する。弾丸は起縁式薬莢にはめられており、今日この薬莢は.577/450実包として知られている。この実包は薬莢がボトルネック型に設計されており、基本はスナイダー・エンフィールド銃の.577実包と同じである。また、85グレイン(5.51g)の発射薬を用い、強力な反動が特徴である。空薬莢はレバー操作により後方から排出される。
小銃の全長は49インチ(124.5cm)であり、鋼鉄製の銃身は33.22インチ(84cm)である。ヘンリーの旋条の特許はヘプタゴナル(七角形)銃身の設計であり、七つの腔綫が22インチ(55.88cm)で一回転した。この兵器の全重は8ポンド7オンス(3.83kg)である。伍長から曹長までの陸軍下士官には銃剣が標準的に支給されており、着剣時には長さが延長されて68インチ(172.7cm)、重量は10ポンド4オンス(4.65kg)に増大した。
標準的な銃剣はソケットタイプの刺突剣であり、1853年型の旧式の銃剣(全長20.4インチ)や、1876年型の新式の銃剣(全長25インチ)と互換性があった。また、エルコー卿の開発した銃剣は叩き斬ることを目的にしており、他に非戦闘のいろいろな用途に使えた。これには二列の歯が追加されており、鋸としても使えた。しかし大量生産はされず、標準的な支給品にはならなかった。
本銃は1,400ヤード(1,300m)を照準できた。射程1,200ヤード(1,100m)では、射出された20発が標的の中央から27インチ(69.5cm)の散布界に入るという平均的な偏りを示しており、弾道の最高点は、500ヤード(450m)における高さ8フィート(2.44m)である。
エンフィールド・マルティニ銃は0.402口径のモデルで、安全装置のようないくつかのマイナーな改善を取り入れており、マルティニ・ヘンリー銃を代替するために1884年以前から段階的に導入された。代替が段階的なのは既存の古い弾薬のストックを使い果たすためである。
しかしながらこれが完了する前に、マルティニ銃をリー・メトフォード銃で刷新する決断がなされた。.303口径のこの銃はボルトアクション作動で弾倉が装備されており、かなり高い発射速度を与えた。従って軍務に3種の異なるライフル口径を採用するのを避けるために、エンフィールド・マルティニ銃は退役させられ、マルティニ・ヘンリー銃は0.45口径に換装された上で、「A」および「B」型小銃に改名した。また、黒色火薬を用いる0.303口径でカービン形式の派生型が少数生産され、これはマルティニ・メトフォード銃と呼ばれたほか、0.303口径でコルダイト火薬仕様のカービン銃もあり、マルティニ・エンフィールド銃と呼ばれた(エンフィールド・マルティニ銃と対照である)。
マルティニ・ヘンリー銃が軍務での運用を終えるまでの間に、英国陸軍は数多くの植民地戦争に巻き込まれたが、最も注目すべきものは1879年に起きたズールー戦争である。本銃は、ロークス・ドリフトに進出していた第24歩兵連隊、第2大隊所属の中隊によって使われた。この戦闘中、139名の英軍兵士が約1,000名のズールー戦士による攻撃に対抗し、防衛に成功した。マルティニ・ヘンリー銃の段階的な代替は1904年まで完了しなかった。
本銃は、ロークス・ドリフトの戦いに先立つイサンドルワナの戦いなどで起こった、英軍部隊の敗北に関して(拙劣な戦術と数的不利に加え)部分的に責を負うものとされる。マルティニ・ヘンリー銃は最高水準の技術にあったが、アフリカの気候の中において、酷使された後の本銃の作動には、過熱や詰まりを起こす傾向があった。これらから結果的にブリーチブロックを動かして小銃に再装填することが難しいものになった。問題の調査後、英軍兵器部は、原因が巻いて成形される真鍮製薬莢の脆弱な構造にあること、詰まりや汚染を起こすのは黒色火薬を用いた発射薬が主因であると決定した。これを修正するため、薬莢が脆弱な巻いて作る真鍮製のものから、強靭な引き抜き成形の真鍮製のものに換えられ、機関部が不具合を起こしたときにはより強いトルクで作動させられるよう、延長された装填レバーが取り付けられた。これらの後期派生型は戦闘において高い信頼性を持っていた。
稀少な散弾銃仕様の派生型がグリーナー警察用散弾銃として知られており、特別な実包を装填する。薬室形状と実包の特殊な形状から、この兵器は盗まれても弾薬の共用性がなく、利用できなかった[1]。この銃はリーズにある王立兵器博物館で見ることができる[2]。
もう一種の派生型はガヘンドラ小銃で、ネパールの地域で生産された。設計は基となったマルティニ・ヘンリー銃からやや進んでいるが、しかしこの銃は手製であることからその性能には様々な差がある。
マルティニ・ヘンリー銃は、第一次世界大戦の様々な任務にも主に補助兵器として投入された。また航空機の搭乗員に支給され(戦争の初期段階で)、観測気球や敵航空機の撃墜に用いられた。マルティニ・ヘンリー銃はまた、第一次世界大戦中、アフリカや中東の戦場で現地住民の補助部隊により用いられた。
トルコ軍のピーボディ・マルティニ銃[編集]
トルコはマルティニ・ヘンリー銃をイギリスから購入することができず、プロヴィデンスのロード・アイランドに所在したプロヴィデンス器具会社から同一の兵器を購入した。これらは露土戦争 (1877年)に投入された[3][4]。
日本におけるマルティニ・ヘンリー銃[編集]
日本におけるマルティニ・ヘンリー銃の配備は、慶応4年(明治元年、1868-1869年)の庄内藩での制式採用が最初の事例[5]で、後の明治4年(1871-1872年)には大日本帝國海軍の移乗攻撃部隊である海兵隊にて本銃が採用された。当時陸軍ではブリーチ式後装銃のスナイドル銃が採用されていたが、移乗攻撃という戦法の性質上速射性能を重視した為に海兵隊では本銃が採用されたという[6]。移乗攻撃が時代遅れとされた為、海兵隊は1876年に一度解体されるが、後に海兵隊の任務を内包する形で臨時編成部隊として発足した海軍陸戦隊でも村田銃の登場までスナイドル銃や本銃が併用されたという。
日本では前述のピーボディ・マルティニ銃と共にマルチニーヘンリー銃またはヘンリーマルチニー銃等と呼ばれていた。
先代:
日本海軍の建軍
日本軍制式小銃
1871-1880
次代:
村田銃
マルティニ・アクションの作動について[編集]
マルティニ・ヘンリー銃の閉鎖部
マルティニ・ヘンリー銃。
A:装填準備。
B:装填完了、および射撃位置
ロックとブリーチはストックからのメタルボルト(A)によって保持されている。ブリーチはブロック(B)により閉鎖されており、ピン(C)が回転するとブロック後方が開放されて通過可能になる。ブロックの終端はケース(D)と共にナックルジョイントを構成するために丸められており、反動をピン(C)よりもある程度多く吸収する。
トリガーガードの下部のレバー(E)は、ケース内部のタンブラー(G)を突きだすとき、ピン(F)を働かせる。このタンブラーはノッチ(H)の中へ移動し、ブロックを押し上げるよう働くもので、レバーの位置に応じて、射撃位置にこれを引き上げるか、これを落下位置に引く。
ブロック(B)は、実包を薬室(J)に装填するのを補助する上面(I)に沿ってへこんでいる。実包を発射するために、ブロックは実包に対して発射機構(K)をセットするよう位置を引き上げる。発射機構は、とがった金属製の撃針と、その周囲をとりまく螺旋形のバネから構成される。その先端は薬室に挿入された実包の電管へ打撃を与えるため、ブロック前面のホールを通過する。レバー(E)が前方へ動かされたとき、タンブラー(G)が回転し、アームの1本が連動する。そしてタンブラーをノッチ(H)が確実にロックするまで、スプリングが後退する。さらにバネは、タンブラーの下部の角に押し込まれるレストピース(L)によって保持される。
発射後、空薬莢はロックによって部分的に引き出される。エキストラクターはピン(M)を中心に回転する。これは2本の垂直の腕(N)を持っており、それらは空薬莢の後端の溝部に押され、元の位置である銃身脇に彫られた2条の筋へと押し戻される。レバーが前に押されるとき、エキストラクターのアームとベントアーム(O)は80°の角度を構成し、下がるブロックによって押しやられる。これにより直立するアームが少し空薬莢を引き抜き、より簡単に、完全な手動排莢が可能となる。
英国の軍用小銃と同様に、マルティニ・ブリーチ・アクションは英国のグリーナー社によって散弾銃に採用された。この単発の「EP」暴動鎮圧用銃は、旧英領の植民地では1970年代まで運用された。 グリーナー「GP」散弾銃もまたマルティニ・アクションを採用し、手軽に使える銃として20世紀中頃まで愛用された。マルティニ・アクションはBSA社も採用した。最近年の銃としては、BSA社のパーカー・ヘイルは彼らの手になる小口径射撃用ライフル「スモール・アクション・マルティニ」を1955年まで生産した。
関連項目[編集]
ビラ銃: 人力作動の機関銃。マルティニ・ヘンリー銃と同じく.577/450実包を装填する。
マルティニ・エンフィールド銃: マルティニ・ヘンリー銃の.303口径の派生型。
マルティニ・カデット銃: カデットライフル射撃用銃。
小銃・自動小銃等一覧
脚注[編集]
1.^ http://www.dave-cushman.net/shot/greenerpolice.html
2.^ http://www.cybershooters.org/Royal%20Armoury/Greener.JPG
3.^ M1874 Turkish Peabody-Martini: (types "A" and "B")
4.^ "The Turkish Connection: The Saga of the Peabody-Martini Rifle" by William O. Achtermeier. originally published in Man At Arms Magazine, Volume 1, Number 2, pp. 12-21, 55-57, March/April 1979
5.^ [www.water.sannet.ne.jp/kazuya-ai/27/rifle-gun.html 幕末の銃器]
6.^ 第玖章 設定資料集 9-3-2 兵士 - TRPG『維新の嵐』
Military Heritage did a feature on the Martini-Henry breach-loading rifle (Peter Suciu, Military Heritage, August 2005, Volume 7, No. 1, pp. 24 to 27), ISSN 1524-8666.
Small Arms Identification Series No 15: .450 & .303 Martini Rifles And Carbines (Ian Skennerton, Arms & Militaria Press) ISBN 0949749443.
Encyclopedia Britannica, "Gunmaking", 1905 edition
Official Report of the Calcutta International Exhibition, 1883-84, Military Exhibits

2014年04月06日
ウィンチェスター モデル1897
ウィンチェスターM1897
移動: 案内、 検索
ウィンチェスター モデル1897
ウィンチェスター モデル1897(フィールド)
種類

ポンプアクション方式散弾銃
原開発国
アメリカ合衆国
運用史
配備先
アメリカ陸軍, アメリカ海軍, アメリカ海兵隊など
関連戦争・紛争
米比戦争, 第一次世界大戦, 第二次世界大戦, 朝鮮戦争, ベトナム戦争
開発史
開発者
ジョン・ブローニング
製造業者
ウィンチェスター・リピーティングアームズ
製造期間
1897年 – 1957年
製造数
1,024,700
諸元
重量
8 lb (3.6 kg)
全長
391⁄4 in (1,000 mm)
銃身長
20 in (510 mm)
--------------------------------------------------------------------------------
口径
12ゲージ
作動方式
ポンプアクション
有効射程
20 m
装填方式
チューブ型着脱式5発弾倉
ウィンチェスターM1897(Winchester Model 1897)、あるいはモデル97(Model 97)、M97、トレンチガン(Trench Gun)とは、アメリカで開発されたポンプアクション式散弾銃である。外装式のハンマーとチューブ型弾倉を備える。ウィンチェスター・リピーティングアームズが製造しており、1897年から1957年までの生産数は1,000,000丁を超えたという。M1897はかつてジョン・ブローニング技師が設計したウィンチェスターM1893に改良を加えたものである。銃身長や口径ごとにいくつかの派生型が設計された。標準的なモデルは12ゲージ30インチ銃身型と16ゲージ28インチ銃身型であった。特注の場合、銃身長は20インチから36インチまでの幅で選択することができたという。設計以来、アメリカの軍隊、警察、ハンター等によって広く使用された[1][2][2]。
目次
[非表示] 1 歴史 1.1 M1893からの改善点
2 概要 2.1 主なM1897のグレードの一覧
2.2 価格
3 軍用散弾銃として
4 第一次世界大戦での抗議について 4.1 ドイツ側の反応
5 その他の使用
6 脚注
7 参考文献
8 外部リンク
歴史[編集]
M1897を設計したのは著名な銃器設計者のジョン・ブローニング技師である。1897年11月、当初は12ゲージのソリッドフレームモデルとしてウィンチェスター社の商品一覧に掲載された。その後、1898年10月には12ゲージのテイクダウン型が、1900年2月には16ゲージのテイクダウン型が発表された[3]。元々、M1897はよりタフで頑丈なM1893の改良型として設計されていた。M1893に比べて機関部の厚みが増しており、当時は一般的でなかった無煙火薬弾の使用が可能になっていた。M1897は散弾銃としては初めてテイクダウン、すなわち銃身の分離を可能とした。これはレミントンM870やモスバーグM500など、今日の散弾銃では基本的な構造となった。現在では「M97はアメリカ市場で最も人気のある散弾銃となっただけではなく大量に輸出され、また散弾銃や他の銃器の標準を確立した」と評価されている[2]。生産は1897年から1957年までの60年間続いた。その後、ウィンチェスターM1912やレミントンM870のようにより先進的なハンマー内蔵型散弾銃が開発されると、M1897は徐々にそれらに置換されていった[4]。しかし、現在でもM1897は主に民間市場で広く流通している。
M1893からの改善点[編集]
M1897では、M1893で指摘されていた多くの欠点が改善されていた[3]。
フレームが強化され、12ゲージ弾のうち2・3/4インチ弾および2・5/8インチ弾が使用できるようになった[3]。
フレーム上部が覆われ、排莢が側面から行われるようになった[3]。これはフレームの強度に寄与するだけでなく、2・3/4インチ弾を使用する際に起きうる弾詰まりの危険性を低下させた[5]。
スライドハンドルをわずかに前進させてアクションスライドロックを解除するまで発砲が出来ないようになっている。射撃時には銃の反動がスライドハンドルをわずかに前進させることでアクションスライドロックを解除しており、素早く射撃が行える。装填後最初の射撃など、反動がない場合には手動でアクションスライドロックを解除する必要がある[3]。
稼働するシェルのガイド部は、装填時に銃を傾けてもシェルが落ちないようにキャリアブロックの右側に設けられた[3]。
銃床が延長され、ドロップ寸も小さくなった[3]。
完全に新たな機構として設けられたスライドロックは、一種の安全装置として設計された。この機構は実際に射撃を行うまで暴発などの問題の発生を防止する。スライドロックによって、ボルトが確実に閉鎖された上で撃針が十分に前進するまで、撃針が雷管に触れることを防ぐことができる[6]。また、射撃を直前で中止した場合にもスリーブが動作することを防止し、より安全性を高めている[7]。
概要[編集]
M1897の機関部を開放した様子。特徴的な長いスライドが露出している
ウィンチェスターM1897はウィンチェスターM1893の設計に改良を加えたもので、いずれもジョン・ブローニングによる設計である。M1997は外装式ハンマーを備えるポンプアクション式散弾銃と分類されているが、1つの特徴としては引き金とハンマーを繋ぐディスコネクターが存在しないので、いわゆるスラムファイア(英語版)(slam fire, 意図的な暴発による速射)が可能である点が挙げられる。つまり、一度射撃した後に引き金を引いたままにしておくと、スライドハンドルを前後に動作させるだけで装填と共にハンマーが動作するので連続した射撃が行えるのである[8]。M1897は長い製造期間を通じて、銃身長や口径などが異なる様々なグレードで生産された。標準的な16ゲージ型は28インチの銃身長で、また標準的な12ゲージ型は30インチの銃身長である。特注の場合は最短20インチ、最長36インチの銃身までの注文が受け付けられていた。標準的な口径は12ゲージと16ゲージの2種類である.[8]。使用するシェルは2・3/4インチか2・5/8インチでなければならない[3]。標準的なM1897は5発装填のチューブ型弾倉を備え、薬室を含むと6発の装填が可能であった。ただし、いくつかのグレードでは弾倉のサイズも異なっている[9]。M1897の機関部が動作する時、フォアエンドの動作に伴ってスライドが機関部から飛び出し、排莢とハンマーのコッキングを同時に行う。
なお、様々な銃器のコピーやレプリカを設計・製造していることで知られる中国北方工業公司(ノリンコ)では、現在でもM1897のレプリカを製造している。ノリンコ製M1897の製品名はYL-1897で、ライオットガン型とトレンチガン型の2種類が販売されている。YL-1897は外見だけではなく内部機構も含めてほとんど完全にM1897のコピーを達成しているが、表面の仕上げなどはオリジナルに劣るとされている[1]。
オリジナルのM1897トレンチガン(上)とノリンコM97Wライオットガン(下)
主なM1897のグレードの一覧[編集]
M1897の各種グレード毎の比較[10]
グレード名
口径(ゲージ)
銃身長(インチ)
生産期間
備考
スタンダード(Standard)
12,16
30,28
1897-1957[11]
平坦なウォールナット製銃床と鉄製肩当てを備える。
トラップ(Trap)
12,16
30,28
1897-1931[11]
刻み加工が施されたファンシーウォールナット製銃床を備える。
ピジョン(Pigeon)
12,16
28
1897-1939[11]
トラップと同じ銃床に加え、機関部に装飾が施されている
トーナメント(Tournament)
12
30
1910-1931[12]
銃床の材質が選べる。光の反射を抑える為、機関部上部に艶消し塗装が施されている。
ブラッシュ(Brush)
12,16
26
1897-1931[11]
短弾倉、平坦なウォールナット製銃床を備える。ソリッドフレーム型。
ブラッシュ・テイクダウン(Brush Takedown)
12,16
26
1897-1931[11]
同上。ただしテイクダウン型。
ライオット(Riot)
12
20
1898-1935[11]
平坦なウォールナット製銃床を備える。ソリッドフレーム型とテイクダウン型が選択できる。
トレンチ(Trench)
12
20
1917-1945[13]
ライオット型の仕様に加え、放熱板や着剣装置、負革の吊環が追加されている。
価格[編集]
M1897がはじめてカタログに載った時、その価格は各グレードがどの機能・装備を備えるかによって算出されていた。例えば何ら装飾のない散弾銃であれば25ドル、機関部に彫刻などの複雑な装飾を施す場合は100ドル程度が価格の目安になったという[8]。M1897のグレードで高価だったグレードはスタンダード、トラップ、ピジョン、トーナメントの4種類である。これらのグレードは多くの場合、機関部への装飾や銃床への刻み加工などが施されていたのである[4][14]。その一方、ブラッシュ、ブラッシュ・テイクダウン、ライオット、トレンチの4種類には一切の装飾が施されず、木材も安価なものだけが使用された[4][14]。これらは軍や警察などによる過酷な使用を想定しており、高い確率で破損することが予想された為である。また、重量のある高級木材もこれらのグレードでは好まれなかった。装飾や高級材料、表面仕上げなどを省略したことに加え、主な顧客であった軍・警察が一度の注文で大量に購入することもあり、これらのグレードは低い価格を維持したのである[4][14]。
軍用散弾銃として[編集]
M1897トレンチガンとM1917銃剣
M1897は第一次世界大戦前からポピュラーな散弾銃であったが、戦争が始まるとM1897単体の売上が一気に上昇した。アメリカ軍は第一次世界大戦に参戦した段階で、開戦以降の3年間に関する調査および検討の結果として、塹壕戦では至近距離で強大な火力を発揮する装備が有効であろうという結論にたどり着いていた[1]。M1897のトレンチグレード、すなわちトレンチガンは軍の要望に応えうるものとして開発された。トレンチガンは速射時の過熱を想定した放熱板を備え[15]、M1917銃剣を取り付けられる着剣装置を備えていた[1]。
M1897トレンチガンのM1917銃剣用着剣装置
取り回しの良い20インチの短銃身を備えたトレンチガンは、狭い塹壕の中では大きな脅威となった。これらのトレンチガンは00Bのバックショット弾(8.4mm弾x9粒)を使用した[2]。また、いくつかの特殊な用途での使用も試みられた。例えばトラップ射撃に自信のある兵士は、敵兵が投げ込んできた手榴弾を自軍塹壕に落ちる前にトレンチガンで撃ち落とし、爆破する役割を与えられていた[2]。
多くの近代的ポンプアクション式散弾銃と異なり、M1897はディスコネクターを欠いていた為にスラムファイアが可能であった。これは6発の装填数と共に近接戦闘における大きな強みとなり、将兵らはM1897によるスラムファイアをトレンチスイーパーと俗称した。ドイツ帝国政府はこれら軍用散弾銃が非人道的火器であり使用の禁止を定めるべきとの抗議を行なっている。ただし、この抗議はのちに却下されている[16]。第二次世界大戦でも少数がアメリカ陸軍およびアメリカ海兵隊によって使用されたが、多くはハンマー内蔵型で同じくスラムファイアが可能なウィンチェスターM1912に更新された。
その他、施設内の警備や捕虜の護送、後方警備、襲撃、市街戦、ジャングル戦などの特殊な任務でもこれらの散弾銃は使用された[16]。
第一次世界大戦での抗議について[編集]
M1897は第一次世界大戦中のアメリカ兵によって盛んに使用されたが、まもなくしてドイツ側から公的な抗議が行われた。1918年9月19日、ドイツ帝国政府は散弾銃が戦時国際法に抵触するとして、アメリカの散弾銃使用に対する外交的抗議を行なった[16]。ドイツによる抗議は、すなわち「散弾銃はハーグ陸戦条約における『不必要な苦痛を与える兵器』に該当すると推定され[2] 、これは戦闘における散弾銃の使用の合法性を問う唯一の機会である[16]」との内容であった。しかし、アメリカ陸軍法務部とロバート・ランシング国務長官はハーグ陸戦条約に関する協議を重ね、速やかにドイツ側の抗議を却下した[16]。なお、フランスやイギリスもまた第一次世界大戦中に塹壕戦向け装備として散弾銃の使用を検討している。ただし、英仏では高威力な散弾の開発を行なっておらず、また主に普及していたのは速射性に劣る二銃身型散弾銃であったことから制式採用には至っていない[16]。
ドイツ側の反応[編集]
抗議の却下に対するドイツ側の動揺は大きく、彼らはこれを戦時国際法に反する不当な扱いであると受け止めた。抗議が却下された直後、ドイツは散弾銃で武装していたことが明らかな米軍捕虜全員を厳罰に処す旨を発表した[2]。この発表を受けた直後、アメリカ側でもドイツ兵捕虜に対する報復が行われたという[17]。
その他の使用[編集]
第一次世界大戦の後、短銃身型のM1897はウィンチェスター社からライオットガンとして販売された。これらは全米の警察署にて配備されたほか、アメリカン・エキスプレス社のメッセンジャーが自衛用に携行したことも知られている[2]。ライオットガンはトレンチガンと異なり、着剣装置や放熱板、負革の吊環が無かった[1][8]。
脚注[編集]
1.^ a b c d e Davis (2006)
2.^ a b c d e f g h Williamson (1952) p. 158.
3.^ a b c d e f g h Henshaw (1993) p. 49.
4.^ a b c d Miller (2005) p. 694, Miller.
5.^ Farrow (1904) p. 335
6.^ Smith (1911) p. 5
7.^ Smith (1911) p. 4
8.^ a b c d Hager (2005)
9.^ Farrow (1904) p. 337
10.^ Wilson (2008) pp.214-219
11.^ a b c d e f Miller (2006) p. 98
12.^ Miller (2006) p. 99
13.^ Wilson(2008). p.220
14.^ a b c Carmichel (1986) p. 78-79
15.^ Lewis (2007) p. 162
16.^ a b c d e f Parks (1997)
17.^ Williamson (1952) p. 159.
参考文献[編集]
Boorman, Dean K. (2001). History of Winchester Firearms. The Lyons Press. ISBN 978-1-58574-307-0.
Carmichel, Jim (1986). Guns and Shooting, 1986. Times Mirror Magazines, Incorporated, Book Division. pp. 78–79. ISBN 978-0-943822-58-7.
Lewis, Jack; Robert K. Campbell and David Steele (2007). The Gun Digest Book of Assault Weapons (7th ed.). Krause Publications. p. 162 2010年4月20日閲覧。.
Miller, David (2006). The History of Browning Firearms. First Lyons Press Edition. pp. 98–99 2010年4月19日閲覧。.
Miller, David (2005). The Illustrated Directory of Guns. Collin Gower Enterprises Ltd.. p. 694. ISBN 0-681-06685-7.
Davis, Phil (2006年8月7日). “Sangamon County Rifle Association Winchester Model 1897”. 2010年1月23日閲覧。
Farrow, Edward S. (1904). American Small Arms. New York: The Bradford Company. pp. 335–337 2010年4月20日閲覧。.
Hager, Michael C. (2005年1月25日). “The Winchester Collector A Timeline History of Winchester”. 2010年1月20日閲覧。
Hager, Michael C. (2005年1月9日). “The Winchester Collector Model 1897 Shotguns”. 2010年1月23日閲覧。
Henshaw, Thomas. The History of Winchester Firearms (6th ed.). Winchester Press, 1993. pp. 48–50.
Parks, W. Hays (1997年). “October 1997 The Army Lawyer”. 2010年4月10日閲覧。
Smith, Morris F. (1911年12月14日). “United States Patent Office”. PIBEABM Patent Search. pp. 4–5. 2010年3月20日閲覧。
Williamson, Harold F. (1952). Winchester (1st ed.). Washington DC: Combat Forces. pp. 158–159.
Wilson, R. L. (2008). Winchester: An American Legend. New York: Book Sales, Inc. pp. 214–220. ISBN 978-0-7858-1893-9.
移動: 案内、 検索
ウィンチェスター モデル1897
ウィンチェスター モデル1897(フィールド)
種類

ポンプアクション方式散弾銃
原開発国
アメリカ合衆国
運用史
配備先
アメリカ陸軍, アメリカ海軍, アメリカ海兵隊など
関連戦争・紛争
米比戦争, 第一次世界大戦, 第二次世界大戦, 朝鮮戦争, ベトナム戦争
開発史
開発者
ジョン・ブローニング
製造業者
ウィンチェスター・リピーティングアームズ
製造期間
1897年 – 1957年
製造数
1,024,700
諸元
重量
8 lb (3.6 kg)
全長
391⁄4 in (1,000 mm)
銃身長
20 in (510 mm)
--------------------------------------------------------------------------------
口径
12ゲージ
作動方式
ポンプアクション
有効射程
20 m
装填方式
チューブ型着脱式5発弾倉
ウィンチェスターM1897(Winchester Model 1897)、あるいはモデル97(Model 97)、M97、トレンチガン(Trench Gun)とは、アメリカで開発されたポンプアクション式散弾銃である。外装式のハンマーとチューブ型弾倉を備える。ウィンチェスター・リピーティングアームズが製造しており、1897年から1957年までの生産数は1,000,000丁を超えたという。M1897はかつてジョン・ブローニング技師が設計したウィンチェスターM1893に改良を加えたものである。銃身長や口径ごとにいくつかの派生型が設計された。標準的なモデルは12ゲージ30インチ銃身型と16ゲージ28インチ銃身型であった。特注の場合、銃身長は20インチから36インチまでの幅で選択することができたという。設計以来、アメリカの軍隊、警察、ハンター等によって広く使用された[1][2][2]。
目次
[非表示] 1 歴史 1.1 M1893からの改善点
2 概要 2.1 主なM1897のグレードの一覧
2.2 価格
3 軍用散弾銃として
4 第一次世界大戦での抗議について 4.1 ドイツ側の反応
5 その他の使用
6 脚注
7 参考文献
8 外部リンク
歴史[編集]
M1897を設計したのは著名な銃器設計者のジョン・ブローニング技師である。1897年11月、当初は12ゲージのソリッドフレームモデルとしてウィンチェスター社の商品一覧に掲載された。その後、1898年10月には12ゲージのテイクダウン型が、1900年2月には16ゲージのテイクダウン型が発表された[3]。元々、M1897はよりタフで頑丈なM1893の改良型として設計されていた。M1893に比べて機関部の厚みが増しており、当時は一般的でなかった無煙火薬弾の使用が可能になっていた。M1897は散弾銃としては初めてテイクダウン、すなわち銃身の分離を可能とした。これはレミントンM870やモスバーグM500など、今日の散弾銃では基本的な構造となった。現在では「M97はアメリカ市場で最も人気のある散弾銃となっただけではなく大量に輸出され、また散弾銃や他の銃器の標準を確立した」と評価されている[2]。生産は1897年から1957年までの60年間続いた。その後、ウィンチェスターM1912やレミントンM870のようにより先進的なハンマー内蔵型散弾銃が開発されると、M1897は徐々にそれらに置換されていった[4]。しかし、現在でもM1897は主に民間市場で広く流通している。
M1893からの改善点[編集]
M1897では、M1893で指摘されていた多くの欠点が改善されていた[3]。
フレームが強化され、12ゲージ弾のうち2・3/4インチ弾および2・5/8インチ弾が使用できるようになった[3]。
フレーム上部が覆われ、排莢が側面から行われるようになった[3]。これはフレームの強度に寄与するだけでなく、2・3/4インチ弾を使用する際に起きうる弾詰まりの危険性を低下させた[5]。
スライドハンドルをわずかに前進させてアクションスライドロックを解除するまで発砲が出来ないようになっている。射撃時には銃の反動がスライドハンドルをわずかに前進させることでアクションスライドロックを解除しており、素早く射撃が行える。装填後最初の射撃など、反動がない場合には手動でアクションスライドロックを解除する必要がある[3]。
稼働するシェルのガイド部は、装填時に銃を傾けてもシェルが落ちないようにキャリアブロックの右側に設けられた[3]。
銃床が延長され、ドロップ寸も小さくなった[3]。
完全に新たな機構として設けられたスライドロックは、一種の安全装置として設計された。この機構は実際に射撃を行うまで暴発などの問題の発生を防止する。スライドロックによって、ボルトが確実に閉鎖された上で撃針が十分に前進するまで、撃針が雷管に触れることを防ぐことができる[6]。また、射撃を直前で中止した場合にもスリーブが動作することを防止し、より安全性を高めている[7]。
概要[編集]
M1897の機関部を開放した様子。特徴的な長いスライドが露出している
ウィンチェスターM1897はウィンチェスターM1893の設計に改良を加えたもので、いずれもジョン・ブローニングによる設計である。M1997は外装式ハンマーを備えるポンプアクション式散弾銃と分類されているが、1つの特徴としては引き金とハンマーを繋ぐディスコネクターが存在しないので、いわゆるスラムファイア(英語版)(slam fire, 意図的な暴発による速射)が可能である点が挙げられる。つまり、一度射撃した後に引き金を引いたままにしておくと、スライドハンドルを前後に動作させるだけで装填と共にハンマーが動作するので連続した射撃が行えるのである[8]。M1897は長い製造期間を通じて、銃身長や口径などが異なる様々なグレードで生産された。標準的な16ゲージ型は28インチの銃身長で、また標準的な12ゲージ型は30インチの銃身長である。特注の場合は最短20インチ、最長36インチの銃身までの注文が受け付けられていた。標準的な口径は12ゲージと16ゲージの2種類である.[8]。使用するシェルは2・3/4インチか2・5/8インチでなければならない[3]。標準的なM1897は5発装填のチューブ型弾倉を備え、薬室を含むと6発の装填が可能であった。ただし、いくつかのグレードでは弾倉のサイズも異なっている[9]。M1897の機関部が動作する時、フォアエンドの動作に伴ってスライドが機関部から飛び出し、排莢とハンマーのコッキングを同時に行う。
なお、様々な銃器のコピーやレプリカを設計・製造していることで知られる中国北方工業公司(ノリンコ)では、現在でもM1897のレプリカを製造している。ノリンコ製M1897の製品名はYL-1897で、ライオットガン型とトレンチガン型の2種類が販売されている。YL-1897は外見だけではなく内部機構も含めてほとんど完全にM1897のコピーを達成しているが、表面の仕上げなどはオリジナルに劣るとされている[1]。
オリジナルのM1897トレンチガン(上)とノリンコM97Wライオットガン(下)
主なM1897のグレードの一覧[編集]
M1897の各種グレード毎の比較[10]
グレード名
口径(ゲージ)
銃身長(インチ)
生産期間
備考
スタンダード(Standard)
12,16
30,28
1897-1957[11]
平坦なウォールナット製銃床と鉄製肩当てを備える。
トラップ(Trap)
12,16
30,28
1897-1931[11]
刻み加工が施されたファンシーウォールナット製銃床を備える。
ピジョン(Pigeon)
12,16
28
1897-1939[11]
トラップと同じ銃床に加え、機関部に装飾が施されている
トーナメント(Tournament)
12
30
1910-1931[12]
銃床の材質が選べる。光の反射を抑える為、機関部上部に艶消し塗装が施されている。
ブラッシュ(Brush)
12,16
26
1897-1931[11]
短弾倉、平坦なウォールナット製銃床を備える。ソリッドフレーム型。
ブラッシュ・テイクダウン(Brush Takedown)
12,16
26
1897-1931[11]
同上。ただしテイクダウン型。
ライオット(Riot)
12
20
1898-1935[11]
平坦なウォールナット製銃床を備える。ソリッドフレーム型とテイクダウン型が選択できる。
トレンチ(Trench)
12
20
1917-1945[13]
ライオット型の仕様に加え、放熱板や着剣装置、負革の吊環が追加されている。
価格[編集]
M1897がはじめてカタログに載った時、その価格は各グレードがどの機能・装備を備えるかによって算出されていた。例えば何ら装飾のない散弾銃であれば25ドル、機関部に彫刻などの複雑な装飾を施す場合は100ドル程度が価格の目安になったという[8]。M1897のグレードで高価だったグレードはスタンダード、トラップ、ピジョン、トーナメントの4種類である。これらのグレードは多くの場合、機関部への装飾や銃床への刻み加工などが施されていたのである[4][14]。その一方、ブラッシュ、ブラッシュ・テイクダウン、ライオット、トレンチの4種類には一切の装飾が施されず、木材も安価なものだけが使用された[4][14]。これらは軍や警察などによる過酷な使用を想定しており、高い確率で破損することが予想された為である。また、重量のある高級木材もこれらのグレードでは好まれなかった。装飾や高級材料、表面仕上げなどを省略したことに加え、主な顧客であった軍・警察が一度の注文で大量に購入することもあり、これらのグレードは低い価格を維持したのである[4][14]。
軍用散弾銃として[編集]
M1897トレンチガンとM1917銃剣
M1897は第一次世界大戦前からポピュラーな散弾銃であったが、戦争が始まるとM1897単体の売上が一気に上昇した。アメリカ軍は第一次世界大戦に参戦した段階で、開戦以降の3年間に関する調査および検討の結果として、塹壕戦では至近距離で強大な火力を発揮する装備が有効であろうという結論にたどり着いていた[1]。M1897のトレンチグレード、すなわちトレンチガンは軍の要望に応えうるものとして開発された。トレンチガンは速射時の過熱を想定した放熱板を備え[15]、M1917銃剣を取り付けられる着剣装置を備えていた[1]。
M1897トレンチガンのM1917銃剣用着剣装置
取り回しの良い20インチの短銃身を備えたトレンチガンは、狭い塹壕の中では大きな脅威となった。これらのトレンチガンは00Bのバックショット弾(8.4mm弾x9粒)を使用した[2]。また、いくつかの特殊な用途での使用も試みられた。例えばトラップ射撃に自信のある兵士は、敵兵が投げ込んできた手榴弾を自軍塹壕に落ちる前にトレンチガンで撃ち落とし、爆破する役割を与えられていた[2]。
多くの近代的ポンプアクション式散弾銃と異なり、M1897はディスコネクターを欠いていた為にスラムファイアが可能であった。これは6発の装填数と共に近接戦闘における大きな強みとなり、将兵らはM1897によるスラムファイアをトレンチスイーパーと俗称した。ドイツ帝国政府はこれら軍用散弾銃が非人道的火器であり使用の禁止を定めるべきとの抗議を行なっている。ただし、この抗議はのちに却下されている[16]。第二次世界大戦でも少数がアメリカ陸軍およびアメリカ海兵隊によって使用されたが、多くはハンマー内蔵型で同じくスラムファイアが可能なウィンチェスターM1912に更新された。
その他、施設内の警備や捕虜の護送、後方警備、襲撃、市街戦、ジャングル戦などの特殊な任務でもこれらの散弾銃は使用された[16]。
第一次世界大戦での抗議について[編集]
M1897は第一次世界大戦中のアメリカ兵によって盛んに使用されたが、まもなくしてドイツ側から公的な抗議が行われた。1918年9月19日、ドイツ帝国政府は散弾銃が戦時国際法に抵触するとして、アメリカの散弾銃使用に対する外交的抗議を行なった[16]。ドイツによる抗議は、すなわち「散弾銃はハーグ陸戦条約における『不必要な苦痛を与える兵器』に該当すると推定され[2] 、これは戦闘における散弾銃の使用の合法性を問う唯一の機会である[16]」との内容であった。しかし、アメリカ陸軍法務部とロバート・ランシング国務長官はハーグ陸戦条約に関する協議を重ね、速やかにドイツ側の抗議を却下した[16]。なお、フランスやイギリスもまた第一次世界大戦中に塹壕戦向け装備として散弾銃の使用を検討している。ただし、英仏では高威力な散弾の開発を行なっておらず、また主に普及していたのは速射性に劣る二銃身型散弾銃であったことから制式採用には至っていない[16]。
ドイツ側の反応[編集]
抗議の却下に対するドイツ側の動揺は大きく、彼らはこれを戦時国際法に反する不当な扱いであると受け止めた。抗議が却下された直後、ドイツは散弾銃で武装していたことが明らかな米軍捕虜全員を厳罰に処す旨を発表した[2]。この発表を受けた直後、アメリカ側でもドイツ兵捕虜に対する報復が行われたという[17]。
その他の使用[編集]
第一次世界大戦の後、短銃身型のM1897はウィンチェスター社からライオットガンとして販売された。これらは全米の警察署にて配備されたほか、アメリカン・エキスプレス社のメッセンジャーが自衛用に携行したことも知られている[2]。ライオットガンはトレンチガンと異なり、着剣装置や放熱板、負革の吊環が無かった[1][8]。
脚注[編集]
1.^ a b c d e Davis (2006)
2.^ a b c d e f g h Williamson (1952) p. 158.
3.^ a b c d e f g h Henshaw (1993) p. 49.
4.^ a b c d Miller (2005) p. 694, Miller.
5.^ Farrow (1904) p. 335
6.^ Smith (1911) p. 5
7.^ Smith (1911) p. 4
8.^ a b c d Hager (2005)
9.^ Farrow (1904) p. 337
10.^ Wilson (2008) pp.214-219
11.^ a b c d e f Miller (2006) p. 98
12.^ Miller (2006) p. 99
13.^ Wilson(2008). p.220
14.^ a b c Carmichel (1986) p. 78-79
15.^ Lewis (2007) p. 162
16.^ a b c d e f Parks (1997)
17.^ Williamson (1952) p. 159.
参考文献[編集]
Boorman, Dean K. (2001). History of Winchester Firearms. The Lyons Press. ISBN 978-1-58574-307-0.
Carmichel, Jim (1986). Guns and Shooting, 1986. Times Mirror Magazines, Incorporated, Book Division. pp. 78–79. ISBN 978-0-943822-58-7.
Lewis, Jack; Robert K. Campbell and David Steele (2007). The Gun Digest Book of Assault Weapons (7th ed.). Krause Publications. p. 162 2010年4月20日閲覧。.
Miller, David (2006). The History of Browning Firearms. First Lyons Press Edition. pp. 98–99 2010年4月19日閲覧。.
Miller, David (2005). The Illustrated Directory of Guns. Collin Gower Enterprises Ltd.. p. 694. ISBN 0-681-06685-7.
Davis, Phil (2006年8月7日). “Sangamon County Rifle Association Winchester Model 1897”. 2010年1月23日閲覧。
Farrow, Edward S. (1904). American Small Arms. New York: The Bradford Company. pp. 335–337 2010年4月20日閲覧。.
Hager, Michael C. (2005年1月25日). “The Winchester Collector A Timeline History of Winchester”. 2010年1月20日閲覧。
Hager, Michael C. (2005年1月9日). “The Winchester Collector Model 1897 Shotguns”. 2010年1月23日閲覧。
Henshaw, Thomas. The History of Winchester Firearms (6th ed.). Winchester Press, 1993. pp. 48–50.
Parks, W. Hays (1997年). “October 1997 The Army Lawyer”. 2010年4月10日閲覧。
Smith, Morris F. (1911年12月14日). “United States Patent Office”. PIBEABM Patent Search. pp. 4–5. 2010年3月20日閲覧。
Williamson, Harold F. (1952). Winchester (1st ed.). Washington DC: Combat Forces. pp. 158–159.
Wilson, R. L. (2008). Winchester: An American Legend. New York: Book Sales, Inc. pp. 214–220. ISBN 978-0-7858-1893-9.
2014年04月06日
トンプソン・サブマシンガン
トンプソン・サブマシンガン
移動: 案内、 検索
「トミー・ガン」はこの項目へ転送されています。ザ・クラッシュの楽曲については「トミー・ガン (曲)」をご覧ください。
トンプソン・サブマシンガン
戦時中に生産されたトンプソン M1928A1
種類
短機関銃
原開発国
アメリカ合衆国
運用史
配備期間
1938年–1971年
(アメリカ陸軍)
配備先
米国はじめ各国
関連戦争・紛争
アイルランド独立戦争
アイルランド内戦
バナナ戦争
日中戦争
第二次世界大戦 [1]
朝鮮戦争 [1]
国共内戦
第一次中東戦争
第一次インドシナ戦争
ベトナム戦争 [1]
ボスニア紛争
開発史
開発者
ジョン・T・トンプソン
開発期間
1917年–1920年
製造業者
Auto-Ordnance Company
(オリジナル)
バーミンガム・スモール・アームズ
コルト
Savage Arms
製造期間
1921年–現在
製造数
約1,700,000丁
派生型
Persuader & Annihilator 試作機,
M1921, M1921AC, M1921A,
M1927, M1928, M1928A1,
M1, M1A1
諸元
重量
10.8lb(4.9kg)空の場合(M1928A1)
10.6lb(4.8kg)空の場合(M1A1)
全長
33.5 in (851 ミリメートル)(M1928A1)
32 in (813 ミリメートル)(M1A1/M1)
銃身 10.5 in (267 ミリメートル)
銃身にオプションでCutts Compensatorが付く 12 in (305 ミリメートル)
--------------------------------------------------------------------------------
弾丸
.45ACP弾(11.43×23mm)
作動方式
シンプル・ブローバック方式
ブリッシュ・ロック方式
発射速度
600–1200発/分
(各モデルにより異なる)
初速
285 m/s (935 ft/s)
有効射程
50メートル (160 ft)
装填方式
20発 箱型弾倉
30発 箱型弾倉
50発 ドラムマガジン
100発 ドラムマガジン
(M1とM1A1はドラムマガジンを装着出来ない)
トンプソン・サブマシンガン(Thompson submachine gun)は、アメリカで開発された短機関銃。トムソン銃、シカゴ・タイプライターといった通称を持つことで知られるが、本項ではトミーガンに統一して表記する。
トミーガンは、禁酒法時代のアメリカ合衆国内において警察とギャングの双方に用いられたことで有名になった。1919年から累計170万挺以上が生産され、今日でも製造が続けられている長命な製品である。頑丈な構造を持ち、耐久性と信頼性に優れ、5kg近い重量のおかげでフルオート射撃を制御しやすい特性から、世界各国で広く用いられた。
目次
[非表示] 1 構造
2 開発
3 バリエーション 3.1 M1919
3.2 M1921
3.3 M1923
3.4 M1927
3.5 M1928
3.6 M1928A1
3.7 M1/M1A1
4 普及 4.1 アメリカ
4.2 日本
4.3 中国
5 登場作品 5.1 テレビ・映画
5.2 アニメ
5.3 漫画
5.4 小説
5.5 ゲーム
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
構造[編集]
トミーガンを特徴付けているのは、主要部品の多くが角を丸めた直角で構成されている点で、円形を基本に構成される事が多かった欧州の製品とは一線を画したデザインとなっている。これはトミーガンは鋼鉄ブロックからの切削加工で製造され、切削作業の大部分が平フライス加工だけで行えるよう考慮したためである。この結果、大規模な専用生産施設を持たなくても、外注工場の利用が容易で効率よく製作できるメリットがあり、中国やベトナムなど工業水準の低い諸国でも容易にコピー生産が可能となった。
トミーガンは上下2つのレシーバ(機関部)によって構成されており、銃身は上部レシーバ先端にネジで固定され、弾倉が接触する部分はドラム型弾倉を装着するため大きく切り欠かれた形状となっているほか、内部はフライス加工によって大きくえぐられ、この空洞内をボルトが前後する。
弾倉は上部まで露出しているため、野戦では泥などが付着しやすいが、逆に拭い去る事も簡単な構造となっている。箱型弾倉を装填する際には下側から、ドラム型弾倉を装填する際には横からスライドさせて装着し、どちらもレール溝によって支持されている。M1/M1A1(後述)では横溝が省略されてドラム型弾倉が使用できないが、上部レシーバの切り欠きはそのままなので、後から横溝を刻むだけで使用できるようになる。
下部レシーバは複雑な形状ながら、機能的には上部レシーバの下部を塞ぎ、トリガーメカを保持するだけの単純な構造である。上下のレシーバはレール溝によって嵌合し、分解する際に上部レシーバ後端にあるストッパを押し込んで下部レシーバを引き抜く形で分離できる。
セミ/フルオートを切り替えるセレクターと、セフティ(安全装置)は別々のレバー状部品として存在しているが、弾倉を固定しているマガジン・キャッチを含めて、位置は全てグリップ上部左側面にあるため、右利きの射手であれば、グリップから手を離さず全て右手親指で操作する事が可能である。
一般的に「トミーガンは生産性が悪かった」と認識されているが、トミーガンの省力化が図られた1940年代にはM1/M1A1のように、単純な板金曲げ加工とスポット溶接に、バレル・カラーなどの切削部品を組み合わせるだけで、同様の外見構造を強度を落とさず低コストで実現できたため、切削加工を前提とした当時の基準ではことさらに生産性の悪い構造だったとは言えない。しかし第二次世界大戦中には全軍への普及を図るべく、MP40やステン短機関銃などに代表される、より一層と生産性が高い短機関銃が要求され、その結果としてプレス加工主体のM3グリースガンの開発が行われた。
また、携行性をあまり重視しない長く重い銃ではあったが、ちゃんと構えて保持すればその重さが発砲の反動を相殺し、良好な命中精度を発揮した。
開発[編集]
ジョン・T・トンプソン元大佐
1916年、アメリカのジョン・T・トンプソン元陸軍大佐(後に復帰し准将として再度退役する)が設立したオート・オードナンス社において、「塹壕箒」(trench broom)と仮称される自動式小火器の試作が開始された。
この自動式小火器は、塹壕戦で膠着状態となった第一次世界大戦の状況を見て、これを打開できる個人装備の需要予測に基づいて開始され、その動機は純粋に商業的なものだった。
当時の機関銃は巨大かつ重量級の装備であり、軽機関銃といえども兵士が一人で操作できる存在ではなく、機械的な信頼性も低かった。そして機関銃は突撃する兵士に随伴して後方から援護射撃を加える事すら難しかった。しかし、塹壕戦の打開に必要とされていたのは、機関銃で強固に防衛された敵塹壕に対する肉薄および突破であり、これに用いる銃器には兵士が携帯できるサイズ・重量であることやフルオート射撃能力が求められた。
1917年に第一次世界大戦に参戦した米軍でも、塹壕の突破を目的として軍用ショットガンや秘密兵器であるピダーセン・デバイスを量産・装備していた。また、同時期の米国ではジョン・ブローニングによってブローニングM1918自動小銃(BAR)の開発が進められていた他、同時期にはドイツ帝国でも塹壕陣地の突破を任務とする突撃歩兵の為にMP18なる小型機関銃の開発が進められていた。
塹壕戦用小型機関銃
トンプソン大佐が提唱した塹壕箒なる自動式小火器は、1918年に試作されたPersuader(パースエーダー。説得者/言うことを聞かせるものの意) によって初めて具体的な形となった。
Persuaderの給弾方式はベルト給弾式だったが、機関部が砂塵や泥汚れに弱いという欠点があった。そこで、これを箱型弾倉に改めたタイプが1919年に試作され、Annihilator(アナイアレーター。絶滅者/敵を打ち負かすものの意)と名付けられた。
両製品は、ともにブリッシュ・ロック方式と呼ばれる遅延式ブローバック閉鎖機構を持ち、後のトミーガンの基本構成要素を備えていた。
バリエーション[編集]
M1919[編集]
最初の『サブマシンガン』
“Annihilator”が完成する前年に第一次世界大戦は終結していたが、トンプソン大佐は念願の製品化に着手し、精密機器メーカーのWarner & Swasey社が製作を担当した。 [2]
このモデルは後年M1919と呼ばれているが、発売に際して付けられた製品名はThompson submachine gunであり、サブマシンガンの名称が初めて使用された。
サブマシンガンは“小型機関銃”を意味する製品名だったが、後に拳銃弾を使用するフルオート火器を総称する呼称として、世界的に使用されるようになった。
M1919は.45ACP弾、.22LR、.32ACP弾、.38 ACP、9x19mmパラベラム弾など各種の弾薬用に製造され、照星や銃床を持たないなど、デモンストレーション用/テスト用としての色彩が強い製品だった。トミーガンの特徴となった垂直フォアグリップは銃身下部に装着され、安定したフルオート射撃が可能だったが、連射レートは1,000発/分程度と高速だった。
1920年4月に行われた軍の採用テストでは、2,000発の発射に対し動作不良は2回のみ、という好成績を残したが、大戦を終えた米陸軍は軍縮に向かっており、M1919が採用される事はなかった。軍用としての見込みが無くなった事から、トンプソン大佐は販売先を警察に切り替え、40挺ほどがニューヨーク市警察によって購入された。
M1921[編集]
民間市場での成功と知名度の獲得
トンプソン自動小銃(上)とM1921
「強盗が一番恐れる銃」と記された1920年代の広告
M1921は、M1919に改良を加えた量産タイプの製品であり、民間市場向けに「手軽にフルオート射撃を楽しめる“スポーツ用途”の銃」として販売が開始された。
1921年当時の販売価格は20発箱型弾倉付きで$225(現在の価格に換算[3]して$2,600程度)であり、製造はコルト社が担当し、15,000挺ほどが生産された[2]。
富裕層向けの高級玩具としての色彩が強い製品であり、木部は美しく仕上げられ、各部品は高精度な切削加工で製造されていた。 弾倉は20発/30発箱形弾倉のほかに50発用ドラム弾倉が用意され、連射レートは800発/分程度まで落とされていた。
1926年からは銃口部にCuts Compensatorと呼ばれるマズルブレーキの一種がオプションで装着できるようになり、フルオート射撃時のコントロールはより安定した[4]。
なお、最初にM1921の大口顧客となったのは、米国のアイルランド系移民の独立運動支持者達と考えられており、製造番号が1,000番未満の初期生産品が英領アイルランドで発見されている。これらのM1921はIrish Swordと呼ばれ、後のアイルランド内戦では主に反条約派によって使用された[5]。
また、当時頻発していた郵便強盗対策のために、米国郵便公社もM1921を400挺購入した。同公社が購入したM1921は、郵便警護を分担した海兵隊にも供与されたが、海兵隊はこれをバナナ戦争での軍事行動に転用した。
しかし、当時のM1921は民間人(この中にはトミーガンを有名にしたマフィア達も含まれていた)を主な購入者としており、1934年に規制されるまで購入に何らの制約も無く通信販売でも購入できたため、バナナ戦争における交戦相手のサンディーノ軍(ニカラグア)も、海兵隊と同様にM1921を装備していた。
M1923[編集]
強装弾薬の試行
トンプソン大佐が想定していた小型機関銃のコンセプトは小銃弾を使用するものであり、M1921に使用された.45ACP弾(480J)のパワーと、有効射程が50ヤードしかなかったM1921の射程は、軍用として力不足なものだった。
しかし、ブリッシュ・ロック方式の閉鎖機構は、その主要部品に真鍮製のロッキング・ピースを用いており、強烈な腔圧を発生させる当時のフルサイズ小銃弾には不向きな事が判明していたため、.45ACP弾の薬莢長を3mm延長して威力を増大した.45 Remington-Thompson弾(1,590J)が新規に開発され、これを用いるM1923が試作された。
.45 Remington-Thompson弾は.45ACP弾の3倍ものエネルギーを持ち、後に開発された.44 Magnum弾に近いパワーを有し、至近距離で杉板15枚、300ヤードで8枚を貫通したとされる[4]。 .45 Remington-Thompson弾はテストの結果.45ACP弾よりも精度が悪い事が判明し、市販されずに終わった。
M1923はM1921より約10cm銃身が延長され、軍用に適した水平フォアグリップが装着されていたほか、強くなった反動を制御するために連射速度は400発/分程度まで遅延されていた(参考画像) 着剣装置が付けられたタイプや、二脚を付けた軽機関銃タイプも試作されて米軍向けのプレゼンが行われたが、既にBARが採用されていた事もあり、採用には至らなかった。そのスタイルは後の軍用モデルであるM1928A1やM1/M1A1へ継承された。
M1927[編集]
セミオート・バージョン
M1921は当時数少ないフルオート火器だったため、慣れない射手が引き鉄を引き続けて銃口が跳ね上がり、制御不能となって意図せぬ方向を撃ってしまう事故が発生する事があった。このためM1921からフルオート射撃の機能を削除し、セミオート・カービンとした製品が要望され、M1927が製造された。
M1927はM1921を改造して製造されたため、M1921の刻印である“Thompson Submachine Gun”を一部削り取り、“Thompson Semi-Automatic Carbine”と改めて打刻し直されている。
M1927はM1921とほとんど同じ製品であるため、簡単にフルオート射撃の機能を復活させる事ができたが、1934年の連邦法改正によるフルオート火器の所持規制以降も民間人が無許可で購入できるトミーガンとして製造され続けた。ただし、1982年以降、オープンボルト撃発火器は、フルオートへの改造を前提とした火器と見なされるようになったため、現在では所持制限の対象となっている。
また、トミーガン用の100連ドラム弾倉はM1927と同時に販売されるようになった。
M1928[編集]
トンプソンM1928を持つイギリス兵(1940年) 正規軍に採用された軍用モデル
マスコミへの露出でM1921は実態以上に有名となったが、製造メーカの“Auto-Ordnance Corporation”社の経営は悪化し、破産の危機に直面していた。これを救ったのは、M1921の連射レートを700発/分まで下げた軍用モデルのM1928であり、500挺ほどが製造され米海軍・海兵隊に採用された[2]。
その後、第二次世界大戦が勃発すると同モデルは仏軍・英軍・スウェーデン軍に採用され、仏軍は3,750挺のM1928と3,000万発の弾薬を発注した。英軍ではコマンド部隊などがこれを使用したことで英兵の通称トミー(Tommy)に由来する“トミーガン”の愛称が付き、以降の代名詞となった。
M1928の納入価格は1939年頃で$209(現在の価格で$3,100程度[3]・希少品となった現在では$20,000前後で取り引きされている)だったとされ、“Auto-Ordnance Corporation”社の経営状態は好転した。
M1928A1[編集]
米軍向け改良モデル
欧州で第二次世界大戦が始まるまで、米陸軍で使用されていたトミーガンは400挺にも満たなかったが、大戦勃発と共に当時は未だ参戦していなかった米軍もM1928の大量調達を図り、軍用として試作されたM1923に近いフォルムを持つM1928A1が製造された。
M1928A1は米軍および英・仏・中といった諸国への援助兵器として総計562,511挺が生産され、量産効果により1942年春には$70(現在の価格で$880程度[3])まで調達コストは下がった。
M1/M1A1[編集]
戦時省力生産モデル
M1A1
M1を射撃するアメリカ海兵隊員。1945年5月、沖縄戦での撮影
詳細は「トンプソンM1短機関銃」を参照
トミーガンは切削加工を前提としたデザインであり、プレス加工を活用した大量生産には再設計が必要だったが、大幅な構造の変更はなされないまま、省力化と操作性向上のために幾つかの改良が施されたM1型が1942年に採用され(ステン短機関銃タイプの鋼板プレス製M3グリースガンも同年に採用された)、1943年末からSavage Arms社で大量生産が開始された[2]。
M1に採用された簡易化は、
工数がかかり信頼性も低かったブリッシュ・ロック式閉鎖機構の替わりに、ボルトの重量を増やしてシンプル・ブローバック方式に変更された。
銃身に装着されていたコンペンセイターや放熱フィンが廃止された。
ストックの固定法が直接ネジで止める方式に変更された。
ドラム弾倉装着用の横スリット溝が廃止された。
コッキングハンドルを上面から右側面にずらした。
といったもので、M1はM1928A1の半分の時間で製造され、調達コストは$45まで低下した。しかし、当初は供給が追いつかなかったため、レイジングM50など他のサブマシンガンで不足分を間に合わせていた。
1944年には簡素化が更に進められて撃針をボルトに固定し、照門(リアサイト)の側面に三角形の保護板を付けたM1A1が採用された。
M1/M1A1は累計で138万挺製造され、第二次世界大戦を通じて米軍でもっとも多く使用されたサブマシンガンとなり、主に下士官や戦車兵、空挺兵に対して供給された。米軍内では1976年頃まで予備兵器としてトミーガンが装備されていたほか、現代に至るまで様々な地域紛争で使用されているのが確認されており、その堅牢さから今後も使用され続けるものと考えられている。
普及[編集]
アメリカ[編集]
1932年の映画『暗黒街の顔役』でマフィアを演じるポール・ムニ
禁酒法の恩恵で急成長を遂げていた米国のマフィアが襲撃兵器としても防御用兵器としても優れていたトミーガンに注目し、抗争などで使用したことがトミーガンの知名度を飛躍的に高めた。
ギャング間の抗争事件は当時のマスコミの格好の題材であり、こうした事件が“再現フィルム”的に映像化されたハリウッド製作のギャング映画によって、トミーガンの存在は“マシンガン”の呼称とともに世界中に知れ渡り、トミーガン=機関銃という認識が広く定着するなど、実態以上に強い印象をもって記憶されており、寿司桶のようなドラムマガジンを装着したトミーガンの姿は“Roaring Twenties”(狂騒の20年代)を演出した歴史上重要なアイテムとして認識されている。
一方で、マフィアなど犯罪者達を取り締まってきたFBIにおいては、トミーガンが草創期の重要な火器だった事もあって、現在でも象徴的な意味を含めて継続して使用されており、同局舎における見学者向けのデモンストレーションでは、射撃教官によるトミーガンを用いた射撃が披露され、教官が標的上に自分の名前を弾痕で刻んで見せるのが通例となっている。
日本[編集]
日本においては、トンプソンサブマシンガンの存在は米国の映画を通じて広く知られており、海軍陸戦隊の近接戦闘用兵器としてMP18と比較検討 [6] されていたほか、陸軍の兵士達も中国各地で多数のM1921/M1928を鹵獲 [7] し、シンガポール占領で英軍から鹵獲されたトンプソンサブマシンガン600丁が、パレンバン作戦後に陸軍落下傘部隊に支給されたとも伝えられている[8]。
また、フィリピン占領時にはトンプソンサブマシンガンやM1ライフルを始めとする各種の米製兵器が大量に鹵獲され、現地の日本兵達はこうした米製兵器を好んで使用していた事が伝えられているほか、日本内地でこれら鹵獲火器に対する性能試験が実施され、その一部は準制式とされている [9]。
敗戦後の1950年に発足した警察予備隊に対しては、米国からM3グリースガンと並んで供与され、“サブマシンガン”の訳語として「短機関銃」という言葉が作られ「11.4mm短機関銃M1」として制式化された。
その後も保安隊-自衛隊において継続して装備され、陸上自衛隊では1970年代まで使用された他、海上自衛隊及び航空自衛隊では1990年代に入っても少数ながら現役として装備されていた。2010年代の現在においても、陸海空3自衛隊において“予備装備”として保管されている模様である。
中国[編集]
軍閥間の内戦が続いていた中国では軍民ともにM1921の人気が高く、山西省を支配した閻錫山の軍閥ではM1921のコピー品が生産され、モーゼル軍用拳銃をM1921の弾薬に合わせて.45ACP弾化した独自製品まで出現した。 また、各地で跋扈する匪賊の襲撃を撃退する効果的な兵器として、富裕な地主や帰国華僑 [10] なども、手頃な価格で強力な防御能力を発揮できるトンプソンサブマシンガンを用いていた。
中国に大量に存在したトンプソンサブマシンガンとコピー工廠は、国共内戦の終結と共に中国共産党の手に渡り、朝鮮戦争では米軍も中国軍も共にトミーガンを装備して戦っていた。その後のインドシナ戦争においてもベトミン/ベトコン勢力やビン・スエン派などがトンプソンサブマシンガンを使用していた事が知られているほか、南ベトナムではこれをコピー生産していた勢力があった事も知られている[2]。
登場作品[編集]
「ギャングが使用する危険な武器」「アメリカ軍の象徴」と捉えられる本銃の背景から、第二次世界大戦やギャングを題材とした作品によく登場する。
テレビ・映画[編集]
『L.A. ギャング ストーリー』
ギャング側がドラムマガジン付きのM1928、終盤ホテルの銃撃戦ではオマラ側がM1A1を使用。 『アサルト13 要塞警察』
警察側が使用。 『アンタッチャブル (テレビドラマ)』、『アンタッチャブル (映画)』
ネス、マローン、ストーン、ウォレス、また、その他ギャングが使用。 『インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説』
上海でギャングが使用。 『俺がハマーだ!』
21話に登場。 『ロード・トゥ・パーディション』
『ガルシアの首』
『キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー』
M1928及びM1928A1が登場。前者は劇中映画でマスコット時代のキャプテン・アメリカが使用。後者は一部の主要人物及び、その他米軍兵士と共に多数登場し、実戦参加後のキャプテン・アメリカが携行しているシーンも少しだけある。 『チェ 28歳の革命』
『パブリック・エネミーズ』
至るところで登場。 『ドキュメンタリー』
失われた世界の謎シリーズ 第25回『アル・カポネの暗黒の街』(ヒストリーチャンネル) 『SFドラマ 猿の軍団』
ゴードが愛用する銃。銃口に撮影用火薬の発火装置を追加したため、銃身がやや長くなっている。 『コンバット!』
ヴィック・モロー扮するサンダース軍曹の装備として登場し、彼のトレードマークになっていた。M1928A1が撮影に使われている。 『戦略大作戦』[11]
ケリー中尉とビッグ・ジョー曹長の他、彼らが率いる小隊のメンバーがM1A1を使用している。 『ゴッドファーザー』
マフィア映画の代表作と言われる本作のマフィアが使用し、多数の銃撃シーンや暗殺シーンで使用されている[11]。なお、ソニー・コルレオーネが乗る車の両側から蜂の巣状に銃撃されるシーンでは、日本製のモデルガンが使用されたと噂されている[11]。 『プライベート・ライアン』
ジョン・H・ミラー大尉が愛用している。 『バンド・オブ・ブラザース』
後にE中隊長となるスピアーズ中尉ほかが装備。 『ウインドトーカーズ』
ニコラス・ケイジ扮するジョー・エンダース伍長がドラム弾倉付きのM1928A1を使用。 『マスク』
マスクを被ってハイテンションになったスタンリーが路地裏でドラムマガジン付きのM1921を乱射。 『遠すぎた橋』[11]
アメリカ軍兵士が主に使用。 『史上最大の作戦』
アメリカ軍レンジャー部隊が使用。 『ザ・パシフィック』
第1海兵師団の隊員が使用。 『ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝』
リック・オコーネルが使用。 『ゾンビ』
略奪者のメンバーの一人が使用。 『謎解きはディナーのあとで』
『太平洋の奇跡 -フォックスと呼ばれた男-』
M1A1をサイパン島に上陸したアメリカ海兵隊の兵士と鹵獲した物を旧日本軍の堀内一等兵が使用。 『沈黙の逆襲』
銃の組み立てを行うシーンで机に置いてある。
アニメ[編集]
『ルパン三世 霧のエリューシヴ』
ノース家の兵達が使用。 『神のみぞ知るセカイ』
『ストライクウィッチーズ』
主要人物の一人 シャーロット・E・イェーガーが使用。 『ジパング』
ガダルカナルにおいて米兵が使用 『うぽって』
『ゆるゆり♪♪』
12話で池田千鶴が2丁使用。フォアグリップがついていない。 『ドラえもん』
ドラえもんが使用。
漫画[編集]
『ジョジョの奇妙な冒険』
Part2戦闘潮流でジョセフがストレイツォに対し使用。 『ワイルド7』
ユキ、飛葉が使用。M1928。モデルガンと見せかけて実は実銃。実写版では最終的にメインアームになっている。 『クロノクルセイド』
ロゼット・クリストファが特殊弾「聖火弾」を装填したドラムマガジンを装着して使用。 『DOGS/BULLETS&CARNAGE』
小説[編集]
『スティーヴン・ハンター』『悪徳の都』
主人公のアール・スワガーがトミーガンの名手で、スワガーが率いる違法カジノ摘発部隊の標準装備がコルト・ガバメントとトミーガンである。 『ラプラスの魔』
草壁健一郎がモーガン奪還のため仲間と共に異世界に強襲した際に使用。
ゲーム[編集]
『カウンターストライクオンライン』 (Windows用ゲーム)
課金武器として登場。 『OPERATION7』
『Paperman』 (Windows用ゲーム)
TOMMY GUNの名称でM1928が登場。但し、連射速度が低く設定されている。 『Alliance of Valiant Arms』
カプセル商店で販売。ポイントマン武器であり、使用者は少ない。 『バイオハザード4』
シカゴタイプライターの名でM1A1が登場。 『バトルフィールド1942』
『メダルオブオナーシリーズ』
『Mafia: The City of Lost Heaven』
『Mafia 2』
『L.A.ノワール』
『HIDDEN & DANGEROUS 2』 (Windows用ゲーム)
『メタルギアソリッド3』
ザ・ペインが使用している。 『メタルギアソリッド ピースウォーカー』
マザーベースで開発可能。 強化によりグリップがつく。 『コール オブ デューティシリーズ』
『スナイパーエリートV2』
『Wolfenstein: Enemy Territory』 (FPS)
『VIETCONG: ベトコン』 (Windows用ゲーム)
『Deadly Dozen』 (Windows用ゲーム)
『Fallout: New Vegas』
DLC「Honest Hearts」にて『.45オートサブマシンガン』(.45 Auto Submachine Gun)の名称で登場。また、光線銃『レーザーRCW』もトンプソンをモチーフとしている。 『ブラザー イン アームズシリーズ』 (Windows,PS2,Xbox用ゲーム)
『BIOSHOCK』 (Windows,Xbox360用ゲーム)
『ゴッドファーザー』 (Xbox360,PS3,PS2用ゲーム)
『ゴーストトリック』
カノンが使用している。 『THE 歩兵 〜戦場の犬たち〜』
『クラッシュ・バンディクー』シリーズ
ピンストライプが使用している。 『戦場のカルマ』
ゲーム内通貨で購入可能。 『クトゥルフの呼び声 (TRPG)』
同テーブルトークRPGの基本セットの中に『トンプソン式サブマシンガン』の名称で登場。マシンガンの弾丸1発当たりのダメージは1d10+2で1戦闘ラウンドで弾倉の中身を空にするまで撃つ事が出来るため同ゲームで非常に強力な武器となっていた。 『WarRock』
「Chicago Typewriter」の名称で登場。 『怪盗ロワイアル-zero-』
トミーガンの名称で登場。
脚注[編集]
1.^ a b c Bishop, Chris. Guns in Combat. Chartwell Books, Inc (1998). ISBN 0-7858-0844-2.
2.^ a b c d e "The world's submachine guns"
Thomas B Nelson, T.B.N. Enterprises, 1963,
ASIN: B0007HVRYY
Prototype to 1919 Warner & Swasey
Models 1921 to 1928 Colt
British made guns B.S.A.
1928A1 & M1 series Auto-Ordnance & Savage
Unlicensed copies China & Viet-Nam
3.^ a b c The Inflation Calculatorから換算
4.^ a b THE THOMPSON SUB-MACHINE GUN, Philip B. Sharpe
5.^ Ireland's History Magazine "Thompson submachine-gun"
6.^ Refcode:C05021291500 『第3530号 5.10.29 兵器貸与並に供給の件』 海軍砲術学校 海軍省公文備考 昭和5年10月29日 横鎮長官 「昭和5年10月21日起案 昭和五年十月二十九日 大臣 横鎮長官宛 兵器貸与並ニ供給ノ件訓令 官房第三五五〇号 横須賀海軍軍需部ノ在庫ノ左記兵器ヲ実験用トシテ昭和六年六月末日迄海軍砲術学校ニ貸与並ニ供給方取計フヘシ 記 トムソン自動拳銃 附属品共 一挺 内砲第一二三六号 @支ノ為貸与 仝 弾薬包 五〇〇個 内砲第一二三七号 @支ノ分供給 (終)」
7.^ 陸軍省大日記 大日記乙輯昭和13年 陸軍技術本部 昭和13年3月〜4月 「軍事、防、主 参第三五三号 陸軍技術本部 押收兵器下付ノ件 昭和13年3月26日 昭和13年4月6日 陸支密 陸軍技術本部長ヘ指令 3月25日附陸技本甲第一六三号申請ノ通認可ス 陸支密第一〇四四号 昭和13年4月4日 陸支密 陸軍兵器本廠長ヘ達 別紙ノ通審査ノタメ陸軍技術本部ニ下付方取計フヘシ 但シ費用ハ臨時軍事費支弁トス 陸支密第一〇四四号 昭和13年4月4日 官房控 別紙 兵器本廠 七粍九捷克歩兵銃 東京兵器支廠保管ノモノ「図書共」 七粍九車筒歩兵銃 以下同シ 各種押收ヤ銃 各種挙銃 自動短銃 各種歩兵銃 テルニ歩兵銃 露式七粍七歩兵銃 トンプソン自動短銃 ブリンデ歩兵銃 各種ヤ銃々身 チエッコ軽機関銃」
8.^ 『陸軍落下傘部隊戦記 あゝ純白の花負いて』 田中賢一著 学陽書房 1976年 P130~131
9.^ 昭和19年2月に作成された大日本帝国陸軍の資料中では、米軍が装備するサブマシンガン(日本陸軍では“機関短銃”と呼んだ)について、トンプソン機関短銃、ライジング機関短銃、M3機関短銃の3点が、鹵獲された米軍資料から転載したと思しきイラスト付きで紹介されている Refcode:A03032193600 『米軍銃器火砲一覧表』 陸軍兵器行政本部 昭和19年2月20日
10.^ 1930年代に福建省に潜伏したタン・マラカは、インドネシアから帰国した客属華僑と知り合い、その下に一時身を寄せていたが、匪賊による襲撃の噂が流れたため、これに備えて華僑の一族がトンプソンサブマシンガンなどの各種火器を準備して迎撃準備に努めていた事を記しており、当時の中国国内でトンプソンサブマシンガンは比較的身近な存在だった事が伺える 『牢獄から牢獄へ - タン・マラカ自伝』 タン・マラカ 著 押川典昭 訳 鹿砦社 1981年7月
11.^ a b c d HEROS Gunバトル ヒーローたちの名銃ベスト100. リイド社. (2010-11-29). pp. pp.190-191. ISBN 978-4-8458-3940-7.

移動: 案内、 検索
「トミー・ガン」はこの項目へ転送されています。ザ・クラッシュの楽曲については「トミー・ガン (曲)」をご覧ください。
トンプソン・サブマシンガン
戦時中に生産されたトンプソン M1928A1
種類
短機関銃
原開発国
アメリカ合衆国
運用史
配備期間
1938年–1971年
(アメリカ陸軍)
配備先
米国はじめ各国
関連戦争・紛争
アイルランド独立戦争
アイルランド内戦
バナナ戦争
日中戦争
第二次世界大戦 [1]
朝鮮戦争 [1]
国共内戦
第一次中東戦争
第一次インドシナ戦争
ベトナム戦争 [1]
ボスニア紛争
開発史
開発者
ジョン・T・トンプソン
開発期間
1917年–1920年
製造業者
Auto-Ordnance Company
(オリジナル)
バーミンガム・スモール・アームズ
コルト
Savage Arms
製造期間
1921年–現在
製造数
約1,700,000丁
派生型
Persuader & Annihilator 試作機,
M1921, M1921AC, M1921A,
M1927, M1928, M1928A1,
M1, M1A1
諸元
重量
10.8lb(4.9kg)空の場合(M1928A1)
10.6lb(4.8kg)空の場合(M1A1)
全長
33.5 in (851 ミリメートル)(M1928A1)
32 in (813 ミリメートル)(M1A1/M1)
銃身 10.5 in (267 ミリメートル)
銃身にオプションでCutts Compensatorが付く 12 in (305 ミリメートル)
--------------------------------------------------------------------------------
弾丸
.45ACP弾(11.43×23mm)
作動方式
シンプル・ブローバック方式
ブリッシュ・ロック方式
発射速度
600–1200発/分
(各モデルにより異なる)
初速
285 m/s (935 ft/s)
有効射程
50メートル (160 ft)
装填方式
20発 箱型弾倉
30発 箱型弾倉
50発 ドラムマガジン
100発 ドラムマガジン
(M1とM1A1はドラムマガジンを装着出来ない)
トンプソン・サブマシンガン(Thompson submachine gun)は、アメリカで開発された短機関銃。トムソン銃、シカゴ・タイプライターといった通称を持つことで知られるが、本項ではトミーガンに統一して表記する。
トミーガンは、禁酒法時代のアメリカ合衆国内において警察とギャングの双方に用いられたことで有名になった。1919年から累計170万挺以上が生産され、今日でも製造が続けられている長命な製品である。頑丈な構造を持ち、耐久性と信頼性に優れ、5kg近い重量のおかげでフルオート射撃を制御しやすい特性から、世界各国で広く用いられた。
目次
[非表示] 1 構造
2 開発
3 バリエーション 3.1 M1919
3.2 M1921
3.3 M1923
3.4 M1927
3.5 M1928
3.6 M1928A1
3.7 M1/M1A1
4 普及 4.1 アメリカ
4.2 日本
4.3 中国
5 登場作品 5.1 テレビ・映画
5.2 アニメ
5.3 漫画
5.4 小説
5.5 ゲーム
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
構造[編集]
トミーガンを特徴付けているのは、主要部品の多くが角を丸めた直角で構成されている点で、円形を基本に構成される事が多かった欧州の製品とは一線を画したデザインとなっている。これはトミーガンは鋼鉄ブロックからの切削加工で製造され、切削作業の大部分が平フライス加工だけで行えるよう考慮したためである。この結果、大規模な専用生産施設を持たなくても、外注工場の利用が容易で効率よく製作できるメリットがあり、中国やベトナムなど工業水準の低い諸国でも容易にコピー生産が可能となった。
トミーガンは上下2つのレシーバ(機関部)によって構成されており、銃身は上部レシーバ先端にネジで固定され、弾倉が接触する部分はドラム型弾倉を装着するため大きく切り欠かれた形状となっているほか、内部はフライス加工によって大きくえぐられ、この空洞内をボルトが前後する。
弾倉は上部まで露出しているため、野戦では泥などが付着しやすいが、逆に拭い去る事も簡単な構造となっている。箱型弾倉を装填する際には下側から、ドラム型弾倉を装填する際には横からスライドさせて装着し、どちらもレール溝によって支持されている。M1/M1A1(後述)では横溝が省略されてドラム型弾倉が使用できないが、上部レシーバの切り欠きはそのままなので、後から横溝を刻むだけで使用できるようになる。
下部レシーバは複雑な形状ながら、機能的には上部レシーバの下部を塞ぎ、トリガーメカを保持するだけの単純な構造である。上下のレシーバはレール溝によって嵌合し、分解する際に上部レシーバ後端にあるストッパを押し込んで下部レシーバを引き抜く形で分離できる。
セミ/フルオートを切り替えるセレクターと、セフティ(安全装置)は別々のレバー状部品として存在しているが、弾倉を固定しているマガジン・キャッチを含めて、位置は全てグリップ上部左側面にあるため、右利きの射手であれば、グリップから手を離さず全て右手親指で操作する事が可能である。
一般的に「トミーガンは生産性が悪かった」と認識されているが、トミーガンの省力化が図られた1940年代にはM1/M1A1のように、単純な板金曲げ加工とスポット溶接に、バレル・カラーなどの切削部品を組み合わせるだけで、同様の外見構造を強度を落とさず低コストで実現できたため、切削加工を前提とした当時の基準ではことさらに生産性の悪い構造だったとは言えない。しかし第二次世界大戦中には全軍への普及を図るべく、MP40やステン短機関銃などに代表される、より一層と生産性が高い短機関銃が要求され、その結果としてプレス加工主体のM3グリースガンの開発が行われた。
また、携行性をあまり重視しない長く重い銃ではあったが、ちゃんと構えて保持すればその重さが発砲の反動を相殺し、良好な命中精度を発揮した。
開発[編集]
ジョン・T・トンプソン元大佐
1916年、アメリカのジョン・T・トンプソン元陸軍大佐(後に復帰し准将として再度退役する)が設立したオート・オードナンス社において、「塹壕箒」(trench broom)と仮称される自動式小火器の試作が開始された。
この自動式小火器は、塹壕戦で膠着状態となった第一次世界大戦の状況を見て、これを打開できる個人装備の需要予測に基づいて開始され、その動機は純粋に商業的なものだった。
当時の機関銃は巨大かつ重量級の装備であり、軽機関銃といえども兵士が一人で操作できる存在ではなく、機械的な信頼性も低かった。そして機関銃は突撃する兵士に随伴して後方から援護射撃を加える事すら難しかった。しかし、塹壕戦の打開に必要とされていたのは、機関銃で強固に防衛された敵塹壕に対する肉薄および突破であり、これに用いる銃器には兵士が携帯できるサイズ・重量であることやフルオート射撃能力が求められた。
1917年に第一次世界大戦に参戦した米軍でも、塹壕の突破を目的として軍用ショットガンや秘密兵器であるピダーセン・デバイスを量産・装備していた。また、同時期の米国ではジョン・ブローニングによってブローニングM1918自動小銃(BAR)の開発が進められていた他、同時期にはドイツ帝国でも塹壕陣地の突破を任務とする突撃歩兵の為にMP18なる小型機関銃の開発が進められていた。
塹壕戦用小型機関銃
トンプソン大佐が提唱した塹壕箒なる自動式小火器は、1918年に試作されたPersuader(パースエーダー。説得者/言うことを聞かせるものの意) によって初めて具体的な形となった。
Persuaderの給弾方式はベルト給弾式だったが、機関部が砂塵や泥汚れに弱いという欠点があった。そこで、これを箱型弾倉に改めたタイプが1919年に試作され、Annihilator(アナイアレーター。絶滅者/敵を打ち負かすものの意)と名付けられた。
両製品は、ともにブリッシュ・ロック方式と呼ばれる遅延式ブローバック閉鎖機構を持ち、後のトミーガンの基本構成要素を備えていた。
バリエーション[編集]
M1919[編集]
最初の『サブマシンガン』
“Annihilator”が完成する前年に第一次世界大戦は終結していたが、トンプソン大佐は念願の製品化に着手し、精密機器メーカーのWarner & Swasey社が製作を担当した。 [2]
このモデルは後年M1919と呼ばれているが、発売に際して付けられた製品名はThompson submachine gunであり、サブマシンガンの名称が初めて使用された。
サブマシンガンは“小型機関銃”を意味する製品名だったが、後に拳銃弾を使用するフルオート火器を総称する呼称として、世界的に使用されるようになった。
M1919は.45ACP弾、.22LR、.32ACP弾、.38 ACP、9x19mmパラベラム弾など各種の弾薬用に製造され、照星や銃床を持たないなど、デモンストレーション用/テスト用としての色彩が強い製品だった。トミーガンの特徴となった垂直フォアグリップは銃身下部に装着され、安定したフルオート射撃が可能だったが、連射レートは1,000発/分程度と高速だった。
1920年4月に行われた軍の採用テストでは、2,000発の発射に対し動作不良は2回のみ、という好成績を残したが、大戦を終えた米陸軍は軍縮に向かっており、M1919が採用される事はなかった。軍用としての見込みが無くなった事から、トンプソン大佐は販売先を警察に切り替え、40挺ほどがニューヨーク市警察によって購入された。
M1921[編集]
民間市場での成功と知名度の獲得
トンプソン自動小銃(上)とM1921
「強盗が一番恐れる銃」と記された1920年代の広告
M1921は、M1919に改良を加えた量産タイプの製品であり、民間市場向けに「手軽にフルオート射撃を楽しめる“スポーツ用途”の銃」として販売が開始された。
1921年当時の販売価格は20発箱型弾倉付きで$225(現在の価格に換算[3]して$2,600程度)であり、製造はコルト社が担当し、15,000挺ほどが生産された[2]。
富裕層向けの高級玩具としての色彩が強い製品であり、木部は美しく仕上げられ、各部品は高精度な切削加工で製造されていた。 弾倉は20発/30発箱形弾倉のほかに50発用ドラム弾倉が用意され、連射レートは800発/分程度まで落とされていた。
1926年からは銃口部にCuts Compensatorと呼ばれるマズルブレーキの一種がオプションで装着できるようになり、フルオート射撃時のコントロールはより安定した[4]。
なお、最初にM1921の大口顧客となったのは、米国のアイルランド系移民の独立運動支持者達と考えられており、製造番号が1,000番未満の初期生産品が英領アイルランドで発見されている。これらのM1921はIrish Swordと呼ばれ、後のアイルランド内戦では主に反条約派によって使用された[5]。
また、当時頻発していた郵便強盗対策のために、米国郵便公社もM1921を400挺購入した。同公社が購入したM1921は、郵便警護を分担した海兵隊にも供与されたが、海兵隊はこれをバナナ戦争での軍事行動に転用した。
しかし、当時のM1921は民間人(この中にはトミーガンを有名にしたマフィア達も含まれていた)を主な購入者としており、1934年に規制されるまで購入に何らの制約も無く通信販売でも購入できたため、バナナ戦争における交戦相手のサンディーノ軍(ニカラグア)も、海兵隊と同様にM1921を装備していた。
M1923[編集]
強装弾薬の試行
トンプソン大佐が想定していた小型機関銃のコンセプトは小銃弾を使用するものであり、M1921に使用された.45ACP弾(480J)のパワーと、有効射程が50ヤードしかなかったM1921の射程は、軍用として力不足なものだった。
しかし、ブリッシュ・ロック方式の閉鎖機構は、その主要部品に真鍮製のロッキング・ピースを用いており、強烈な腔圧を発生させる当時のフルサイズ小銃弾には不向きな事が判明していたため、.45ACP弾の薬莢長を3mm延長して威力を増大した.45 Remington-Thompson弾(1,590J)が新規に開発され、これを用いるM1923が試作された。
.45 Remington-Thompson弾は.45ACP弾の3倍ものエネルギーを持ち、後に開発された.44 Magnum弾に近いパワーを有し、至近距離で杉板15枚、300ヤードで8枚を貫通したとされる[4]。 .45 Remington-Thompson弾はテストの結果.45ACP弾よりも精度が悪い事が判明し、市販されずに終わった。
M1923はM1921より約10cm銃身が延長され、軍用に適した水平フォアグリップが装着されていたほか、強くなった反動を制御するために連射速度は400発/分程度まで遅延されていた(参考画像) 着剣装置が付けられたタイプや、二脚を付けた軽機関銃タイプも試作されて米軍向けのプレゼンが行われたが、既にBARが採用されていた事もあり、採用には至らなかった。そのスタイルは後の軍用モデルであるM1928A1やM1/M1A1へ継承された。
M1927[編集]
セミオート・バージョン
M1921は当時数少ないフルオート火器だったため、慣れない射手が引き鉄を引き続けて銃口が跳ね上がり、制御不能となって意図せぬ方向を撃ってしまう事故が発生する事があった。このためM1921からフルオート射撃の機能を削除し、セミオート・カービンとした製品が要望され、M1927が製造された。
M1927はM1921を改造して製造されたため、M1921の刻印である“Thompson Submachine Gun”を一部削り取り、“Thompson Semi-Automatic Carbine”と改めて打刻し直されている。
M1927はM1921とほとんど同じ製品であるため、簡単にフルオート射撃の機能を復活させる事ができたが、1934年の連邦法改正によるフルオート火器の所持規制以降も民間人が無許可で購入できるトミーガンとして製造され続けた。ただし、1982年以降、オープンボルト撃発火器は、フルオートへの改造を前提とした火器と見なされるようになったため、現在では所持制限の対象となっている。
また、トミーガン用の100連ドラム弾倉はM1927と同時に販売されるようになった。
M1928[編集]
トンプソンM1928を持つイギリス兵(1940年) 正規軍に採用された軍用モデル
マスコミへの露出でM1921は実態以上に有名となったが、製造メーカの“Auto-Ordnance Corporation”社の経営は悪化し、破産の危機に直面していた。これを救ったのは、M1921の連射レートを700発/分まで下げた軍用モデルのM1928であり、500挺ほどが製造され米海軍・海兵隊に採用された[2]。
その後、第二次世界大戦が勃発すると同モデルは仏軍・英軍・スウェーデン軍に採用され、仏軍は3,750挺のM1928と3,000万発の弾薬を発注した。英軍ではコマンド部隊などがこれを使用したことで英兵の通称トミー(Tommy)に由来する“トミーガン”の愛称が付き、以降の代名詞となった。
M1928の納入価格は1939年頃で$209(現在の価格で$3,100程度[3]・希少品となった現在では$20,000前後で取り引きされている)だったとされ、“Auto-Ordnance Corporation”社の経営状態は好転した。
M1928A1[編集]
米軍向け改良モデル
欧州で第二次世界大戦が始まるまで、米陸軍で使用されていたトミーガンは400挺にも満たなかったが、大戦勃発と共に当時は未だ参戦していなかった米軍もM1928の大量調達を図り、軍用として試作されたM1923に近いフォルムを持つM1928A1が製造された。
M1928A1は米軍および英・仏・中といった諸国への援助兵器として総計562,511挺が生産され、量産効果により1942年春には$70(現在の価格で$880程度[3])まで調達コストは下がった。
M1/M1A1[編集]
戦時省力生産モデル
M1A1
M1を射撃するアメリカ海兵隊員。1945年5月、沖縄戦での撮影
詳細は「トンプソンM1短機関銃」を参照
トミーガンは切削加工を前提としたデザインであり、プレス加工を活用した大量生産には再設計が必要だったが、大幅な構造の変更はなされないまま、省力化と操作性向上のために幾つかの改良が施されたM1型が1942年に採用され(ステン短機関銃タイプの鋼板プレス製M3グリースガンも同年に採用された)、1943年末からSavage Arms社で大量生産が開始された[2]。
M1に採用された簡易化は、
工数がかかり信頼性も低かったブリッシュ・ロック式閉鎖機構の替わりに、ボルトの重量を増やしてシンプル・ブローバック方式に変更された。
銃身に装着されていたコンペンセイターや放熱フィンが廃止された。
ストックの固定法が直接ネジで止める方式に変更された。
ドラム弾倉装着用の横スリット溝が廃止された。
コッキングハンドルを上面から右側面にずらした。
といったもので、M1はM1928A1の半分の時間で製造され、調達コストは$45まで低下した。しかし、当初は供給が追いつかなかったため、レイジングM50など他のサブマシンガンで不足分を間に合わせていた。
1944年には簡素化が更に進められて撃針をボルトに固定し、照門(リアサイト)の側面に三角形の保護板を付けたM1A1が採用された。
M1/M1A1は累計で138万挺製造され、第二次世界大戦を通じて米軍でもっとも多く使用されたサブマシンガンとなり、主に下士官や戦車兵、空挺兵に対して供給された。米軍内では1976年頃まで予備兵器としてトミーガンが装備されていたほか、現代に至るまで様々な地域紛争で使用されているのが確認されており、その堅牢さから今後も使用され続けるものと考えられている。
普及[編集]
アメリカ[編集]
1932年の映画『暗黒街の顔役』でマフィアを演じるポール・ムニ
禁酒法の恩恵で急成長を遂げていた米国のマフィアが襲撃兵器としても防御用兵器としても優れていたトミーガンに注目し、抗争などで使用したことがトミーガンの知名度を飛躍的に高めた。
ギャング間の抗争事件は当時のマスコミの格好の題材であり、こうした事件が“再現フィルム”的に映像化されたハリウッド製作のギャング映画によって、トミーガンの存在は“マシンガン”の呼称とともに世界中に知れ渡り、トミーガン=機関銃という認識が広く定着するなど、実態以上に強い印象をもって記憶されており、寿司桶のようなドラムマガジンを装着したトミーガンの姿は“Roaring Twenties”(狂騒の20年代)を演出した歴史上重要なアイテムとして認識されている。
一方で、マフィアなど犯罪者達を取り締まってきたFBIにおいては、トミーガンが草創期の重要な火器だった事もあって、現在でも象徴的な意味を含めて継続して使用されており、同局舎における見学者向けのデモンストレーションでは、射撃教官によるトミーガンを用いた射撃が披露され、教官が標的上に自分の名前を弾痕で刻んで見せるのが通例となっている。
日本[編集]
日本においては、トンプソンサブマシンガンの存在は米国の映画を通じて広く知られており、海軍陸戦隊の近接戦闘用兵器としてMP18と比較検討 [6] されていたほか、陸軍の兵士達も中国各地で多数のM1921/M1928を鹵獲 [7] し、シンガポール占領で英軍から鹵獲されたトンプソンサブマシンガン600丁が、パレンバン作戦後に陸軍落下傘部隊に支給されたとも伝えられている[8]。
また、フィリピン占領時にはトンプソンサブマシンガンやM1ライフルを始めとする各種の米製兵器が大量に鹵獲され、現地の日本兵達はこうした米製兵器を好んで使用していた事が伝えられているほか、日本内地でこれら鹵獲火器に対する性能試験が実施され、その一部は準制式とされている [9]。
敗戦後の1950年に発足した警察予備隊に対しては、米国からM3グリースガンと並んで供与され、“サブマシンガン”の訳語として「短機関銃」という言葉が作られ「11.4mm短機関銃M1」として制式化された。
その後も保安隊-自衛隊において継続して装備され、陸上自衛隊では1970年代まで使用された他、海上自衛隊及び航空自衛隊では1990年代に入っても少数ながら現役として装備されていた。2010年代の現在においても、陸海空3自衛隊において“予備装備”として保管されている模様である。
中国[編集]
軍閥間の内戦が続いていた中国では軍民ともにM1921の人気が高く、山西省を支配した閻錫山の軍閥ではM1921のコピー品が生産され、モーゼル軍用拳銃をM1921の弾薬に合わせて.45ACP弾化した独自製品まで出現した。 また、各地で跋扈する匪賊の襲撃を撃退する効果的な兵器として、富裕な地主や帰国華僑 [10] なども、手頃な価格で強力な防御能力を発揮できるトンプソンサブマシンガンを用いていた。
中国に大量に存在したトンプソンサブマシンガンとコピー工廠は、国共内戦の終結と共に中国共産党の手に渡り、朝鮮戦争では米軍も中国軍も共にトミーガンを装備して戦っていた。その後のインドシナ戦争においてもベトミン/ベトコン勢力やビン・スエン派などがトンプソンサブマシンガンを使用していた事が知られているほか、南ベトナムではこれをコピー生産していた勢力があった事も知られている[2]。
登場作品[編集]
「ギャングが使用する危険な武器」「アメリカ軍の象徴」と捉えられる本銃の背景から、第二次世界大戦やギャングを題材とした作品によく登場する。
テレビ・映画[編集]
『L.A. ギャング ストーリー』
ギャング側がドラムマガジン付きのM1928、終盤ホテルの銃撃戦ではオマラ側がM1A1を使用。 『アサルト13 要塞警察』
警察側が使用。 『アンタッチャブル (テレビドラマ)』、『アンタッチャブル (映画)』
ネス、マローン、ストーン、ウォレス、また、その他ギャングが使用。 『インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説』
上海でギャングが使用。 『俺がハマーだ!』
21話に登場。 『ロード・トゥ・パーディション』
『ガルシアの首』
『キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー』
M1928及びM1928A1が登場。前者は劇中映画でマスコット時代のキャプテン・アメリカが使用。後者は一部の主要人物及び、その他米軍兵士と共に多数登場し、実戦参加後のキャプテン・アメリカが携行しているシーンも少しだけある。 『チェ 28歳の革命』
『パブリック・エネミーズ』
至るところで登場。 『ドキュメンタリー』
失われた世界の謎シリーズ 第25回『アル・カポネの暗黒の街』(ヒストリーチャンネル) 『SFドラマ 猿の軍団』
ゴードが愛用する銃。銃口に撮影用火薬の発火装置を追加したため、銃身がやや長くなっている。 『コンバット!』
ヴィック・モロー扮するサンダース軍曹の装備として登場し、彼のトレードマークになっていた。M1928A1が撮影に使われている。 『戦略大作戦』[11]
ケリー中尉とビッグ・ジョー曹長の他、彼らが率いる小隊のメンバーがM1A1を使用している。 『ゴッドファーザー』
マフィア映画の代表作と言われる本作のマフィアが使用し、多数の銃撃シーンや暗殺シーンで使用されている[11]。なお、ソニー・コルレオーネが乗る車の両側から蜂の巣状に銃撃されるシーンでは、日本製のモデルガンが使用されたと噂されている[11]。 『プライベート・ライアン』
ジョン・H・ミラー大尉が愛用している。 『バンド・オブ・ブラザース』
後にE中隊長となるスピアーズ中尉ほかが装備。 『ウインドトーカーズ』
ニコラス・ケイジ扮するジョー・エンダース伍長がドラム弾倉付きのM1928A1を使用。 『マスク』
マスクを被ってハイテンションになったスタンリーが路地裏でドラムマガジン付きのM1921を乱射。 『遠すぎた橋』[11]
アメリカ軍兵士が主に使用。 『史上最大の作戦』
アメリカ軍レンジャー部隊が使用。 『ザ・パシフィック』
第1海兵師団の隊員が使用。 『ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝』
リック・オコーネルが使用。 『ゾンビ』
略奪者のメンバーの一人が使用。 『謎解きはディナーのあとで』
『太平洋の奇跡 -フォックスと呼ばれた男-』
M1A1をサイパン島に上陸したアメリカ海兵隊の兵士と鹵獲した物を旧日本軍の堀内一等兵が使用。 『沈黙の逆襲』
銃の組み立てを行うシーンで机に置いてある。
アニメ[編集]
『ルパン三世 霧のエリューシヴ』
ノース家の兵達が使用。 『神のみぞ知るセカイ』
『ストライクウィッチーズ』
主要人物の一人 シャーロット・E・イェーガーが使用。 『ジパング』
ガダルカナルにおいて米兵が使用 『うぽって』
『ゆるゆり♪♪』
12話で池田千鶴が2丁使用。フォアグリップがついていない。 『ドラえもん』
ドラえもんが使用。
漫画[編集]
『ジョジョの奇妙な冒険』
Part2戦闘潮流でジョセフがストレイツォに対し使用。 『ワイルド7』
ユキ、飛葉が使用。M1928。モデルガンと見せかけて実は実銃。実写版では最終的にメインアームになっている。 『クロノクルセイド』
ロゼット・クリストファが特殊弾「聖火弾」を装填したドラムマガジンを装着して使用。 『DOGS/BULLETS&CARNAGE』
小説[編集]
『スティーヴン・ハンター』『悪徳の都』
主人公のアール・スワガーがトミーガンの名手で、スワガーが率いる違法カジノ摘発部隊の標準装備がコルト・ガバメントとトミーガンである。 『ラプラスの魔』
草壁健一郎がモーガン奪還のため仲間と共に異世界に強襲した際に使用。
ゲーム[編集]
『カウンターストライクオンライン』 (Windows用ゲーム)
課金武器として登場。 『OPERATION7』
『Paperman』 (Windows用ゲーム)
TOMMY GUNの名称でM1928が登場。但し、連射速度が低く設定されている。 『Alliance of Valiant Arms』
カプセル商店で販売。ポイントマン武器であり、使用者は少ない。 『バイオハザード4』
シカゴタイプライターの名でM1A1が登場。 『バトルフィールド1942』
『メダルオブオナーシリーズ』
『Mafia: The City of Lost Heaven』
『Mafia 2』
『L.A.ノワール』
『HIDDEN & DANGEROUS 2』 (Windows用ゲーム)
『メタルギアソリッド3』
ザ・ペインが使用している。 『メタルギアソリッド ピースウォーカー』
マザーベースで開発可能。 強化によりグリップがつく。 『コール オブ デューティシリーズ』
『スナイパーエリートV2』
『Wolfenstein: Enemy Territory』 (FPS)
『VIETCONG: ベトコン』 (Windows用ゲーム)
『Deadly Dozen』 (Windows用ゲーム)
『Fallout: New Vegas』
DLC「Honest Hearts」にて『.45オートサブマシンガン』(.45 Auto Submachine Gun)の名称で登場。また、光線銃『レーザーRCW』もトンプソンをモチーフとしている。 『ブラザー イン アームズシリーズ』 (Windows,PS2,Xbox用ゲーム)
『BIOSHOCK』 (Windows,Xbox360用ゲーム)
『ゴッドファーザー』 (Xbox360,PS3,PS2用ゲーム)
『ゴーストトリック』
カノンが使用している。 『THE 歩兵 〜戦場の犬たち〜』
『クラッシュ・バンディクー』シリーズ
ピンストライプが使用している。 『戦場のカルマ』
ゲーム内通貨で購入可能。 『クトゥルフの呼び声 (TRPG)』
同テーブルトークRPGの基本セットの中に『トンプソン式サブマシンガン』の名称で登場。マシンガンの弾丸1発当たりのダメージは1d10+2で1戦闘ラウンドで弾倉の中身を空にするまで撃つ事が出来るため同ゲームで非常に強力な武器となっていた。 『WarRock』
「Chicago Typewriter」の名称で登場。 『怪盗ロワイアル-zero-』
トミーガンの名称で登場。
脚注[編集]
1.^ a b c Bishop, Chris. Guns in Combat. Chartwell Books, Inc (1998). ISBN 0-7858-0844-2.
2.^ a b c d e "The world's submachine guns"
Thomas B Nelson, T.B.N. Enterprises, 1963,
ASIN: B0007HVRYY
Prototype to 1919 Warner & Swasey
Models 1921 to 1928 Colt
British made guns B.S.A.
1928A1 & M1 series Auto-Ordnance & Savage
Unlicensed copies China & Viet-Nam
3.^ a b c The Inflation Calculatorから換算
4.^ a b THE THOMPSON SUB-MACHINE GUN, Philip B. Sharpe
5.^ Ireland's History Magazine "Thompson submachine-gun"
6.^ Refcode:C05021291500 『第3530号 5.10.29 兵器貸与並に供給の件』 海軍砲術学校 海軍省公文備考 昭和5年10月29日 横鎮長官 「昭和5年10月21日起案 昭和五年十月二十九日 大臣 横鎮長官宛 兵器貸与並ニ供給ノ件訓令 官房第三五五〇号 横須賀海軍軍需部ノ在庫ノ左記兵器ヲ実験用トシテ昭和六年六月末日迄海軍砲術学校ニ貸与並ニ供給方取計フヘシ 記 トムソン自動拳銃 附属品共 一挺 内砲第一二三六号 @支ノ為貸与 仝 弾薬包 五〇〇個 内砲第一二三七号 @支ノ分供給 (終)」
7.^ 陸軍省大日記 大日記乙輯昭和13年 陸軍技術本部 昭和13年3月〜4月 「軍事、防、主 参第三五三号 陸軍技術本部 押收兵器下付ノ件 昭和13年3月26日 昭和13年4月6日 陸支密 陸軍技術本部長ヘ指令 3月25日附陸技本甲第一六三号申請ノ通認可ス 陸支密第一〇四四号 昭和13年4月4日 陸支密 陸軍兵器本廠長ヘ達 別紙ノ通審査ノタメ陸軍技術本部ニ下付方取計フヘシ 但シ費用ハ臨時軍事費支弁トス 陸支密第一〇四四号 昭和13年4月4日 官房控 別紙 兵器本廠 七粍九捷克歩兵銃 東京兵器支廠保管ノモノ「図書共」 七粍九車筒歩兵銃 以下同シ 各種押收ヤ銃 各種挙銃 自動短銃 各種歩兵銃 テルニ歩兵銃 露式七粍七歩兵銃 トンプソン自動短銃 ブリンデ歩兵銃 各種ヤ銃々身 チエッコ軽機関銃」
8.^ 『陸軍落下傘部隊戦記 あゝ純白の花負いて』 田中賢一著 学陽書房 1976年 P130~131
9.^ 昭和19年2月に作成された大日本帝国陸軍の資料中では、米軍が装備するサブマシンガン(日本陸軍では“機関短銃”と呼んだ)について、トンプソン機関短銃、ライジング機関短銃、M3機関短銃の3点が、鹵獲された米軍資料から転載したと思しきイラスト付きで紹介されている Refcode:A03032193600 『米軍銃器火砲一覧表』 陸軍兵器行政本部 昭和19年2月20日
10.^ 1930年代に福建省に潜伏したタン・マラカは、インドネシアから帰国した客属華僑と知り合い、その下に一時身を寄せていたが、匪賊による襲撃の噂が流れたため、これに備えて華僑の一族がトンプソンサブマシンガンなどの各種火器を準備して迎撃準備に努めていた事を記しており、当時の中国国内でトンプソンサブマシンガンは比較的身近な存在だった事が伺える 『牢獄から牢獄へ - タン・マラカ自伝』 タン・マラカ 著 押川典昭 訳 鹿砦社 1981年7月
11.^ a b c d HEROS Gunバトル ヒーローたちの名銃ベスト100. リイド社. (2010-11-29). pp. pp.190-191. ISBN 978-4-8458-3940-7.